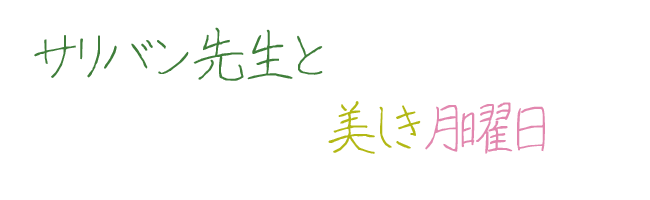
閉じ込められた。
よりによってこいつと。
ジミーは荷物を運ぶのをちょっと手伝ったつもりだった。
ノウェムの兄のゼノは掃除をついでにしだしたので、ジミーもついでにそこにあるコピー用紙にはたきをかけてやった。
俺様超親切! と胸中自画自賛して部屋を出ようとしたら、もう扉は動かなくなっていた。
「おい、動かねえぞ」
がちゃがちゃやっても動かない。
体当たりをしても動かない。鍵の故障というより、誰かが扉の前に荷物を置いてるようだった。
「ぶっ殺す! 中に人がいるのも確認しなかった奴見つけ次第スープにいれるつみれ団子にしてやる!」
「つみれ団子……」
ぼそっと後ろからゼノが呟く。
ジミーはゆっくりとゼノを振り返った。ゼノについてはちょっと苦手意識があった。
妹のノウェムは付き合いやすく、交流もかなりある。
しかし兄のほうといえば、ノウェムの兄ぐらいの認識しかなかった。兄がゼノという名前だということを知っていても、それ以上のことなどほとんど知らなかった。知人程度だ。
「やあ、ゼノ」
へら、と笑顔を作ってみるも、ゼノの表情筋は動かない。
「ここに荷物置いた奴ぶっ殺してえよな!」
「待てばいい」
「食事は?」
「我慢すればいい」
「トイレは?」
「我慢すればいい」
「寂しさは?」
「我慢すればいい」
「空気は?」
「我慢すればいい」
大丈夫だろうかこいつ。そう思ってしまう。
ジミーは窓の外を見た。ごうごうと楓の木が揺れている。
今日は嵐がきている。窓から脱出するのはちょっと危ないと考えた。本当に待つしかなさそうだ。
部屋の中を眺めれば、そこは図書館らしからぬ景色。書庫でないのだから当然本などもない。暇つぶしになりそうなものはなかった。
あるのは1メートルものさしや、壊れた黒板、コピー用紙、古くなった電球などなど。
古臭い埃と黴のにおいの閉塞感を解放するにも窓を開ける必要があったが、それさえかなわなかった。
携帯を取り出して、グリードに連絡をいれてみる。用事があるときの音声が流れたのを合図に、ジミーは伝言を残さずに切った。メールのほうに室番と閉じ込められた旨を書いて送る。しばらくすれば助けはくるだろう。
ゼノのことは何もしらないとはいえ、それは彼の個人的な嗜好を知らない程度のものだ。彼がやっている仕事の内容や、普段どんなことをしゃべるかは知っている。
何度か話しかけてみたことはあるし、今日だって荷物を運ぶ手伝いをしたのは彼が一人で荷物を運ぼうとしていたからだ。
図書館のメンバーがそこまで冷たいわけじゃあない。つまり手伝ってほしいと言えば気づく人はいるだろう。
(言わないんだよなあ、そういうこと)
かといって態度で可哀想をアピールしているわけでもない。
重たい荷物を一人で抱えて、立ち上がったところで電球がこぼれおちた。それを拾って、途中でかわろうと言ってみた。
ジミーから見ればなんでだろうと思うことが図書館にはいっぱいある。
グリードはなぜキリシュのためなら自分を犠牲にできるのか。ノウェムの自信はどこからくるのか。ルリハが植物のために自分のエーテルを削る理由はなんだろう。環が食事に興味がないのは自分に興味がないのだろうか。などなど……
だが結局、愚問だなと最後に思う。
グリードにキリシュより自分を大切にしろと言ったところで彼は理解しないだろう。ノウェムの自信を挫くのはナンセンスだ。ルリハに癒しは自分を削ると説明しても彼女はエーテルを削るだろう。環が食事に感謝をするのは彼が体を壊したあとかもしれない。
言う意味がない。
いう意味がないが、言いたい。
言いたいが、すごく意味がないことだ。
意味がないのに、結局自分が正しいと言いたい。
すごく言いたい。小一時間言いたい。
そして一切相手の間違った主張を聞きたくない。
そんなジミーの独善的主張など、相手は一切聞きたくない。そしてだいたい最後は想像がつくんだ。
わかりたくないし、わかってくれない。
人間の答えはいったりきたりしてもだいたいここに集約される。ジミーが頭がいいとは思えないが、人間が頭がいいとは思えない。
ゼノにも言いたいことがあった。
言わなきゃ伝わらない。
しかしこれは伝えることより伝え方のほうにすごく難しさを感じた。
言えばいいのにと言うのは簡単だ。
言わせるようにするのは難しい。
(別に俺は偉い先生じゃないんだけどね)
色々めんどくさいものはあるが、一番自分の気持ちがめんどくさい。
「図書館ってさ、ヘレン・ケラーの本何冊あるんだろうな」
ジミーは壁にしゃがみこんで、ゼノを見上げた。ゼノは何を考えているかわからない顔で「わからない」と答えた。
「俺はほとんど覚えてないけれど、サリバン先生がTHINKって額に書くシーンだけはずっと鮮明に思い出せるんだ。水と叫ぶシーンよりもずっと」
「ふむ」
「ヘレン・ケラーは何冊図書館にあって、何人の子がサリバン先生を見るんだろうなって考えることがある」
「貸出記録を見てみたらどうだ?」
肩がこけた。ジミーはそういうことじゃあないと思って、言ったところでそれをきっちり説明できそうな気がしなかった。
「読んだことあるか?」
「必要ない」
サリバン先生が必要ない子供なんていないぞと言おうとして、ヘレン・ケラーを読む必要を感じないという意味かと置き換え直す。
「みんなヘレン・ケラーになれるわけじゃあないけど、それはサリバン先生が不足してるからだと思う」
もう一度別の言い方をしてみた。意固地になってるのが自分でもわかった。
「みんながサリバン先生になれるわけじゃあない」
ゼノの答えに、じゃあ誰が次のヘレン・ケラーを見るんだよ。そう反論したい自分がいた。ヘレン・ケラーが耳と目が見えないから仕方がないと受け入れるのか、ヘレン・ケラーを怒りにまかせて叩くのか。どっちもヘレン・ケラーの未来を奪うという意味じゃ同じことだと感じるが、それは違うのか。
ジミーは胸中自分に聞いてみる。
自分はサリバンになりたいのか? と。
ジミーは胸中自分に聞いてみる。
自分はサリバンになれると大それたことを考えているのか。
ジミーは胸中自分に聞いてみる。
自分はサリバンになれるだろうか。
ジミーは胸中自分に聞いてみる。
答えははいといいえをいったりきたりした。
羞恥心がいいえと答えて、傲慢さがはいと答えた。
「ゼノはサリバンになりたい? ヘレン・ケラーになりたい?」
ゼノに向けた質問は、自分の中のぐるぐるを抜けるための逃げだった。そしてゼノにその質問をする無意味さは、当然自分が知っているものだった。
沈黙。
ジミーは壁に背中をつけたまま、ゼノが答えるのを待ったが、答えはかえってこない。
「自分のままでいたいか?」
「わからない」
次の質問にはすぐに答えがかえってきた、ように感じた。
「サリバンやヘレン・ケラーになれると思ったことはない」
ジミーは心の閉塞感から膝を抱えたくなったが、膝をあえてくつろがせてもたない話題をかえようと思った。
「俺の姉貴は女男爵だから書簡だらけで一日中雑務に追われている。悪魔に対する人間たちの苦情に『だったら自分から動け』と返事を書きながら彼女が叫ぶ言葉がビューティフルマンデ! いい月曜日だよなあ」
「今日は日曜日だ」
「明日月曜じゃん。ビューティフルマンデ!」
両手をぱかん、と開いて言ってみる。
残念なことに、こだましたビューティフルマンデ! という声がジミーが一人おめでたい人のように響いただけだった。
自分が滑稽なのか相手が不気味なのかわからない。
ゼノを否定する言葉ならすぐに浮かぶのに、ゼノに何かうまいことを言ってみようと思ったらとたんに詰まる。
ゼノを言い負かそうとして言葉を紡げばどんどん言葉は浮かぶのに、ゼノを負かしたところで何の利益も得られない。
なんだ、自分って悪魔じみたやつだ。
悪魔なのだから当然だろうと言われればそれまでだが、サリバン先生になろうとしてその実デビルだった。
浮かんだ文句を一つずつ、手の中で潰すのをイメージする。
肯定的になんて悪魔は考えない。ジミーももちろん考えない。ただ、これは違うと感じたのだ。
こんな方法で人間を唆せると思うなよ? と自分の中で呟いた。ジミーは人間になりすぎた。
どんな方法なら人間をかどわかせたっけ? 思い出そうとした。
誘惑は欲望に語ればいい、裏切りは苦痛に語ればいい、耽溺は快楽に語ればいい、優しさは忙しさで奪えばいい、人間を破壊したければ寂しくさせればいい、絶望させたければすべて奪えばいい。
「なんか俺ゼノみたいになりたくないなとか色々考えていたけれどすっげ無駄だったわ。ゼノは正しい。ゼノはずっと正しいんだ」
出た結論はそれだった。
自分は悪魔だ。それが仕事だ。休暇中人間界にきても所詮悪魔に戻る。
悪魔が間違ってるわけじゃあないが、人間が間違ってるわけじゃなあい。
ジミーが間違ってるわけじゃあないが、ゼノが間違ってるわけでもない。
「意味がわからない」
「今日は日曜日だし、ヘレン・ケラーを借りた人の人数は名簿を見れば確認できる」
「そうだな」
ゼノはまだ棒立ちしていた。隣に座れよと床を叩くが、彼に座るつもりはなさそうだった。
「あんたの話を聞かせてくれよ」
「何もないよ」
「長生きしてんのに?」
「何もない」
何もないわけがないだろう。何もいいことがなかった。何も面白いことはなかった。何も話すことはない。そんなところだろう。
「それはそれで面白いな。なんもないのにここまで育ったって」
「色々あったってほどじゃあない」
「一つ何か思い出すとしたら?」
ゼノが首をひねって答えを考えだす。
こういうところは素直だよなあと思いながら、ジミーは自分はゼノに何を欲しているのだろうと考えた。
まさか自分がゼノを導けるとは思っていまい。
まさか自分がゼノより賢いと思っていないか。
まさか自分がゼノより立派だと言いたいのか。
まさか自分がゼノの魂を自由にできると思っていないか。
まさか自分の満足のためにゼノを利用してないか。
まさか自分は暇なんじゃないだろうか。
まさか自分は暇なんじゃないだろうか。
暇だ。暇だからジミーは色々考えているのだ。
「子供の頃……」
ゼノはそんなジミーの心の内を知るよしもなく語りだす。
「ノウェムが飴をくれた。嫌いなハッカ飴を」
ゼノの眉が少しだけ寄ったような気がした。
「ノウェムクールミントとか好きそうだしな」
「その飴をどこかに仕舞ってなくした」
そのときはゼノの眉はもういつもの様子だった。
「よくあるある」
「それぐらいだ」
あれだけの時間かけて、そんな思い出が出てくるとは思ってもいなかった。
「飴は嫌いだったんだな」
「甘いほうが好きだ」
「ノウェムが飴をくれたからとっておいた」
「なくした」
「でも思い出したし」
ゼノはもう一度、飴は消えたと呟いた。
飴は消えた。なんだか広がるもやっとした感覚。
「甘い飴だったらどうだった?」
「嬉しかったかもしれない」
「ハッカ飴よりは?」
「そうだな」
「言ってみな。あの時甘い飴が欲しかったって」
「ずっとむかしの話だ」
「唯一の思い出なのに」
唯一の思い出なのに、嫌いな味の飴をもらって、それが消えてしまったそんな内容だ。
飴が買えなかったわけではあるまい。嫌いな飴を妹がからもらったのが記憶なんだ。嫌いだけど大事に仕舞ったのだ。そしていつの間にか親か誰かに捨てられたのだ。
甘い飴だったら何がかわったのだろうと考えてみた。
もしくは甘い飴を欲しがる子だったら何が今、違ったのだろうとも。
じじくささと青臭さが自分をちくちくと刺激して、まるで干し草の上で寝ていた中世時代を思い出した。
体を動かして居心地の悪さを解消していると、外側で荷物が動く音がした。
「荷物、どいたな」
「仕事に戻る」
「俺は飯食いにいく。ゼノ、飯は?」
「いらない」
また我慢すればいい、か。どういう忍耐力だ。
「今度食いにいこう。好きなものは?」
「……プリン」
今日はじめて聞いた、彼の意志のこもったような声だった。
「プリンは俺も好きだ。じゃ、今度プリンな」
ゼノが出て行ったあと、開いた扉からグリードが顔をのぞかせた。
「変な顔」
グリードの第一声がそれだった。
「なんかあったのか」
「なーんもねえよ」
変な顔ってどんな顔してたのか。ジミーはとりあえず全面に笑顔出してみた。グリードは眉をひそめる。
「今、何時?」
「十二時過ぎた頃」
「ビューティフルマンデ!」
そう叫んだジミーにグリードは怪訝な顔をした。
「お前はややこしい」
「カボチャでいいじゃん」
「カボチャだけどな」
「おうともよ」
シンプルに生きたい。シンプルに生きよう。
人間にさちあれ、自分よ愛してる。
ビューティフルマンデ!
TOP |