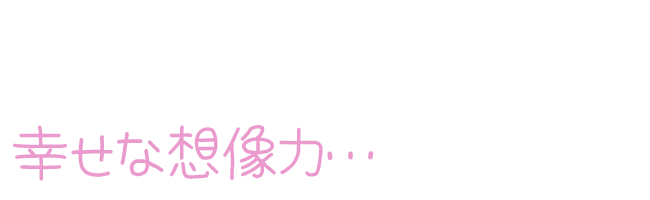
幸せな妄想はある日唐突に終わりを迎える。
「ああー!」
ジミーは仕事中に大声を上げた。
書類を持ってきたラーイはジミーが嬉しそうな顔をしているので怪訝な顔をした。
「どうしたんです? 坊ちゃん」
「俺サイコーなこと忘れてたわ。あのな、俺シャルと婚約していたの。三百年前に」
嬉々として報告したジミーに対して執事の反応はあまりかんばしいものではなかった。
「へえ。もう破棄されたも同然じゃないですか」
ラーイは何をこいつはこんなに喜んでいるんだとばかりにそう言った。
「急いでプロポーズしなきゃだよな!」
「坊ちゃん、本当にその女性はあなたのことを三百年も待ってるのです?」
「じゃなかったら? 俺の悲しい勘違い?」
「悲しい勘違いだと思いますよ。三百年前の婚約を持ちだされたらその女性だって困るはずです」
「言ってみなきゃわかんねーじゃん? もしかしたらOKくるかもだし」
「白魔術師が悪魔にOK出すとか聞いたことないですよ。おまけに淫売でもない美しい魂の処女だなんて」
「おい。シャルのことを変な目で見るんじゃねーよ」
「なんですか。はしたない口調ですね。そんなことこの悪魔執事、まったく考えておりません。ただ、坊ちゃんが玉砕してくることを楽しみに待っているだけですよ」
性格の悪い執事だ。今に見ていろ、シャルアンティレーゼにがつんとプロポーズをして思ったとおりの成果を納めてきてやる。
ジミーは急いでラーイの持ってきた書類をひったくると仕事を始めた。
仕事は半分やっつけ仕事だったような気もする。あとで姉に叱られるのは覚悟しなければならない。
今はこの気持ちを早くシャルアンティレーゼに伝えたい。
花束に何を選ぼう。
白い薔薇、ピンクの薔薇、赤い薔薇……
白い薔薇がいいだろうか。いいや、今の気分はピンクの薔薇だ。
「この薔薇を30本束ねてください」
花屋の女の子は薔薇を束ねてジミーに渡しながら、「プレゼントですか?」と聞いてきた。
「今からプロポーズに行くの」
ジミーは笑顔でそう答える。
自分でも満面の笑顔を作っていることがわかったし、花屋の娘もいっしょに笑顔を作ってくれた。
時計台近くの噴水前にてお待ちしております。
シャルアンティレーゼにそう手紙を送っておいた。
時計台の下は様々な人々が行き交う。
スリの少年、ジプシーの女、愛しあうカップル、子供、母子、グループで行動している学生たち。
たくさんの人たちの中からただ一人を探そうとしていた。
シャルアンティレーゼはいつ姿を表すだろう。
噴水の縁に腰掛けて待っていると、約束の時刻にジミーの頭の上に陰ができた。
顔を上げると日傘をさしたシャルアンティレーゼが笑っている。
「派手な花束ね。遠目でもすぐにわかったわ」
「一番今の気持ちにあってる色を選んだ。垢ほど情熱的でもないけど、白ほど純粋なものでもない」
「ピンクの理由は?」
「喜びの色だと思ったから」
ジミーは恭しく膝を傅き、シャルアンティレーゼに花束を差し出した。
周りの人はその様子に気づいていない。
この空間は現実の世界と紙一重でつながっているだけの世界だ。
シャルアンティレーゼを見ているのはジミーだけだし、ジミーを見ているのもシャルアンティレーゼだけだ。
「結婚してください」
花束をさっと差し出し、心をこめてそう言った。
「触るな望んでないと言うのであればそういうことは一切しないから結婚して。めっちゃ好きだから」
息を呑んで、シャルアンティレーゼからの答えを待った。当然Yesであることを期待して。
シャルアンティレーゼは沈黙して、困ったように目を伏せた。
しばらくして、花束を押し返す。
「教えておかなきゃいけないことがあるの」
シャルアンティレーゼのおじいちゃんがマリーンだということは知っていた。
マリーンは夢魔の父親と高貴な女性の間に生まれた子供だと伝説で記されていることも、知らなかったわけではない。
このままではマリーンが悪に染まると思った母親が修道院にあずけて、マリーンの心から邪悪が消えて不思議な力が残ったとされている。
つまり、こういうことだ。異母兄弟の弟マリーンは白魔術師に、兄ジミーは悪魔として育てられた。
孫のシャルアンティレーゼは自分の遠い親戚にあたる、血の繋がった存在だということ。
とつとつと、シャルアンティレーゼから説明を受けて、そういえば父親は中世時代あちこちで人間の女に種をばらまいていた話を思い出した。
まさか自分の愛した女性が同じ父から血を分かつ存在だとまでは想像は働かなかったし、働いていたとしてもきっとどこかで思考が停止していただろう。
「だから私、一生あなたのことを愛することはないわ」
頭の中でシャンデリアが落ちるような音がした。
しばし呆然とするジミーを置いて、シャルアンティレーゼは申し訳なさそうな顔をして去る。
「シャル……」
シャルアンティレーゼの名を呼ぶ。
どう声をかければいい? 血なんて関係ないよなんてさすがに言えない。
シャルアンティレーゼの背中に伸ばしかけて、伸ばした手を躊躇した。
雑踏の中にシャルアンティレーゼの背中は消えていった。
足元を見れば、ついさっきまで喜びの色だと思っていたピンクの薔薇が無残に落ちていた。
TOP |