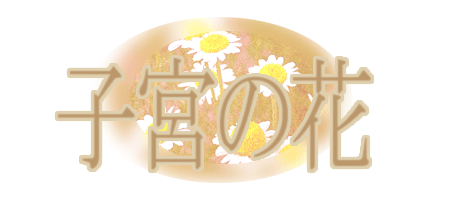
レインマンの恋人
犯罪心理学者を続ける目的がなくなったとしても、その給料で食べているということはその仕事をするのに充分すぎる理由だった。
ギーは去年、オリアーヌ=デュピュイトランを助けたときの功績で犯罪心理学者としての仕事をもらえるようになった。
といっても、犯罪者プロファイラーとしての仕事をやらせてもらえるのかと思いきや、彼が任された仕事はパリの郊外にある、パリ・サンテ刑務所で服役する囚人たちのカウンセラーだった。
犯罪心理学というとすぐにプロファイリングのほうが目立つが、実は犯罪者の更生のほうがメインの仕事になることが多い。
去年の七月から仕事をはじめ、今はもう五月だった。
気候もだんだん暖かくなってきたし、仕事も慣れてきたし、居候先のレインマンと喧嘩することもなかったので概ね平和だった。
ギーのカウンセリングだが、実は人当たりがいいと評判だった。
中には童顔で女顔のギーのことをからかう囚人もいたが、他愛もない話を重ねるうちに、何故罪を犯したのか話してくれるようになった。正直理由は納得できるようなものばかりではなかったが、それはいつものこと。
「あんたは俺を否定しないんだな」
それがよく言われる言葉だった。
ギー自身としては、否定できるほど相手をよく知っているわけではないし、更生させようという気が毛頭なかったのだ。
ただ面接時間中、相手の話を聞いて頷いているだけでお金がもらえるならば下手に口出ししない姿勢だった。
そんな不真面目すぎるカウンセラーのギーだったが、真剣に相談されることに対しては真摯に答えたつもりだ。だから今の評価に繋がったのだろうと思っている。
いつものように刑務所で各希望者との面談を済ませて帰宅すると、マリー・ルイーズの声が聞こえた。続けてレインマンの声も。彼らは口論しているようだった。
「あ、ギー。おかえりなさい」
マリー・ルイーズが先にギーに気づいて挨拶する。
「ただいま。どうしましたか?」
「聞いてくださいよ、ギーくん。マリー・ルイーズは僕の交際に理不尽な理由で反対しているんです」
「理不尽!? よく言うわよ。ギー、エミールが付き合っている相手のこと聞いた? アルジェリア人なんだって」
「アラブ系ですか?」
「だからなんだって言うんですか」
棘のある言い方でレインマンが腹を立てる。恋人の悪口を言われているのだから仕方がない。
「マリー・ルイーズが人種差別をする方だとは思ってもいませんでした」
「兄さん、違うのよ。人種差別なんてしてないわ。イスラム系と付き合うのはすごく難しいのよ! わかってないんだから」
「えーと……」
どう口を挟むべきか悩む。
そもそもあの戒律の厳しいイスラム系にゲイがいるというのが驚きだが、あれだけの人口がいれば、まったくのゼロというほうがかえって不自然なのかもしれない。
「ギーくん、この恥知らずな妹に何か言ってやってください」
「ギー、わからずやな兄さんにびしっと言ってやって!」
ボードレール兄妹に同時に矛先を向けられた。どっちも必死なのが伝わってくる。
「えーと……付き合うのは、ちゃんと覚悟があるなら悪くないと思います」
マリー・ルイーズが何か言いたげに口を開く。
「でも、イスラム信者とスピリチュアル関係を職業にしているあなたが思想の面でぶつからないわけがない。そこのところ、自覚していますか?」
そう、これは重要な問題だ。厳格なイスラム教の教えとレインマンの信じている思想は反りが合わない。
あまりにも的を射た注意だったので、レインマンが黙り込む。きっと思い当たることがあったのだろう。
「諦めませんからね!」
「諦めてよ!」
ボードレール兄妹は最後にそう言うとリビングと自室へと別れた。ギーは話が通じそうなマリー・ルイーズのいるリビングへと向かう。
「エミールの恋人の話って詳しく聞いたことがないです。教えてくれますか?」
「そうなのよ! 私も今日初めて聞いてね、驚いちゃったの」
マリー・ルイーズは金に近い茶色の目を大きく見開いて言った。
「なんでもベルヴィル地区あたりに住んでる、さっきも言ったとおりアルジェリア人なんだけど……職業がタクシーの運転手でね、高校にも行ってないし、家賃を滞納して兄さんが立て替えたこともあるらしいのよ」
「うわー……」
「あ、わかっていると思うけど私、別に人種も職種も学歴も部落差別もないから」
「わかっていますよ」
ベルヴィル地区といえば治安が悪く、ギーはあまり近づきたくない地域だった。アルジェリア人ということは移民だろう。当然金の持ち合わせは少なく、学歴も低く、低賃金で雇える労働者として使われることが多い。
おまけに家賃を立て替えさせたりする金銭にルーズな面がある上に思想の面でも折り合いがつきそうもない。
これだけ条件が揃えば、いくら差別はないと言っているマリー・ルイーズでも「ちょっと」と言いたくなるはずだ。
「エミールはその男の方が本当に好きみたいですね」
「騙されているのよ。でなかったらベッドで黙らされているんだわ」
「後ろの事実は聞きたくありませんでした」
マリー・ルイーズの生々しい言葉にギーは呻く。まあ普段から強姦魔の武勇伝などを聞かされているのでまったくの初心というわけでもないのだが、どうしても苦手だった。
「絶対に別れてもらわなきゃ」
「その方に会われてから決めたほうがいいんじゃあないでしょうか」
「今の条件でギーはどういう男想像した?」
「駄目な男は想像していませんよ? ただエミールとは釣り合わないかもしれませんね」
あんな動きのひとつひとつまで優雅すぎる男と釣り合う人間がいるのかと聞かれたら難しいが。彼の我侭な部分を受け入れられるスケールを考えるとさらに難しい。
駄目男は想像しなかったが、レインマンとお似合いとは言いがたい。
結局、来週のあたま、マリー・ルイーズのかわりにギーがレインマンの彼氏を視察してくることになった。
(この手の話題には関わりたくないんだけどなあ……)
居候先の家主がゲイならばこういった事態も致し方ないのだろう。
レインマンたちはお金に困っていない。占い師とセラピストという職業はどう考えても儲かる職業ではないが、亡くなった父親の遺産は、別れた母親と兄妹が山分けしてもけっこうな量だったようだ。
レインマンは判断が的確だし、マリー・ルイーズは先読みの能力がある。資産運用は充分すぎるほどセンスがあるふたりだった。
だからこそレインマンの金をあてにしている男がいたとしてもおかしくはない。
マリー・ルイーズが色ボケしている兄のことを心配しているのもよくわかるのだ。
兄妹間の問題にギーが首を突っ込むことはしない。しかし巻き込まれた。友達の恋人のことなのに、とても面倒だと感じる自分が嫌だった。