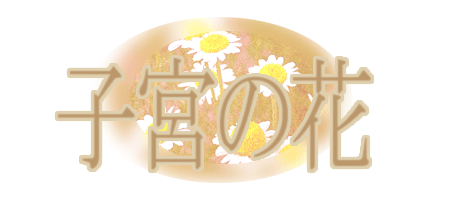
無差別殺人犯のフェリクス
その日の朝は順調なすべり出しだった。
朝起きるといつものようにカフェオレを飲む。レインマンは「珈琲はオーラに悪い」という理由から妹が摘んできたばかりの葉で入れたセージ茶だ。マリー・ルイーズも同じハーブティーを飲んでいた。
昨日喧嘩したからといって、マリー・ルイーズが兄に意地悪をすることもなければ、兄が妹に特別辛辣ということもない。この兄妹は長い間離れていたとは思えないほど意志が通じあっている。
というのも、マリー・ルイーズは先を予知する能力が少しあり、レインマンは生粋のエンパスというのが原因だろう。
彼らはお互いを"察する"という能力がずば抜けて高いのだ。
もっともレインマンに至っては、察する能力が高いからといって必ずしも気を使ってくれるわけではないのだが。
「気を使えない人で悪かったですね」
レインマンがぼそっと呟く。このように思考を読み取っていちいち突っ込んでくる癖はどうにかしてほしい。
機嫌が悪そうなレインマンに、恋人について何か言おうかどうか迷っていると、彼が先に口を開く。
「あなたはお仕事でしょう。早く寝癖直してから行ってください」
口出し無用と言いたいらしい。口も出していないうちからこれだ。
ギーは洗面台で歯を磨き、彼が言ったとおり一本だけくるんとしていた寝癖を直してから仕事場へと向かった。
バスに揺られながら今日の面会者リストを確認する。
シャリーフ=アル=クトゥブ
三十七歳。チェニジア人。
強盗殺人罪。
ジェルヴェ=ルケッティ
三十四歳。フランス人。
ひき逃げ。
フェリクス=ブラック
二十五歳。フランス人。
殺人罪。
まあまあ、普通のリストである。
ギーの苦手な強姦殺人罪がないことにちょっと安心した。
しかし最後のフェリクスの罪名の下に、「無差別」と備考があった。
そこでフェリクスの顔と性格を思い出す。若い男だ。いつでもケラケラと陽気に笑っていて、自分が殺した人間の数が自慢のようだった。
ギーがフランスに戻ってくる数年前にあった、無差別発砲事件の犯人だ。
「こーんなにたくさん死んだんだぜ」
とケラケラ笑いながら説明してくるのだ。
ギーは「そんなに死んだんですか」と言った。
「そー。どう思う?」
「どうも思いません」
「なんとも? きめえとも面白いとも?」
「ええ。あなたはどうでしたか?」
「すげぇすっきりした」
「それはよかったですね」
そんな会話だっけなあ……などと思い出す。全部の会話は思い出せないが、毎回似たようなものだ。飽きもせずずっと同じことを言う。
歳が近いこともあってタメ口だ。だけどギーのことを「先生」と呼んでくれている。
囚人たちのギーの呼び方は様々だが、だいたい「先生」か「ワロキエさん」と呼ぶ人が多い。アランのように「坊や」と呼ぶ人はまずいなかった。
ギーはこの男と話すのはそんなに辛くなかった。鬱々とした過去を聞くわけでもなかったし、恨み言をずっと聞かされるわけでもない。いきなり愛を告白されるわけでもないし、歌をせがまれることもなかった。
ただ、「こーんなに殺したんだぜ」と言う彼に、「そうでしたか」と言えば終わりだった。
だから無差別殺人犯なのにあまりカルテが頭に入っていないのだ。今日の会話もきっとそんなものだろう。
だけどどうして今日に限って、普段あまり頭に止めない記憶が戻ってきたのかがわからなかった。
面談をする部屋でカルテを出し、よく削った鉛筆と消しゴム、ミネラルウォーターを用意する。
いつものように見張りの看守が部屋に入ったのを確認すると、「どうぞー」と声をかけた。
三人のうち最初に入ってきたのはフェリクスだった。
「こんにちは、フェリクス。お元気でしたか?」
「こんにちは、先生」
元気だったかという質問には答えずにフェリクスはお向かいに座る。まあいつもどおりのすべり出しだろうと思った。
あとはいつものように、彼の自慢話を三十分間延々と聞かされるだけだった。
「あと一分で次の人ですが、他に話すことは何もないですか?」
「えー、もうそんな時間? もっと話していたいのに」
「一分以内に言えることはありますか?」
「んー」
考えこむフェリクス。やれやれ、次の囚人はひき逃げ犯のジェルヴェか? と考えていたときだった。
「先生はカモミールの花って好きですか?」
唐突すぎる問いに反応が遅れる。
「カモミールですか。好きですよ、ジャーマンもローマンもどっちも。あなたは好きですか?」
「俺、すごく好きなんだ」
フェリクスが初めてする話だと思ったので面接時間を過ぎていることを気にせず延長してみた。
「ふわふわしていてさ、やさしい色と香りがして、大好き」
「そうですね。ピーターラビットのお母さんもピーターがお腹を壊したときにカモミールティーを入れたみたいですよ」
「あれって腹に効くのか?」
「カモミールの学名はマトリカリアって言うんです。語源はラテン語のマトリックス、子宮という意味です。つまりお腹に効くんですよ」
「俺は子宮ないよ、精巣ならあるけど。でも詳しいんだな、先生」
「ハーブを摘むのが趣味の女性が近くにいるので」
マリー・ルイーズの知識の受け売りだが、まあいいだろう。
フェリクスは構わず話を続ける。
「カモミール、その友達の庭にはもう咲いてる?」
「まだ咲いてないんじゃあないでしょうか。パリは寒いし、今の時期だったらまだ南のほうだけでしょうね」
「そうか、南ではもう咲いているのか。春だな」
「春ですね。もうちょっとして花が咲いたら、乾燥させてここにも持ってきてあげましょうか?」
ギーが親切心でそう言った。フェリクスは目を輝かせる。
「俺、カモミールが見たい!」
「わかりました。今度持ってきますね」
「今すぐ見たい!」
無理を言うと思った。咲いていないと言ったばかりではないか。
「先生、カモミール見に行こうよ」
なんだか雲行きが怪しくなってきたような気がした。何故、彼がこんなにカモミールに執着しているのかがわからない。
「そろそろ次の人の時間です」
強制的に打ち切ろうとした瞬間だった。フェリクスの手がギーの手元に転がっていた鉛筆を奪い取る。それを見た看守が危険を感じて近づいてくると、フェリクスは素早く振り向きざまに看守の喉を鉛筆で貫いた。
部屋中に叫び声が木霊する。フェリクスは鉛筆を引き抜いた。先っぽが折れて看守の首の中に残っている。のた打ち回る看守からスタンガン式の警棒を奪い、ギーを振り返る。
「さ、行こう。先生」
「だ……」
言葉が詰まる。誰か呼ばなきゃと思うのに声が出なかった。
「来るでしょ? 先生」
フェリクスが低い声でそう言った。脅している、来なければ殺してやると。
仕方なしに警備がくるまでの間、いっしょに行動することにした。扉を開けて外に出るとそこにはシャリーフとジェルヴェの姿があった。
「どうしました?」
中の絶叫に怯えるようにジェルヴェが言った。シャリーフはもう何が起こったか察知したようだ。
「逃げるぞ」
シャリーフの言葉にジェルヴェが一歩以上遅れて「え?」と呟く。脱獄囚たちといっしょに足早に刑務所の中を進んで行く。
異常を察知した警備がサイレンを鳴らしはじめる。走る足音が聞こえてきた。シャリーフはフェリクスから警棒を借りるとそれを使って角をこっちに曲がろうとした警備を叩き伏せた。シャリーフが銃をジェルヴェに渡す。ジェルヴェは「ひい」と声をあげて、それをフェリクスに投げて渡した。
「あんた人殺したことないの?」
フェリクスのそれはまるで「お前万引きもしたことないの?」と聞く子供の口調と同じだった。
「俺はただのひき逃げだよ! 過失致死だ」
「殺してるじゃねえか。四の五の言わずに来いよ」
シャリーフが笑ってジェルヴェの手を引く。いざとなったら弾除けにするつもりなのだろう。
逃げる最中にバケツを蹴飛ばしてジェルヴェが顔色を変える。ガラガラと音を立ててバケツは水道蛇口のほうへと転がっていった。
「この間抜け、まだ連れて行く気?」
フェリクスがシャリーフにそう聞く。シャリーフは「盾くらいにゃなるさ」と答えた。ギーもいつ盾にされるかわかったものではない。
ふと、フェリクスが
「いいことを思いついた」
と顔を明るくする。
彼は収容所の入り口に水を引くと、シャリーフに警棒を投げ込むように言った。彼は言っている意味を理解して電圧を目一杯にあげた警棒をその中に放り込む。
放電しはじめた水の境界線を放置したまま、さらに進んで行く。門番をしている警備が銃をこちらに構える。ギーは息を呑んだ。
フェリクスは別に自分を人質になんてしなかった。ただギーを前に押し、盾にしながらぐいぐい進んでいく。
そうしてギーの影から警備を撃つと、そのまま正面の扉を堂々と出て行った。
おそらく警棒が放電をやめるまでは室内の警備は出てこられない。白昼堂々の脱獄だった。