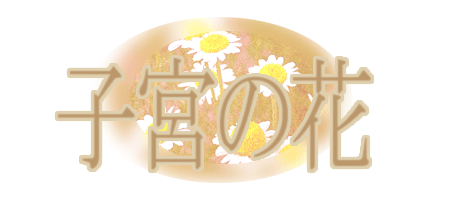
04能力を封じられたレインマン
アランは殺風景な自分の部屋で、この前の日曜日にスケッチした風景に色をつけていた。
アランの絵は風景画ばかりだ。人物画は描かないのか、と聞かれたことが何度かある。そのたびに昔描いた絵を見せることにしている。そこには能面のような、生気のない顔をした人間の顔があった。
「死んだ人間か」と聞かれ、生きている人だと答えたが、生きているように見えないと言われた。
「私にはこう見える」としか言いようがなかった。人間は動く人形にしか見えない。
絵に描かれたかつての恋人は、アランの絵を見てとても腹を立てた。
「これじゃデスマスクじゃない」
と。そのときも「私にはこう見える」と言った。恋人はアランの前でいくつかの表情をつくってみせて
「人間は笑ったり悲しんだり、喜んだり怒ったりするのよ?」
と反論する。無表情が多かったアランに「あんたも笑いなよ」と言った。
笑ってみせようとした。だけどどうすればいいのかわからなかった。
面白いことがあったわけでもないのに、どうやって笑えというのだ。表情筋の使い方がよくわからない。
そうしてようやくできた作り笑いは、口元がチックを起していて、それを見た恋人はアランの元を離れた。
最後に残した言葉が
「あなたの傷は私には癒せない」
だった。癒してほしいなんて思っていなかった。ただ傍にいてくれるだけでよかったのに、拒絶された。
綺麗に笑えないと拒絶される。そう思って綺麗に笑えるように鏡の前で練習してみた。チックは出なくなったし、作り笑いも人並みにはできるようになった。だけどアランはそれでも笑い方がわからなかった。鏡の前で作り笑いをしてみて、自分は笑っているのだろうかと問う。泣いているのか、喜んでいるのか、怒っているのか、そう聞いてみる。
だけど表情から自分の感情は読み取れなかった。
「これじゃデスマスクじゃない」
恋人の言葉がリフレインする。そう、自分の顔はデスマスクだ。恋人の顔も、両親の顔も、顧客の顔も全部同じに見えた。
「アランは、人を殺すときにどんな昂揚感を感じるんですか?」
そう質問したのは玻璃(びいどろ)のように綺麗な青い目を持つ、犯罪心理学者だった。
「昂揚感はあまりない」
「ないんですか」
「ただ、安心する」
もう動かない、もう責められない。
自分の前で笑ったり泣いたりして、お手本にして笑ってみろと言わない。
もう叩かれない、怒鳴られない。
描いた絵を目の前で燃やされて、勉強をするように強制されない。
もう悲しまない、罵らない。
あんたはおかしな子、人と物の区別がつかないなんて。あんたは人並み以下、お母さんを悲しませて楽しいの?
心の中のもやもやが一時的に晴れる。暗闇がお前はお前のままでいいと言ってくれる。そうすると安心するのだ。
「人間ってなんだろう」
アランは呟いた。人間らしさってなんだろう。こんなに個体が違うのに、同一を求められるのか。
「えーと……霊長類、ホモサピエンス、ヒト科……それくらいしかわかりません」
ギーがそう言った。
「よくわかりませんが、生れたときから人間なのだから、それが人間のアイデンティティなんだと思います。僕は猫にも鳥にもなれませんし、猫らしくなろうとも鳥らしくなろうとも思いません」
「人間らしく、も無視か?」
「人間は生れたときから人間ですよ。何度も言いますけど。狼少女だって人間、腕が六本あった少女も人間です。僕もあなたも人間、その他の人も人間。らしいとからしくないとか、それってまず凡例があるってことですよね? 人間とは、の凡例ってなんでしょうか。感性でもの言っていい世界ではないですよ」
大真面目にギーが答える。いかにも学者らしい発想だと思った。
「私は色々な人間らしさを知っているぞ」
「へえ、教えてください」
「まず人間は集団で生活する生き物だ。協力し合って田畑を耕し、家畜を育てる。他の動物より偉いと思っていて、仲間意識は高いくせに、排斥するときも一瞬だ」
「それは人間ではなく人間の生態系ですね」
「生れたときは四足歩行、しばらくしたら二足歩行。老人になると杖をつく」
「なぞなぞみたいです」
「楽しいときは笑わないといけないそうだ。あと思いやりも必要なんだとか。悲しいときは泣き、怒ると怒鳴るそうだ」
「誰が決めたんですか? それ」
「子供の頃教えられた」
「面倒ですね。悲しいときには泣いて、怒るときは怒鳴って、楽しかったら笑って、人に思いやりの心を持つなんて。僕も親に『自然体でいい』って言われましたけど、そもそも自然になろうとがんばる姿が不自然だと思っていました。笑いたいときに泣いたって、怒りたいときに笑ったって、誰も困らないと思うんですけど。人の表情や感情までいちいち頓着しないでほしいです」
アランは変な子だと思った。別にギー自身が笑いたいときに泣くような人間じゃあないのはわかっている。自然に笑えて、自然に泣けるはずだ。
「おかしな子だね」
「ええ、ええ、どうせ変ですよー」
監禁されているという極限状態でのこの間延びした口調。本当に変な犯罪心理学者だった。
自然も不自然もない。人間は生れたときから人間だと言ったのは彼だった。
アランの中で一番しっくりくる説だった。
――臨時速報です。
テレビの音で我にかえった。付けっぱなしにしていただろうか。
――午前十一時、パリ・サンテ刑務所から三人の囚人が脱獄しました。
「物騒だな」
自分も物騒な人間なことを忘れて思わずひとり言を呟く。
――逃亡した犯人の名前はシャリーフ=アル=クトゥブ、ジェルヴェ=ルケッティ、フェリクス=ブラックの三人です。
まったく聞いたことのない名前といっしょに、囚人の画像が表示される。どいつも面構えが悪いと嘲笑っていると、見覚えのある顔まで表示された。
――囚人たちは人質にカウンセラーのギー=ワロキエを拘束中とのこと。詳しくわかり次第続報します。外出の際はお気をつけください。
思わず口があんぐりと開く。もう元の番組に戻ったというのに、しばらく画面を見つめ続けた。
「あの坊やは殺人鬼ホイホイか?」
自分といい、殺したフランチェスカといい、一年に一回のペースで危険な目にあっているではないか。
とりあえず小腹が空いたので昼食をとることにした。カップ麺をセットして、ヌードルができあがるまで待っている間、部屋の隅に置いてあった油絵が目に入る。いつぞや描いた、ギーの絵だった。
どこかぼんやりした表情なのに、ひんやりと透明感のある絵。あの青年のとぼけた雰囲気がよく出ている。
その視線が訴えかけてくるのだ。そのヌードルを寄越せ、と。食い意地の張ったプロファイラーだったことを思い出す。
「こっち見るなよ」
背中を向けてもカンバスの方向から視線を感じる。さすが自分の絵、存在感だけは美術館の中でもぴか一なのだ。
無視してヌードルを啜ったが、食いしん坊の視線がより一層強くなった気がした。アランの小腹が空いたように、逃亡中の自分も小腹が空いているんだと訴えてくるのだ。
涙よりも叫び声よりもうるさく訴えかけてくる、お腹の鳴る音が聞こえてきそうだった。
アランは途中でフォークを置いて、ギーの絵に布を被せに行った。
布さえ被せてしまえば存在感のあるアイスブルーの目も効力を失う。ほっとしたように残りのヌードルも食べてしまおうかと思ったときだった。
今しがた、布をかけたギーの絵を振り返る。視線を感じたからではない。視線を感じなくなったから振り返ったのだ。
もしこの先、ギーが死ぬことになんてなったら、あの青い目はもう光を宿さないのだろうか。
もう笑うこともないし、怒ることもないし、変な歌を口遊むこともない。文字どおりのデスマスクだ。
そのとき自分は安心するのだろうか。もうギーは動かない、罵らない。お前は何ひとつ変わらなくていいと、また闇が囁くのだろうか。
動かない彼の目を想像した。きっと死んだ瞬間はぞくりとするほど美しいのだろう。だけど時間が経てばその目は曇って、最後は朽ちるのだ。
そうして思い出の中にだけ、美化された、かつての理解者というギーが残るのだろうか。なんだか腹が立つ。お前なんて自分の心に揺さぶりをかけてくる、食い意地の張った男でしかないくせに。
何かが自分を駆り立て、アランは春物のコートを掴むとそのまま玄関の外へと出た。
同様にギーが攫われたという内容は、レインマンとマリー・ルイーズの元にも届いた。
マリー・ルイーズはショックで声が出ないようだった。レインマンも「またか」とは思ったが、また無事に帰ってくるという保証もない。
「あの、待ってください」
やっと声が出るようになったマリー・ルイーズが報告して帰ろうとする警官を呼び止めた。言った。
「兄には透視能力があるんです。ギーの居場所をリーディングできるかも」
「マリー・ルイーズ、彼が一番思い入れのありそうなものを持ってきてください」
「わかった。お菓子のレシピ集持ってくる」
マリー・ルイーズがキッチンに走って行く。リビングで警官を待たせながら、レインマンは自分に落ち着くよう言い聞かせた。彼女が使い古された大学ノートを持ってくる。
雑誌の切り抜きがいっぱい貼ってあるノートの上に手を置き、目を瞑る。何が見えてくるだろう。
「……兄さん、何か見える?」
「見えません」
「……え? なんで?」
「ちょっと待ちなさい、マリー・ルイーズ。まだ見えないだけかもしれないし」
しかし待てども待てども、普段ならうるさいほど流れてくるあいつの思考が見えてこない。
「どうしたものでしょうね……」
「兄さん、珈琲かお酒飲んだの?」
「飲みませんよ。そんな泥水や昼間からワインなんて」
珈琲のことを泥水と言いながら目を開ける。やはり何も見えてこなかった。
「お引止めして申し訳ありませんでした」
警官たちに帰ってもらう。
室内を見渡すと、マリー・ルイーズだけでなく、使用人たちもギーを心配しているようだ。
「兄さん……」
「何ですか?」
「ギーは」
「死にませんよ」
思考を読んで、先に結論を言う。
「でも」
「死ぬ未来が見えましたか?」
「ううん。でも、無事な可能性、低い……」
用済みになった段階で消されるのは確実だろう。それがどの段階でそう判断されるかにもよるが。
「コートをとってきてください」
使用人がレインマンのコートを持ってくる。それに袖を通し、財布と携帯をポケットに仕舞う。
「傘の用意を。パリに向かいます」
「兄さん、ギーを探すつもり!?」
「いいえ。ちょっと恋人のところまで」
「兄さん!」
今度は怒りのこもった声だった。レインマンはマリー・ルイーズを振り返る。
「しばらくギーくんを探すから会えないことを伝えるだけですよ」
「なんで、なんでギーより先にそいつのところに行っちゃうの? 信じられない、馬鹿、アホ、冷血漢」
「マリー・ルイーズは品がいいですね。こんなときですら三単語しかなじる言葉が浮かばないなんて」
レインマンは傘を持つとそのまま屋敷を出て行った。なんだか怒り心頭のマリー・ルイーズにかける言葉が見つからない使用人たちだけが残される。
パリの街は雨が降っていた。
晴れでも曇りでも関係ない。レインマンが外に出れば必ず雨が降るのだから。
ベルヴィル地区に向かう道のりを歩きながら、レインマンは先ほどのことを考える。ギーそのものにフィルタがかかっていて、まったく見えなかった。
ただ、これは初めてではなかった。二度目だ。
一度目、それは自分の恋人――リヤードの思考がまったく読めなかったことだ。リヤードはそれだけでミステリアスに見えた。口を開けば自分と同じくらい性格の悪い男だが、それでも魅力的に見えた。
「あなたは何故心を隠しているのですか?」
と聞くと、彼は
「普通はみんな見えないもんなんだよ。勝手に覗くてめぇがいけないんだ」
と言った。ただ心が読めないというだけで、何が隠れているかわからない、プレゼント箱のような気がした。
それまでのレインマンにとって、触れればほとんどの情報が一瞬で流れ込んでくるのが日常だった。
ところが相手が心の内を打ち明けてくれることがこんなに嬉しいことだと思ったことがあっただろうか。毎回会うのが楽しみだった。今度は何を知ることができるだろうか、と。
(まあリヤードのことは置いておくとして……)
問題はギーの居場所だ。ギーまでフィルタがかかるとは思っていなかった。あの思考の読みやすい男がどうして今日に限ってこんななのだろう。
もしかして自分はエンパスの能力がどんどん鈍磨してきているのだろうか。そのうち普通の人間になってしまうのだろうか。
(普通の人間になったからといって、なんなんです?)
それが普通なのだ。生れてから今に至るまでのレインマンの常識が人からずれすぎていただけ。
父親は「人の思考を勝手に謁見する行為は盗みに等しい」とレインマンに言った。
そう言われても見えたり聞こえたりするものは仕方がないではないか。見えるのが当たり前なのだから、そんなことを言われても困った。
しかし、もし自分がエンパスでなくなったとしたら、この空間は静かになるだろうな、と思った。ただの物理的な音しか聞こえなくなるとしたら、とても静かだ。
レインマンはリヤードとふたりきりでいるのが好きだ。心の声が聞こえない、彼の声は聞こえる。とても静かで、落ち着く。
いかんいかん、と思考を立て直す。ギーを探すことが最優先だ。エンパスの能力がなくなるとしたらそのあとにしてほしい。
そう思ったときだった。
――ギーはどこに連れて行かれた。
低い誰かの心の声が聞こえてくる。地を匐うような低い波動だ。レインマンはこの大嫌いな波動の正体を知っている。
周囲にアランがいないか見渡した。絶対にこの近くにいるはずだ。
傘の影に隠れて最初は見えなかったが、やがて路頭で何かを物色しているアランを見つけた。
レインマンはそちらのほうに近づいて行く。
「今度は誰を殺すおつもりですか? アラン」
声をかけられて、アランがこちらを見る。レインマンを確認すると、首を傾げる。
「たしか個展を見に来てくれた……」
「ええ。チェスターくんの依頼で嫌々、あなたの絵を見に行った占い師のレインマンと申します。よしなに」
アランが面喰らった顔をする。きっと自分が睨みつけているからだ。
「それで、こんなところから傘の群を眺めていたところで、ギーくんは見つからないでしょうけどね」
「家に閉じこもっているよりはマシだ。お前もきっとそうだったんだろう?」
黙り込んだ。じっとしていられなかったのは本当だ。アランは不思議そうに呟く。
「はて。今、私は坊やのことを口にしたかね?」
「僕が思考を読んだんですよ」
「便利なものだな」
アランはそう呟くと、レインマンに聞いた。
「その能力はあいつを探すのに役立つと思うか?」
「さあ、どうでしょう。先程がんばったのに結果はかんばしくありませんでした」
「ならば私ががんばるしかないな」
「何をですか? 千里眼の能力があるとか」
「そんなのはない」
「ならばどうするっていうんですか。一般人がひとりでどうにかできる範囲ではないですよ」
アランはこちらを見たまま沈黙する。彼は何も言っていないが、思考が流れ込んできた。
「協力しろって言いたいんですか?」
「お互い彼が無事のほうが、色々と助かるだろう?」
「まあそうですけど」
自分はともかくとして、アランはギーが無事だと何が助かるのかよくわからない。しかし思考回路を読む限りでは人並みに心配しているのだ。
「わかりました。一時的に協力関係を結びます」
今、逃亡犯の心理が一番わかりそうなのは、犯罪者プロファイラーよりも彼のほうだと思った。