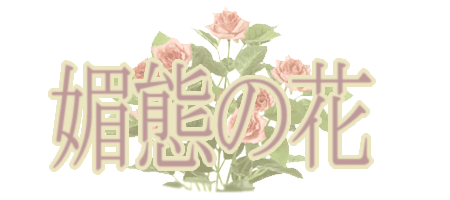
05/15
本日は初めての大学講義だ。少しドキドキしながら教室に入ると、自分とそう年齢の変わらない若者たちがこちらを見る。
「こんにちは……」
緊張したままへらっと笑うと、何人からか挨拶が返ってきた。
「今日から臨時講師をやることになったギー=ワロキエです。緊張しているのでお手柔らかにお願いします」
くだけた雰囲気の笑い声がいくつか聞こえた。あまり手厳しい生徒がいないようで安心する。
「では、さっそく講義を始めます。とりあえず出席はあとでサインしてもらうとして、僕からみなさんに質問です。犯罪心理学についてのイメージを教えてください」
ひとりの生徒が挙手をして、
「犯罪者をプロファイリングするのは犯罪心理学ですよね?」
と言った。
「それも犯罪心理学のひとつですね。他には?」
「犯罪者がどんなことを考えているか分析するとかは?」
「それもそうですね。他には?」
特に答えが返ってこないみたいだったので、次のステップに進むことにした。
「じゃあ、犯罪者プロファイリングと犯罪者がどんなことを考えているか分析する、というところに視点を置いてみます。どういうことをやると思いますか?」
しばらくして、何人かが手をあげる。
「犯罪者にインタビューする」
「犯罪の事例をたくさん読む」
「事件の解決に協力する」
「殺人を未然に防ぐ」
割と近い意見から間違った意見までさまざま出てきたなあ、と思いながらギーは言った。
「ええと、じゃあみんなの犯罪心理学のイメージがわかったところで、とりあえず僕が考える犯罪心理学とは、についてお話しますね」
だんだんドキドキしていた心臓が落ち着いてくる。ゆっくりと話し始めた。
「僕も最初、犯罪心理学って猟奇殺人犯とかを捕まえるための手段だと思っていたんですよね。しかも犯罪者が誰なのかわかっちゃうスーパー心理学だって。でもそんなものがあるわけありません。FBIの犯罪者プロファイリングは犯人が現場に性的ファンタジーを残しているときしか役立たないし、捜査心理学は強姦か強盗の場合にしか役立たない。何より格好いいどころか地味すぎる仕事でした。写真は怖いし、気持ち悪い犯人と対談することもあるし、寝ても冷めても猟奇殺人のことばかり追いかけるとんでもない学問です。中途半端にミラノ大学で犯罪心理学の授業さえとらなければ、僕はシカゴに行って勉強しようなんて思いませんでしたね」
いきなり犯罪心理学をやらなければよかったと言い始める講師にみんなが笑った。
「犯罪者プロファイラーはただの犯罪マニアには務まらないということを最初に認識しておいてください。犯罪者と同じ気持ちになったり、だけど常識的な心も忘れない、柔軟な心が必要です。だけど繊細すぎても使い物にならない。でも覚えておいてください、犯罪心理学はとても繊細な学問です。犯罪者たちは自分勝手な理由で人を傷つけますが、その実、愛情に対してすごくコンプレックスのある人が多いんです。もちろん事例はそれだけじゃあないですが、彼らはとてもデリケートな人たちです。興味半分で対面してはいけません。犯罪とも、犯罪者とも、真剣に向き合わなくてはいけないんです。『何故そんな犯罪をやったのか』理解できる理由ばかりではありません、『そんな理由で人を殺して いいのか』答えは出ません、『この人は死に値するのか』僕たちが決める問題ではありません。だけど犯罪心理学者は犯人の心を理解する努力が必要です。犯人と真剣に向き合う、それが犯罪心理学だと僕は思っています」
教室の中がしーんとなった。熱弁しすぎたか? と思って気まずそうに笑ってみる。
ちらほら、と拍手が聞こえてきた。いちおう成功したようだ。
「まあ、それを踏まえて、最初の授業は犯罪心理学についてどう思うかということをディスカッションしてもらおうと思います」
最初の授業はうまくいきそうな雰囲気だった。
授業が終わってから食堂で食事をとった。ベーコンスクランブルエッグと厚切りのトースト、サラダのランチにカフェオレを飲みながら、無意識に周囲を見渡していた。
(今日は、いない?)
アランは今日はいないのか。それともただ単に別のところで仕事をしているのか。
食事を終わらせてトレーを返している最中、アランが入れ違いで入ってきたが、ギーのことは一瞥もせずにランチのメニューを眺めはじめた。こちらにはノータッチらしい。
「ギー?」
「うわぁ!?」
後ろからいきなり話しかけられてギーは悲鳴をあげた。振り返るとフランチェスカがいる。
「フランチェスカ、びっくりさせないでください」
「誰か気になる女の子いたんでしょう? 女好きめー」
「誤解ですよ、そんなことありません」
ギーはこほん、と咳払いをした。
「大学の講師、順調?」
「最初の滑り出しはまずまずですね。改めてありがとうございます」
「何言ってるのよ。親戚同士でしょう、困ったときは助け合わないと」
フランチェスカは陽気に笑ってそう言った。彼女は十七歳のときから比べてかなり大人っぽくなったと思う。目の周りにアイラインがくっきり描いてあるせいだろうか、いつの間にか化粧をする年齢になったのだな、と思った。
「それじゃ、僕は家に帰るので」
「えー。いっしょに食事しようと思ったのに」
「先に食べちゃいました。今度待ち合わせしていっしょに食べますか?」
「今度っていつ? 明日? 明後日?」
「来月です」
フランチェスカがあきらかに不服そうな顔をした。
「ギーってあまりモテないでしょう」
「大当たり。まったくといっていいほどモテません」
「女の子が食事に誘っても自分がお腹いっぱいだからとかいう理由で断っちゃうからモテないんだ。この、ばかー」
「ばかーと言われましても……」
別に親戚の子と恋愛ごっこをするために大学の講師をしているわけではない。婉曲に断っているのだということが分からないのだろうか。
「どこ? ギーのハートを奪った女学生さんはどこにいるの?」
「は? いませんよ、そんな人」
「だってさっき、あっちの方角見ていたじゃない!」
「わーっ!」
アランの方角を指差すものだから、慌ててフランチェスカの手を下ろさせて、声をひそめた。
「やっぱり可愛い子がいたのね?」
「可愛くないですよ」
「うそ、ブス専?」
「どこでそんな言葉覚えてきたんですか。もう」
呆れるばかりである。フランチェスカは下から覗き込むように上目づかいでギーを見つめた。
「ギーは今どこに住んでいるの?」
「友達の家です」
「今度遊びに行っていい?」
「いえ、その……駄目です」
「なんで?」
「友達と言っても、そんなに親しい関係の友達じゃあないんですよ。なんかはずみでお世話になることが決定しちゃって……だからガールフレンドを連れていったりはできません」
「私のことガールフレンドって思ってくれているの?」
「それは、そのう……」
口ごもるギーに笑いながら、「相変わらずそっちの話になるとてんで駄目ね」とフランチェスカは言った。
「じゃ、帰るんでしょう?」
「はい」
「私はどのランチにしようかなあ……」
メニュー表を眺め始めたフランチェスカを置いて、ギーは食堂を出ようとした。
刹那、誰かに背中を見つめられているのを感じて後ろを振り返る。一番最初に確認したのはもちろんアランだが、こちらのことは気にしていないようだった。
(気のせいかな……)
気のせいでなかったとしてもアランがこっちを見ていたのだろう。そう思うことにして今度こそ食堂を後にした。