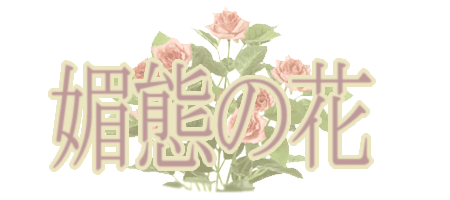
06/16
昨日はボードレール家の住人が早めに寝付いたため、家に帰ってきてもシャワーを浴びることができなかった。早朝から熱いシャワーを浴びて、髪を乾かしてワックスをつけていると、いつもどおりの時間に起きてきたレインマンが洗面所の扉を開けた。
「おはようございます、レインマン」
「おはようございます。昨晩は随分遅かったんですね。何かあったんじゃあないかと心配でしたよ」
「ああ、すみません。大学の知り合いの人といっしょに夕食を食べていたんです」
アランと会ったことを伏せてそう言った。
レインマンの表情が途端に険しくなり、そしてギーの耳を引っ張ると言った。
「随分アラン=アレキサンドラと親しくなったみたいですね!」
記憶を読み取られた。心配させまいと思って言わずにいるのに、勝手に人の頭の中を覗くのだから趣味が悪い。
「誰が趣味が悪いですか。心配させまいと思って隠すそれがいけないんですよ、あなたの場合進んで破滅の道に突っ込んでいるようなものです」
「いだだだだだ!」
耳朶を抓りあげられて悲鳴をあげると、間近でレインマンが真剣な顔で言った。
「いいですか? アランは別にあなたに愛してもらいたいとか思っているわけじゃあないんですよ。あの人は人を愛するとかそんな生易しい感情の通用する男ではありません。ただ単に、あなたを欲望の捌け口にしようとしているだけです」
「そ、そうかもしれませんけど……」
「そうかもしれないけれど、なんですか?」
咎めるような語調でレインマンが聞き返す。
「別に僕はアランと特別懇意になろうとか考えていないですよ。あっちはどうか知らないけれども、今のところ僕に危害を加えるつもりはないみたいだから当たり障りなく接しているだけで……」
「どうでしょうかねー」
嫌味たっぷりにレインマンが笑うと耳を抓っていた指を離した。
「あなたは一度アランの思考回路を見てみるといいですよ。A・アレキサンドラ展を見に行ったことがあります。彼の絵には欲望がぎっしり詰まっている。破壊衝動、性へのカタルシス、みんな『綺麗な風景画ねー』とか言っていたけれども、僕から言わせれば猥褻物を見せられている気分でしたよ。あの人は愛情に飢えた可哀想な人とか、ギーくんに好意を持っているけれどもそれをうまく表現できない困った人とか、そんなのには分類しがたいんです。人を殺す瞬間でしかリビドーを鎮めることができない生粋の変態です。まだ死体相手に興奮する趣味のほうが品がいい」
「そこまで言いますか? あの人って関わりかたさえ考えれば、更生できるような気がしますけど」
「それは犯罪心理学ですか? それとも臨床心理学ですか? それともあなたのアランボケした心理学ですか? あなたの好きな心理学の世界でもの言ってあげますよ。ストックホルム症候群です」
「ストックホルム症候群がまだ続いているわけないでしょう。やめてください」
「あなたは本当どうでもいいところには繊細なくせに、こういうところで馬鹿なんですよ。毒だか薬だかわからずに彼のちょっとした言葉を心理学という調味料で味付けして咀嚼し続ける。僕ならあんな気持ち悪い男は即座に毒と判断して吐き出しますね」
レインマンの言っていることは間違っていないと思う。普通の人から見たら、猟奇殺人者なんてただの気持ち悪い人間だ。その人間がどんなことでつまずいてそうなったかなど、どうでもいい。これは学生時代、ギーが自分の先生にも言われたことだったが、ギーは犯罪者の気持ちに感応しすぎて、正常な人の心や被害者の心を忘れがちなのだ。それではいけないと、よく注意された。
「僕はエンパスとしてもあなたに注意しているんですよ。人の感情に感応しやすい人は、相手の感情を自分のものにしない術を身に付けなきゃだめです。ラカンの理論にもあったでしょう、『相手の欲求がいつの間にか自分の欲求とすり替わっていた』と。あなたがアランのために彼の父親を憎む必要なんてこれっぽちもないんです。心理学やっていても自分の感情には鈍感で、そのくせ心は人より壊れやすく繊細にできすぎているんですよ、あなたは。気づいてください」
てっきり腹を立ててこれだけまくし立てているのだと思ったら、レインマンが次にこう言った。
「僕はあなたを心配しているんですよ」
心配させてしまった。なるべく気を遣ったつもりが、逆に。
「あなたはもっと僕を頼るべきなんだ。そんなの僕は迷惑ともなんとも思っていません」
そう言い捨てて、レインマンは洗面所をあとにした。
自分はアランに対して特別な感情を持ちすぎなのだろうか。これはストックホルムなのだろうか。相手の欲求が自分の欲求とすり替わっているのだろうか。相手の心の中で動くものは見えるのに、自分の心の中はまったくわからない。
その日の午後は家庭教師の仕事があった。
「先生は好きな人がいるの?」
その質問が授業とまったく関係ない質問だったことにすぐに気づけなかったのは、朝方にレインマンに言われた言葉を思い出していたからだ。
「いいえ、いませんよ?」
「じゃあ私にも勝機が……」
「なんの勝機ですか。テストでクラスメイトに勝ってくださいよ」
まったく違うところで勝負をしようとしているオリアーヌに呆れたように呟いた。
「でも先生、先生みたいに格好いい人はすごくモテるんでしょう」
「まったくモテませんよ。僕は恋とかそういうのに奥手すぎるんですね」
「今までどんな人と付き合ったの? 好みのタイプとかある?」
「付き合ったことがあるのは過去にひとりだけなので比較する対象がありません。タイプとしてはそうですね……控えめな人だった気がします」
「控えめな女の子が好きなんだ?」
「いやわかりません。たまたま好きになった人が控えめだっただけで……実は僕けっこうな面喰いなので、講義の席で隣に座った女の子をナンパしました」
「ナンパするの? 先生」
「ナンパはイタリアの挨拶ですから。でも僕はその挨拶すら億劫でナンパしたのはそのときが最初で最後です」
「純情なんだね」
「どうでしょうね」
ギーは肩を竦める。自分が純情だと思ったことはないが、恋愛に疎いのには自信がある。おそらく恋をしにくい体質なだけで、ひとたび恋に落ちれば相手を落とすまで粘るくらいのことはするだろう。
「でも、先生が気づいてないだけで周囲の人は先生に興味があるかもしれないんだよ?」
「たとえば今勉強すっぽかして恋バナに華咲かせているオリアーヌとか?」
「そうそう。先生との相性を占い師に占ってもらったんだけれどもね、まずまずいいみたいなの」
「へえ。まずまずですか」
柔和に笑ってみせる。まずまずよかろうがまずかろうが、十三歳の女の子と付き合う気など毛頭ないが、恋をしている少女はきらきらしていて可愛らしいと思った。
「でもね、占い師が言うのよ。ギー先生は今、人生最大のモテ期到来中だからライバルは多いって。本当に心当たりないの?」
「いくつか心当たりはありますけど、ひとりは親戚の女の子で、あとは妙に僕に執着している男がひとりいて、どっちも勘弁ですね」
「うっそ、男も!?」
オリアーヌがびっくりしたように呟き、そして声をひそめて言った。
「そういうときはね、左薬指に指輪をつけておくのよ」
「指輪ですか?」
「そう。誰かもう先約がいるってフリしておくの。そうすると相手も諦めるから」
「ああ、なるほど。いい考えですね」
「そしてあわよくば私がギー先生をいただく」
「声に出てますよ、オリアーヌ」
十三歳の子にいただかれるほど自分は理性の弱い男ではない。というよりも中学生の口からいただくなんて言葉が出てきたことがまずびっくりだった。
「さて、次は数学やりましょうか」
話題をさらりと勉強に戻す。オリアーヌは恋の話題は年頃の子以上にませているが、勉強の実力は年頃の子をかなり下回る。一方ルノーは恋の話題はコンプレックスの塊だが、勉強は満点に近い。家庭教師は大変だ、学校の先生なんて職業だけは絶対にならないぞ、と思ったところで今自分が大学の講師だったことを思い出した。自分の思っている姿とやっていることは必ずしも重なるわけではないようだ。
ひととおりテストの復習をしたあとにデュピュイトラン家を出て、坂を下り駅へと向かった。たまにはいつもと違う道を、と思って選んだ道の途中に可愛らしい雑貨屋さんがあった。オリアーヌはこういうものが好きそうだな、と思って中を覗くと、ピンク色のバスフィズやお菓子のような香りのアロマキャンドル、白い食器やアクセサリーの類がところ狭しと並んでいる。
「マリー・ルイーズにひとつくらい買って行こうかなあ……」
彼女にはいつもお世話になっている。だけど調香師の彼女がただの雑貨屋に並んでいるようなアロマキャンドルでは気に入るかわからない。ボードレール家は上質のバスジェルを使うため、バスフィズを買うわけにもいかない。服の趣味が合うかわからないから服を買うわけにもいかない。
ふと天然石のピアスを発見した。なかなか幻想的なアクセサリーで、彼女の少し魔女っぽい雰囲気に合うのではないかと思った。
「すみません、これと……」
指差したそのすぐ下に、シンプルな指輪を見つけた。女性用のデザインだが、とても可愛らしい。
「あとこれも」
思わず衝動買いしてしまった。昔から可愛いものに目がないから自分はすぐ散財してしまうのだ。しかも自分で身につけられないようなデザインまで買ってしまうから結局女友達にプレゼントする羽目になる。自分が女の子だったらああいうアクセサリーをつけたい、服を着てみたいと思うものを友達にプレゼントするという歪んだ貢ぎ癖をどうにかしたいギーだった。
店を出て、買ったばかりの紙袋を開けてみる。指輪は色のついたジルコニアがライン状に並んでいるシンプルな指輪だ。
(男がつけても大丈夫かな?)
指のサイズとしてはギリギリ入るかもしれない。問題はつけてもおかしくないか、だ。
中指には入りそうもないけれど小指には大きすぎる。はめるとしたら薬指だが、どっちの指にはめるべきか。
ふとオリアーヌが人避けに左薬指につけるといいと言ったのを思い出し、左薬指にはめてみた。
はまった。少しきついかもしれないが、鬱血するほどではない。街灯の明かりを反射して自分の指がきらきらと光る。左薬指に指輪をはめたのは何年ぶりだっただろうか。
「って、脱けない!」
ためしにはめてみたはいいが脱けなくなった。石鹸でこすれば取れるだろう、自分の馬鹿加減を呪いながら仕方なくそのまま帰宅することにした。
「ただいま帰りました」
ダイニングに顔を出すと、先に食事をしていたレインマンとマリー・ルイーズがいた。
「マリー・ルイーズ。おみやげがあります」
「お菓子?」
「アクセサリーです。可愛い雑貨店があって」
紙袋を渡すと、マリー・ルイーズが嬉しそうに包みを開け始めた。隣からレインマンがギーをつつく。にっこり笑って、
「僕にはくれないんですか?」
と言うのだ。
「あなたの分はありません」
「なんですって。マリー・ルイーズにおみやげがあって僕にないんですか?」
「兄さんは小さい頃からおみやげをくれない親戚には冷たいのよ。ギーも気をつけなさいね?」
「エミールのイメージって最初と比べてどんどん崩れていきますよね。嫌な方向に」
レインマンの我侭ぶりに呆れるやら感心するやらしていると、彼は目ざとく左手を見て言った。
「左の薬指に指輪をはめていますね」
「あ、これは……」
「僕避けですか?」
「何言ってるんですか。脱けなくなっただけですよ」
何故そこまで皮肉屋なのか不思議で仕方がない。
「おみやげを買ってこなかったのは謝りますけど、何をそんなに腹立てているんですか」
「なんだか面白くないだけですよ。今からパリまでおみやげを買いに行きなさい」
「なんですか。往復一時間半ある距離をおみやげだけ買いにもう一度行かせるって。どれだけおみやげに執着しているんですか」
「おみやげに執着しているんじゃあありません。おみやげが貰えなかったことに執着しているんです」
「同じことです」
たまにしょうもなく子供っぽいことを言うレインマンの我侭に悩んでいると、彼はこう言った。
「どうせ僕は、チェスターくんみたいにあなたと冗談言い合える仲じゃあないんでしょうに。僕流の冗談は相当キツイってことを教えてあげます」
「あのですねえ……」
昨日の早朝に考えていたことをレインマンが読み取って気にしていることはわかった。どうしようもなく威張りくさった、意地悪が大好きな占い師を見る。
「あなたには割りと格好いい、狙っている人がいるんでしょう? どうなりました」
隣のマリー・ルイーズが息を呑む。レインマンの表情が変わった。
「自意識過剰男! 別に僕がゲイだからって誰彼かまわず性対象にするわけじゃあないですよ。あなたのことなんて微塵も好きじゃあありません」
「兄さん、例の人とうまくいってないからってギーに当たっちゃ駄目だよ」
「おだまりなさいマリー・ルイーズ。この男は僕にだけおみやげを買ってこないばかりか、甚だしい勘違いをしているんです」
「あーはいはい。兄さん、おみやげは明日私がパリに行ったとき買ってくるから」
レインマンを宥めて部屋に返したあと、マリー・ルイーズがギーに苦笑いした。
「兄さん今ちょっと神経質だから」
「意地悪な人が神経質なときはこちらがつらいですね」
「ああいう威張りん坊にはね、軽くマシマロでも与えておけばいいのよ」
「だめですよ。あの人、全然躾けられてないじゃあないですか。きっと欲しいものは全部手に入る人生だったんでしょう。手に入らないものがあると腹が立つってことは、そういうことです」
「うちはお金持ちだし、そんなに苦労せずに育ったからね。だけど欲しいものを手に入れるときの兄さんの集中力はすごいのよ? 他は全部投げやりになるくせにそれにだけは没頭するから、結果的には手に入るの」
「それって周囲はすごく迷惑でしょう」
困ったようにギーは呟いた。マリー・ルイーズは笑って首を振る。
「私は、兄さんが戻ってきてくれただけで嬉しい。家族だもの、離れ離れは嫌なの。距離が離れている分には我慢できる、心の距離までそのうち離れちゃいそうで、それが不安だった。でも兄さんは十八歳の飛び出していったときとちっとも変わってなくて……あ、ちょっとだけ落ち着きは出てきたけれども、それ見ていたらね、すごく安心した」
傍目から見ていてもマリー・ルイーズは本当にレインマンのことが好きである。そしてレインマンもマリー・ルイーズのことを大切にしている。
「あとね、私はギーが来てくれたことも嬉しいのよ? 兄さんがあそこまで我侭発揮しているところ久しぶりに見た。きっとギーに甘えているのね」
「しょうもない甘ったれですよね、あの人」
「でもいっしょに暮らすまでそう思わなかったでしょう? 本当猫かぶりが上手よね。逆かしら、身内に甘えすぎるのよね。どこまでしたら相手が怒るかわかっていないから、際限なく甘えちゃって。だから悪く思わないでね」
少し甘えられる分には嬉しい。頼りにされていると感じるからだ。だけど今のレインマンの態度には少しだけ戸惑っている。
自分と同い年の男と会話している気がしない。まだ二つ年下のチェスターと会話しているほうが「年下だから」という視線で余裕がもてるくらいだ。
「僕はエミールに甘えているんでしょうか。同い年としてもうちょっと我侭を控えてほしいと思うのは」
「逆じゃあないの? 私は、ギーはもっと我侭言っていいと思うの。エミールほど我侭になられちゃ私の身がもたないけれども、ギーは自分が『欲しい!』って思ったものでも我慢しちゃうでしょう」
「僕も物欲強いですよ? 欲しいものはすぐに買う癖ありますから」
「男なんて物欲強くてなんぼでしょう。無欲な男なんてお坊さんになっちゃうわよ。私はエンパスじゃあないけれどもわかるわよ、あなたは可愛いものが大好きで、子供の頃はファンシーなものが女の子と同じくらい部屋にいっぱいあった?」
「ありましたね」
「でも今は部屋にほとんどないわよね?」
「ないですね。興味がなくなったわけではないんですけど、なんだかおかしいかなって思って」
「どうしてそう思ったの?」
「滅多に嘆かない父親が、十六歳の男子高校生が熊のぬいぐるみ抱いて寝ているのを見て、僕が学校に行っている間に部屋の中のものを全部捨てたからです」
「それ以来いい年した男がぬいぐるみを抱いて寝るのはおかしいと思うようになったのね?」
「実際おかしいでしょう。たぶん誰が見ても気持ち悪いと思いますよ」
マリー・ルイーズは「そう?」と首を傾げた。彼女はそう思わないのだろうか。
「ギーは女の子に生まれなかったことを疑問に思っている?」
「うーん、たまに考えますね。だからといって性同一性障害ではありませんよ、僕はやっぱり男だと思うし」
「でも女の子みたいに可愛いものに囲まれていたいのよね。ふりふりのお洋服とか着てみたい?」
「僕が着ても似合いませんので、似合う女の子にプレゼントしていました。ブティックにいるのは楽しいです」
「女物の下着を身につけてみたい?」
「さすがにそれは……」
「恥ずかしがらなくたって、私は平気よ」
「いや、恥ずかしがっていません。興味ありませんって」
「じゃあふりふりのお洋服までが許容範囲か……」
「そうですね」
隠そうと思って隠していた過去ではないが、必要以上に人に言ったことのない話をしながらギーは自分はジェンダーなのだろうかと考えた。
「たぶん、完全にそうではないにしろ、ジェンダーみたいなところはあるんだよ」
そして考えていたタイミングと同じくらいにマリー・ルイーズがそう言った。
「二階の部屋、ぬいぐるみでいっぱいになっても私は気にしないから」
「そう言われましても」
「私の部屋なんて、香水瓶と精油と観葉植物でいっぱいなのよ? やっぱり自分の部屋は自分で住みよいように改造しなきゃ。兄さんなんて小さい頃、部屋にでっかいクラスター置いていたし」
「クラスターって?」
「水晶の原石の塊みたいなやつ。ひとつでもものすごく高いのに、それがいっぱい部屋にあったから洞窟の中みたいだった」
「今はないんですか?」
「さすがにアメリカには持っていけないからね、兄さんがいなくなってから全部オークションで売却。いい金額になったわよ」
たしかにひとつですら高いものがそんなにたくさんあったのなら、まとまった金額になったのだろう。
「本当に私たちのことは家族だと思ってくれていいのよ。遠慮しないで」
「……努力します」
マリー・ルイーズはいい子だ。レインマンも我侭だが別に悪い人間ではない。だけど家族のように接してほしいと言われても、住んで一ヶ月程度でそれは難しい。特に使用人がいるような豪邸で好き放題していいと言われても、戸惑うばかりだ。
マリー・ルイーズと別れて二階の部屋に戻ろうとしたとき、レインマンの部屋が目に入った。
どうして彼とうまくやることができないのだろう。自分はできることなら仲好くしたいと思っているはずだ。あっちもそう思っていると思う。だけど何かがうまくいかない。