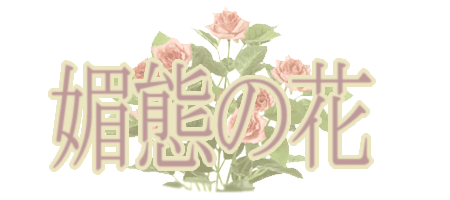
06/17
翌日は午前中がオフだった。ギーは時差を計算して、久しぶりにチェスターに電話をかけた。
――クラークです。
「僕ですよー、チェスター」
――ギーか! 元気にしていたか? 電話かかってこないからちょっと心配だった。
「国際電話ってお金かかるじゃあないですか。メール書くにも当たり障りのない話題がなくて」
――まるで当たり障りのある話題はあるみたいな言い方だな。そっちでうまくいってないのか?
「仕事や生活は割りと順調なんですけれども、思わぬ人に出会ってしまいました」
――もったいぶるなよ。誰だ?
アランのことを話そうと思って一瞬口を開いたが、考えてみればチェスターにこのことを話すと正義感の強い彼が野放しにするはずがなかった。
――どうした?
「親戚の子に会ってしまって」
――それのどこが思わぬ人だよ。まさかアランにそっちで会ったとか、そういうびっくりが起きているんじゃあないだろうな?
「違いますよ! 会うわけないじゃあないですか」
思わず声が裏返る。警察にバラしたらアランが黙っているわけがない。必ず草の根分けてでもギーを探し出して報復してくるだろう。
――アランに遭遇したら俺に言うんだぞ? ああいう凶悪犯を野放しにしているわけにはいかないからな。
「善処します。ってフランスに来ているわけないでしょう。だいたいまた遭遇するわけないじゃあないですか」
――まあそうだよな。それにお前の「善処」ってお前の筋力くらい頼りにならない言葉だ。レインマンとはうまくやっているか?
「ところがあまりうまくいってないんですよね。僕が悪いと思えないんだけれども、困っています」
――例えば?
「いちいち突っかかってくるんですよね。意地悪言われたり、往復一時間以上かかるところにパシらせようとしたり」
――お前がシンデレラ状態なのはわかった。待っていても王子様はこないから現実的にその屋敷から逃げればいい。
「別にシンデレラほどひどい待遇は受けていませんよ。レインマンの妹はとてもいい子ですし、彼だって今狙っている男を落とせば機嫌は治ると思います」
その瞬間、電話の向こうのチェスターが沈黙した。
「チェスター、電波状況が悪いんですか?」
――お前今さらっとすごい重大なこと言わなかったか? 男? 男落とすってどういうことだよ。あいつそういう趣味あるのかよ、きめえ。そんな奴の家に同居しているのはマズいだろ。お前狙われるよ、間違いなく。
「きめえとか言わないでくださいよ。昨日散々僕には興味ないって言っていたから大丈夫です」
――ジャンだって学生時代シンディーには興味ないとか言っていたくせに今じゃあアツアツだよ、今度同棲するらしいし。男女が同棲するときに清い仲であるはずがない。「いっしょに住んであたしを養って、ただしセックスは抜きよ」って通用すると思うか? 屋根のある家はそこだけじゃあないだろ、今すぐ出るべきだ。
たしかに男女の場合は遅かれ早かれそういう展開になるだろう。
チェスターはその後もずっと「お前の無防備という罪について」を語り続けた。もちろん国際電話はギーのほうからかけたため、料金を気にしないですむからできる業だ。ひとしきりお説教を食らったあとに電話を切った。液晶画面に表示された四十分という時間を見て、電話代を計算するのをやめた。
講義の前に食堂で不動産物件を見ていると、目の前に影ができた。顔をあげると目の前にフランチェスカがいる。
「何か勉強しているのかと思った。すごく真剣なんだもの」
「引越ししようと思って」
「友達と喧嘩したの?」
「似たようなものですね。ぎくしゃくしちゃって」
ギーが困ったように笑った。
「安い物件見つかった?」
「なかなかいい物件が見つかりません。収入がすずめの涙だからかな。もうひとつくらい仕事を増やさないと引越しは難しいかも」
「うちに来る?」
フランチェスカがそう切り出した。
「私もルームメイトと喧嘩しちゃって、彼女が出て行ったばかりなのよね。ちょっと家賃が苦しくて、ギーが入居してくれると助かるんだけど」
「でも、いくら親戚だからってそれはマズくないですか? いちおう僕は男で、あなたは女なんですから」
「別の男とシェアするよりはずっと安全よ」
フランチェスカが肩を竦める。ギーは「考えておきます」と言った。
さて、引っ越したいという話題をどう持ち出すかはギーにとって問題だった。レインマンはエンパスだ。ギーがどうして引っ越したいと思ったかの理由もすぐにバレるし、そして彼は今機嫌が悪い。
ブックカバーのかかった文庫サイズの本を片手に、左手でマシマロを摘みながらリビングでリラックスしている彼に近づいた。
「何の本ですか?」
「ランボォの詩集です」
ギーはランボォが苦手だ。なんとなくロマンチストで、気障ったらしいのが好きになれない。
「何か僕に言いたいんでしょう?」
「何も言わなくたってわかるでしょう」
「僕がエンパスだと会話を面倒くさがるんですか。そのうち口が退化して深海魚みたいになりますよ?」
ひどい譬えだ。おおよそランボォの詩集を読む人間の比喩とは思えない。
「引っ越そうと思っています」
「引越し先は決まったんですか?」
「親戚の子がシェアするルームメイトを探しているので、そこに入ろうかと」
「それってこことそんなに変わらないでしょうに。一人暮らしがしたいんじゃあないんですか?」
「こことそう変わらないわけがないでしょう。部屋の広さはもっと狭いし、環境だってここよりもっと悪いところですよ」
「じゃあここにいればいいじゃあないですか」
「でも引っ越すって決めたんです」
レインマンがこちらを睨みつけてくる。普段ならば思考を読み取って何か言ってくる彼が、視線だけで威圧してきた。
「わかりました。さようなら」
彼はそう言うとまた視線を詩集に落とした。その瞬間、ギーは自分がレインマンに甘えていたことに気づいた。彼が自分の思考を読み取れるのを利用して、言いにくいことを言わないままにしてしまった。彼はきっと傷ついている。だけど普段のように意地悪な言葉はかえってこなく、かわりに沈黙だけが続いた。