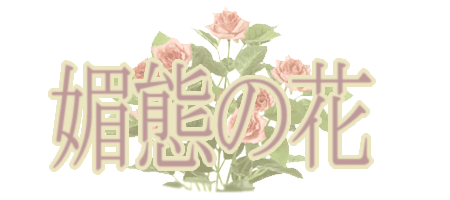
07/06
病院の退院自体は三日後にできた。警察からの事情聴取が少しだけあり、荷物の後片付けにまた少し時間をとられ、そうして火事で消失してしまったために随分減った荷物を再びボードレール家に運び込んで、やっとひと段落した頃の話である。レインマンが寝込んだ。
「風邪、というわけでもないみたいですね」
風邪でもない、持病があるわけでもないのに、躰が重くて動かないと言っているレインマンの体温を計ったギーが呟いた。
「まあ僕はだいたい理由はわかっていますけれども」
「なんなんですか? レインマンが倒れている理由って」
「カルマの法則を破ったからです」
「カルマの法則?」
物憂げにため息をつくと、レインマンは言った。
「ギーくんはあそこで死ぬ運命だったんですよ。だけどその未来を僕が勝手に塗り替えた。だから僕にその分のしわ寄せがきたんです」
「そんなことあるものなんですか?」
「あるものなんですよ。あなたはわからないかもしれないけれども、人間の生きている世界には見えないものの力がいっぱい関わっているんです。僕はその彼らのプログラムを勝手に書き換えたから、それを刈り取らねばならなくなった、それだけです」
そこでレインマンはもう一度深くため息をつく。呼吸をするのもしんどそうな彼をギーは心配そうに見つめた。
「僕はあそこで死ぬはずだったんですか?」
「そうですよ。それがどうかしましたか?」
「じゃあ何故、こうなると分かっていてもレインマンは僕を助けてくれたんですか?」
「それは――」
「ギー、オリアーヌから電話よ」
レインマンの答えを障るようにマリー・ルイーズが電話を持ってきた。
「ごめんなさい。あっちの子、今すごく大変なことになっていて」
「知っていますよ。デュピュイトランさんのほうに行ってあげなさい。僕は大丈夫ですから」
レインマンはこういうときに、自分の傍にいてほしいとは言わない。一見我侭し放題な彼だが、我侭を言うところと抑えるところの加減はあるようだ。
オリアーヌの用件は最後に一度ギーと会いたいとのことだった。ギーは彼女のためにクッキーを焼いて持って行った。
「おみやげですよ」
そう言って渡したクッキーを見て、オリアーヌは笑った。「美味しそう」と言ってひとつ口に運んだ。
オリアーヌとの雑談は楽しかった。しかしそれは、彼女が無理をしている証でもあった。彼女は全然弱音を吐いていない。
「先生、私は悔しい。お父さんは犯人なんかじゃあないのに」
ようやく最後の最後で彼女はそう呟いた。たしかにポールが犯人という説にはあまり納得がいかない。しかし社会はそれで納得したし、警察も今のところその線で落ち着いている。
「どうしてそう思うのか詳しく教えていただけませんか?」
「だってお父さん、『昇進が決まった。明日はパーティーをやろう』って言っていたのよ? そう言っていたのに、急に帰ってきたら部屋に鍵をかけて三日間出てこなくて、おかしいと思って開けたら……自殺していたなんて」
「たしかにおかしいですね……」
「そうでしょう?」
納得がいかない、とオリアーヌは呟く。しかしだからといって、オリアーヌにもギーにもそれを覆す手段がないのが残念だった。
「先生……」
「オリアーヌ、先生を長くお引止めしてはいけません」
何か言いたげなオリアーヌをジュゼが叱った。
「いえ、いいんですよ。僕なら大丈夫ですので」
ジュゼに頬笑み、オリアーヌを見た。
「……先生との授業、楽しかった」
彼女は精一杯笑顔をつくってそう言った。本当に、もう最後なのだ。このませた少女に勉強を教えることはもうないのだ。