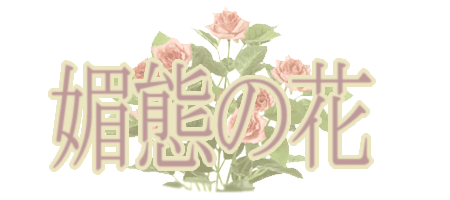
07/01
今日は雨が降っている。天気予報では曇りと言っていたはずなのに、どうしてだろうと思っていたらその答えはすぐにわかった。
「レインマン」
呼び鈴が鳴って玄関を開けると、傘とバスケットを持ったレインマンが立っていた。
「どうしたんですか? リムジン外に止めてあるんですか?」
「仕事場から歩いてこちらまで来ました。おかげでパリは雨に降られましたが、まあいいでしょう」
入っていいとも言っていないうちからレインマンは家の中にあがってきた。
「けっこう広いじゃあないですか。古いですけど」
「築百年くらいらしいですよ?」
「へえ、由緒正しい建物なんですね」
レインマンはテーブルの上にバスケットを置きながら、ギーを振り返った。
「マリー・ルイーズがお菓子を焼いたから持って行くように言ったんですよ。大丈夫です、僕は黙っておくからそのまま捨ててくださっても構いません」
「そんなことしませんよ。美味しくいただき……」
言いかけて、中のぺたんこになったシュークリームを見てギーは固まる。ひとつ手にとってみるが、シュー生地がクッキーのようになっている間に玉子の黄身が固まったようなカスタードが挟んである。
「これは……」
「美味しくないので味見せずに捨ててもらってけっこうです」
マリー・ルイーズがお菓子作りの腕が壊滅的なのは本当のことらしい。彼女には申し訳ないが、見た目からしてあまりに問題ありだったので捨てることにした。
レインマンは勝手にそこに立てかけてあった写真立てに手を触れた。
「これはルームメイトの写真ですか?」
「ええ、フランチェスカとタルティーニ家のみんなです」
「そうですか……」
レインマンはため息をついて、その隣にある熊のぬいぐるみにも触れた。
「レインマン、どうかしたんですか?」
「真実を言うべきか否か迷っていたところです」
「真実?」
また勝手に自分やフランチェスカの記憶を読み取ったのか。この覗き癖はどうにかならないのかと思った矢先、彼は意外なことを言った。
「フランチェスカさんですよ、犯人は」
少しだけ沈黙が訪れた。窓を濡らす雨の音が耳障りなほどよく聞こえた。フランチェスカが犯人だと? 猟奇殺人の犯人がフランチェスカだとでもいうつもりだろうか。
「違います。放火魔の正体がフランチェスカです」
「それ、確かなんですか?」
「嘘ついてどうする気ですか。まったく」
「だってフランチェスカは僕の親戚ですよ? 僕の両親を殺す意味がさっぱりわかりません」
「あなたの両親はお菓子作りについてはとても厳しかったみたいですね。フランチェスカさんは随分ストレスをためていたみたいです。あとちょっと前にあなたをつけていたストーカー、あれも彼女があなたの住んでいるところを探っていたみたいです」
「そんなことありません。あるはずがない」
「じゃあ僕が嘘をついているって言うんですか?」
レインマンはギーに手を差し伸べて言った。
「ここにいるのは危険です。シャンティーに帰りましょう」
「少し考えさせてください……」
レインマンは困ったような顔をして、「また明日来ますね」と言うと玄関のほうへと歩いていった。
「それでは、ごきげんよう」
彼は軽く会釈をすると、そのまますたすたと雨の降る雑踏へと消えていった。
レインマンがさっきまで見ていた写真を見る。そこにはフランチェスカとタルティーニ家の面々が写っている。フランチェスカが犯人だと? そんなことがあるというのだろうか。
「ただいまー」
フランチェスカがそんな日に限って早く帰ってくる。
「雨降ってきたからさ、洗濯物取り込んでくる間だけお休みもらったの。って……そうか。ギーがいたんだったね。やっぱり家族がいるっていいなあ」
フランチェスカがいつものように人懐こい笑みを浮かべる。だけどギーは笑い返すことができなかった。
「ギー?」
「フランチェスカ、あなたはあの火事の日どこにいましたか?」
「え?」
「アリバイ」
手短にそう呟いた。フランチェスカは「もう随分昔のことよ? 忘れたわ」と呟いた。たしかに四年前のアリバイなど、普通は覚えてはいないだろう。だけどそのときの彼女の表情に、少しだけ違和感を感じ取ったのはレインマンが先程あんなことを言ったからだろうか。
「あ、そんなことより私、仕事に行く前にお茶飲みたいな。ギー、何か入れてよー」
この様子はたしかにいつものフランチェスカと同じだ。ギーはいったん考えるのをやめようと思い、お茶の準備を始めた。フランチェスカが犯人だとしたら、事は尚更慎重に進めなければならない。幸い自分はこの家に住んでいるのだ、彼女のいない間に探せば何か証拠になるものが出てくるかもしれない。そう思った瞬間、頭を何かで強打されてギーはキッチンに転がった。
意識が飛ぶ瞬間に目の端に映ったのは麺棒で自分の頭を殴打したフランチェスカの顔だった。思考が黒い海の中に潜って行く。
黒い海の中に沈んでいた。海面に上がりたいのに、なぜか躰が重くて動かない。自分の耳元で誰かが「沈んでしまえ」と囁いている。
(生きたい、死にたくない)
海の中なのに涙が溢れそうだ。呼吸が苦しい。錘がついたようにもがいてももがいても、どんどんと水面が遠のいていく。
そのときだった。ものすごい力でギーの腕を掴んで引き上げる力があった。それが天使なのか悪魔なのかさえわからず、ギーは生きたいと望んだ。
目が覚めたとき、最初に目に入ったのはマリー・ルイーズの心配そうな顔だった。
「ここは……」
頭がずきっとする。頭がぐらぐらして意識がうまく定まらない。
「強く殴られたみたいだから、無理しないで」
マリー・ルイーズが隣からそう言った。
「ここは病院」
「フランチェスカは?」
「家に火をつけて逃げたそうよ。エミールがあなたを助けたの」
よりにもよって、また放火か。だんだん定まってきた意識の中で手のひらをもちあげてみると、軽く火傷している。
「まいったな……」
ギーは薄笑いをして呟いた。自分の直感なんてまったくあてにならない。フランチェスカならば信じられると思ったのだ。なのに裏切られた。いいや違う、最初から信じるに値しない人間を信じてしまった自分が愚かだったのだ。
「ギー」
マリー・ルイーズが心配そうな声でギーに話しかけてきた。
「あなたさえよければ、シャンティーにまた帰ってこない?」
「でも……エミールは怒っていませんか? 彼に失礼な理由でボードレール家を後にして、そしてこんな事件に巻き込まれた僕に対して」
「それは……」
マリー・ルイーズが複雑そうな顔をした。
「怒っていますよ」
唐突に病室の入り口のほうから声がした。麻の詰襟の服に、黒髪の端を結い紐で結っている姿は見間違えようもなく、レインマンのものだ。
「あなたという人は、僕が『ここに残ればいい』と言った言葉を無視して女にほいほいついて行って、しかもそれがただの女ではなく放火魔で、殺されかけて、非力な僕が熱い思いをしながら必死で助けたのに、まだ僕が怒っているとかそんなことを気にして戻ってこないつもりでいるんですからね」
レインマンはギーの額をぴたぴたと叩きながら言った。
「あなたみたいなすぐに攫われるヒロインみたいな男は誰かの保護下にいたほうがいいんですよ。四の五の言わずに帰ってらっしゃい」
ベッドに寝たまま、レインマンを見上げた。彼は眉をつりあげてむっすりした顔をしていたが、そう怒っているようには見えなかった。というよりも、精一杯怒っているフリをしているだけで、本当は嬉しそうな表情。
「では、またお世話になります」
「わかればよろしい」
レインマンは踵を返すとさっさと病室を後にした。マリー・ルイーズがにこにこしながら言った。
「兄さんはギーが戻ってくるから嬉しいのよ」
「あの捻くれさえ直してくれれば少しは可愛いんですけどね」
ギーも苦笑いする。レインマンは大切な友達だ。