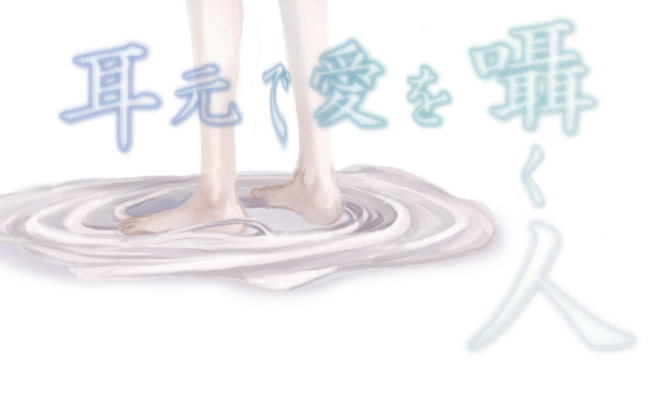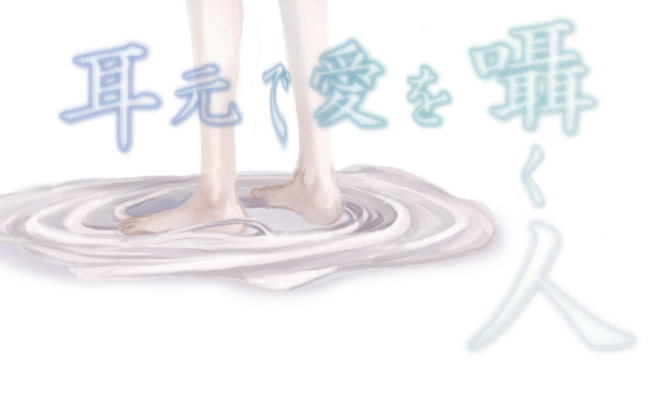「Magnifica! Sei bellissima!」
僕が自分のことを、実は綺麗なのかもしれないと思ったのは十四歳のときだった。
声変わりもしていない僕のことを少女と間違えた馬鹿な外人がいた。
塾帰りの僕は思わず自分の格好を見る。普通のTシャツとYシャツ、そしてぶかぶかのジーンズ。この格好で男に見えないのだとしたら、僕は相当女顔なのだろうと思った。
その外国人は茶に近い金髪をしていて、目は茶色かった。身長が高くて割りとしっかりした体格の若い男だ。隣にいた日本人の男が少しだけおかしげに「ぷっ」と笑う。
「たしかに、美人だよな」
不躾にこちらを眺めてそう言ったその男は、とてもきれいな男だった。自分が女顔だとしたら、あっちは美男子、美形という言葉がぴったりだ。荒々しいイメージではあるが、はっきりした輪郭と形のよい唇、やさしい穏やかな目をしたお兄さんだなと思った。
「なあ、お前この男の子気に入ったの?」
「なんだよそれ、彼女じゃないの?」
舌ったらずではあるが、慣れたように日本語で外国人が応じる。さっきの一瞬出てきたよくわからない外国語は思わず地が出ただけで日本語も喋られるようだった。
いきなり話しかけられ、そして目の前で繰り広げられる会話。思わず無視して帰ることもできずに棒立ちしていると金髪の男は僕の顔を覗き込んですごく馴れ馴れしく、笑った。
「君すごく美人だよね。本当に男の子?」
「んな……な……」
僕は自分の性別を男以外だと思ったことはない。僕の声を聞いて彼は「ボーイソプラノだぜ? タマ」と言った。タマと呼ばれた男がこちらを見て「あー…ウィーン少年合唱団みたいな声だな」と応える。
「ねえ、名前なんて言うの? 俺の名前はカヴェリエーレ=カヴァッツォーニ」
「こいつさ、名前が韻踏んでるって信じられないだろ? ああ、俺の名前は高楠環(たかくすたまき)って言うの。君は?」
ふたりして馴れ馴れしい。僕は少しだけ黙ったあとに「鶴谷颯(つるやはやと)」と小さな声で名乗った。
「鶴谷って変わった名前だな」
「お前の高楠だって変わってるだろ?」
「お前のカヴェリエーレだってな」
お互いにお互いの名前を変わっていると言ったあとにカヴェリエーレが僕のほうをもう一度ちらりと横目で見た。
「ハヤト、すごくいい名前だと思う」
「たしかに雰囲気あってるよな。なあ颯」
「馴れ馴れしいですよ、お兄さんたち」
僕はつい、反抗的にねめつけてそう言ってしまった。ふたりは顔を見合わせてから、漸く自分たちが不躾な態度をとっていたことに気付いたらしい。
「いや悪い、悪かった。俺イタリア人だからこれが普通だと思っていたよ」
「俺もここ暫くずっとイタリア暮らしだったもんなあ。日本の感覚忘れてた!」
さっきのはイタリア語だったのか、などとどうでもいい思考が頭を掠めた。僕は携帯を確認する。九時半……早く帰らないと塾の宿題を終わらせる時間がない。
「あの…僕はそろそろ失礼したいのですが、」
「えー、なんで? もっとお話していたい」
カヴェリエーレが僕の手首を掴んでそう言った。僕の中に少しだけ恐怖が生まれる。隣から高楠さんが「カヴェリエーレ、怖がってるだろ?」とそれを制す。
「俺たちこの近所に仕事場あるから、また会うかもな?」
「何を……仕事にしているんですか?」
僕が訝しんで聞いてみると、カヴェリエーレが「建築」と答えた。
「カヴェリエーレ=カヴァッツォーニって世界的じゃあないにしろイタリアではちょっと有名な建築家なんだよ。建築士じゃあなくて建築家ね、アートのほう。俺はただの建築士だけど」
「なんで自分を卑下したみたいな言い方してんの? お前。お前が無理な重量計算してくれないと建たなかったもん多いだろ?」
どうやらふたりは同業者関係での知り合いらしい。ここらへんに立派な建物を建てる計画なんてあったっけ? そう考えながらもう会うこともないだろうと思いつつぺこりとお辞儀をして帰った。
家に帰ると母親が「少し遅かったわね」とキッチンから声を投げかけてきて、僕はさっきの彼らのことを言って無駄に母親を心配させることもないかと思い、コンビニで立ち読みしていたことにしてから冷めた夕食をレンジで温めて遅めの食事を摂った。
部屋で小論文の宿題をやりながら、そういえばとさっきのふたりを思い出した。カヴェリエーレはちょっと怖い感じだったけれども高楠さんはすごくやさしそうに見えた。ずっとイタリア暮らしでしょう? しかも有名建築家の友達で、きっとあの人も優秀な建築士。顔は男の僕が見ても俳優かって思うほど格好よかったし、たぶんモテるんだろうなあと思った。
僕は別に誰も好きな子がいないからモテるとかモテないとかそんなのどうでもいいけれども、きっとああいうお兄さんは彼女もきっとすごく美人な元モデルのお姉さんとかがいるんじゃあないかな。美形でキャリアありで優しい男を見逃す女なんているはずがないよ、すごいなあ。
まあもう会うことはないだろうけれどもね、雲の上の人たちだよと思って宿題を終わらせたあとに眠った。
翌日、学校で授業を受けて部活をやってから帰宅途中、僕はコンビニに寄った。本当は学校のきまりで帰りに道草しちゃいけないことになっているんだけれども、いちいち家に帰ってから雑誌を買いにいくのは面倒なのだ。
ファミリーマートの自動ドアが開くと僕は素早く今日発売の週刊誌のところへ行った。それを手にとり、そのままレジに持って行こうとしたときだった。
「だーから、お前は蕎麦無理だって。ヌードル食べるのすごく下手じゃん」
「お前こそそのでかいティラミスなんだよ?食いきれるのか」
「漢のスイーツシリーズしらねえのかよ? こら、置けよ。お前絶対箸なんてもの突き刺すしか使い方しらねえんだし」
聞き覚えのある声が弁当コーナーのほうから聞こえて、僕はそちらを振り向いた。
「……やっぱり、」
僕のひとりごちた言葉に先にカヴェリエーレが反応した。
「颯! いきなり翌日遭遇とは俺たちけっこう運命感じないか?」
「おい、いたいけな中学生いじめるなよ」
何故中学生ってバレたんだろうと思ったら考えてみれば今僕は中学校の鞄を持って、制服を着ていた。こんなに声の高い高校生がいるはずもないし、すぐにわかるだろう。
彼らはめいめいの欲しいものを持ったままレジにやってきて僕の雑誌をいきなり取り上げると、同時にレジに出した。
「学生、奢ってやるよ」
「ありがたく思え」
高楠さんがにやりと笑って、カヴェリエーレが財布から全部まとめて樋口一葉で支払った。
コンビニから出て、カヴェリエーレに雑誌を手渡された。
「……ありがとう」
「どういたしまして。なーんだ、男の制服着てるところみると本当に男なんだな」
「当たり前でしょ」
「口調はちょっと女の子みたいな喋り方なのにな」
余計なお世話だと思いながら閉口した。僕は自分が女だなんて、女子みたいだなんて思ったことはない。あんな口うるさい、いつも集団で行動しなくちゃ何もできないような奴らとは違う。
「カヴェリエーレ、お前ちょっとゲイの気とかあったりするの?」
「いーや。ただちょっと可愛いなあと」
「あるんじゃねえか」
「いやないですよ? 颯が女の子だったら食事に誘うのにって思っただけで」
「あるんじゃねえか」
「まあ男でも誘うかもしれないけれど」
「やっぱりあるんじゃねえか」
三度高楠さんがあるんじゃねえかと突っ込んだ。僕は少しずつ、カヴェリエーレに警戒し始める。それに気付いたように彼はにかっと笑った。
「いやただの軽口だからな? 俺はただ颯はベリッシマって言ってるだけで」
「ばっかやめろよ、ベリッシマひでえだろ。女じゃねえんだし」
「ベリッシマ?」
僕が聞きなれない、おそらくイタリア語だと思われる単語について聞き返すと、ふたりは「すげえかわいこちゃん」「超美しい女」と口々に説明した。なんだか腹が立って僕はまた黙り込む。
「ほら、怒っちゃったぞ?カヴェリエーレ」
「ああ、賞めたのに?」
「颯、イタリアの奴らってみんな思ったことは全部口に出す奴多いから気にすんなよ?」
高楠さんがカヴェリエーレのフォローをしたから僕は頷いた。本当はすごく嫌な奴だと思ったけれども。
「今仕事終わったところ?」
「うん。職人たちが帰っちゃったから着工できなくてさ、測量はすんだんだけれども今から俺の部屋でふたりで作業するつもり」
「高楠さんの部屋で?」
「高楠さんなんて呼ぶなよ、環でいいんだよ。どうせこいつのことなんて脳内でカヴェリエーレって呼び捨てしてるんだろ?」
図星を高楠さんに突かれてから自分で環さんと呼ぶことにしようと意識した。
「颯、もし暇なら来るか?」
カヴェリエーレが僕にそう聞いてきた。
「行ってみたい気はするけれど……仕事中なんでしょう?」
「関係ねえよな?タマ」
「ひとり増えるくらいで狭くなる職場じゃあねえしな」
ふたりともまったく気にしていない様子だったので、お言葉に甘えてお邪魔することにした。
ただの一軒屋にしか見えなかったその自宅の、一階が仕事場、二階が住むところのようで、ふたりは二階で食事をしたあとに一階の仕事場でパソコンの画面を広げて作業を始めた。
僕は二階の彼らが読んでいる漫画に目を通していた。母親が僕がこんなのを読んでいたとしたら絶対怒るだろうと思うくらい下ネタだらけのものだったけれども。
暫くしてからふたりはまた二階に上がってきて、そして「夕食にするけど食べていくか?」と聞いてきた。僕は母親に友達の家で食べることになったと電話を入れて、カヴェリエーレが作る美味しいパスタを食べた。
「イタリアでもふたりはいっしょに暮らしているの?」
「まーさかー。男ふたりで暮らしていたら彼女連れ込むのに不便だろ? 別々だよ」
「というか別々になりました。カヴェリエーレが女を連れ込みすぎるから」
アサリと白ワインのパスタをくるくるとフォークに巻ながら環さんがそう言った。僕は食べる手を止めて、聞き返す。
「カヴェリエーレってモテるの?」
「モテない理由があるのか? こんな美形で、金持ちなアーティストが」
カヴェリエーレが自分でそう言ったから、環さんが隣から「ばーか」と笑い飛ばした。
「なんか……環さんのほうがモテそうな気がした」
「環もモテるよな。割と軟派な印象だけど、根はしっかりしてるってみんな知ってるし」
「そらーまあ、お前よりはな」
あまり噛む癖がついていない環さんはラーメンを啜るくらいの感覚でどんどんとパスタを坦らげて、そしてまた仕事場へと戻っていってしまった。
僕はカヴェリエーレをじっと見つめたまま、もそもそと口を動かし続ける。
「なんだよ?」
「いや。イタリアの美形ってこんな顔なんだと思って」
「お前さー、割とワイルドでなく端正な顔が好きなほうだろ」
「……なんのこと?」
「なんつーの? 男の好み? いやゲイとかそういうこと言ってるわけでなくな、あるだろーこう…同性でも好みの顔っていうのが」
きもちわるい。そんなことを考えたこともない。
たしかに好印象な顔の人もいる。環さんとか、男の自分から見ても格好いいと思う。だけど好みの顔って、男に好みも何もあるわけないじゃあないか。
カヴェリエーレが、こちらを見て、言った。
「俺そんなに変?」
「なんか言うこときもちわるい」
「うわー傷つくなあ。大丈夫だって、何もとって食うわけじゃあないし、悪さするわけじゃあないんだから」
悪さするわけじゃあないって、たぶん悪いことする人が言う台詞だと思う。
カヴェリエーレは大仰に傷ついた様子を見せて、そう言った。
「颯って何歳?」
「……十四歳」
「じゃあ来年受験生? イタリアって来る気ないか?」
「はあ?」
「イタリアだよ。俺の住んでるところはヴェネツィアなんだけどさ、綺麗なところだぜ? まあ水は汚いけれどもな」
「ふうん。それで……それとどう、僕が関係あるの?」
「いや純粋な好意だってば。下心一切ナシ、ゼロ、φ(ファイ)、皆無」
「色々言葉知ってるんだね」
でも断る、ときっぱり言った。この外国人、どこか絶対におかしい。僕が世間知らずの坊ちゃんだったとしてもこんな男にはついていかない。
「カヴェリエーレって僕のことなんだと思ってるの?」
「え……可愛い男の子」
「本当にそう思っている?」
「じゃあなんだっていうんだよ。実はやっぱり女の子だったり?」
何期待した顔しているんだ、と顔を背けた。空になったパスタ皿を流しにつけながら、「僕は男だ」ともう一度言う。
「だから期待しても、カヴェリエーレとは付き合わない!」
大声でそう怒鳴った瞬間、タイミングよく二階にあがってきた環さんが目を丸くして僕たちを見ていた。
「あの……カヴェリエーレさん、あなたはその、颯くんに言い寄ったんで?」
「言い寄ってなんか……」
「環さん、この人変態なんです!」
「おおよしよし、怖かったな。変態男とふたりきりにして悪かった」
環さんが僕を自分の背後に隠しながらカヴェリエーレを見つめた。カヴェリエーレがつまんなさそうな顔をして、環さんに一言こう言った。
「……で?」
「いや、ちょっと言ってみただけ。本気じゃあないんだろ?」
「もちろん本気じゃねぇけど」
「颯、大丈夫だよ。カヴェリエーレはお前のこと揶揄っただけだから」
環さんが僕の頭を大きな手でなでた。何故この人はやさしく感じて、カヴェリエーレに生理的嫌悪が生まれるのかはわからない。
「いいか、颯。はっきり言うけれども、カヴェリエーレはイタリアでも有名な建築家で、金もある。おまけにベッロ(美形)だ。性格だってとてもフランクで明るいし、話も上手。つまり、女に人気あるんだ。大丈夫、颯は狙われてないから」
「……本当?」
「というか彼女いるしね」
「どんな彼女? 本当にいるの?」
「架空だとでも思ったのか? 大工やってる、ラテン系の格好いいお姉さんが彼女だ」
随分とアクティブなお姉さんが彼女なんだなあ。たしかにツナギの似合いそうなお姉さんとか彼女にいそうな気がするけど。環さんはにっこり笑った。
「あいつの彼女は本当にベッラなんだぞ。小柄な体型だけど、引き締まったボディと黒い髪がとても綺麗な、しかも性格も可愛いときている最高の美女だ」
「そうなんだ……」
「むしろ俺のほうが彼女いない歴三年を更新したところだ」
「そうなんだ!?」
二度目のそうなんだはあきらかに語尾が飛び跳ねた。
カヴェリエーレがぷぷっと笑ながら、環さんを指差した。
「こいつさ、すんごい真面目だから、自分の中の理想の女性像を求めて早三年経過してるんだ」
「そうなんですか?」
「前の彼女と別れた原因も、理想と違うから」
意外すぎる。なんだかどんな女性とでもうまくやっていけそうな雰囲気があるのに。
「環さんの理想の女性像って?」
「えー、うまく表現できないけど、綺麗な人」
「顔?」
「ううん。内面が」
環さんの求める理想の内面をもった女性ってすごくグレードが高そうな気がした。
ふと、壁にかかっていた時計を確認する。
「九時!?」
「あれ? もうそんな時間か?」
「家帰らないと。お母さんに怒られる」
ばたばたと学生鞄をとりに行くと、環さんが車の鍵をちらつかせて、「送っていく」といってくれた。
すぐ近くだからいいと言ったのに、危ないからと車に無理やり乗せられた。
カヴェリエーレが笑顔で見送ってくれる中、僕は異人さんに攫われた気分になりながら車の外を眺めていた。
「おうち帰らせて……」
「帰すってば。心配するなっての、次の角どっち?」
「右いってすぐのところ」
昨日出会った道のところを車が右折する。ここが家だと言うと、車はすんなり止まった。
「颯、もし良かったらだけどさ、アルバイトする気ないか?」
車を出る瞬間、環さんが僕にそう持ちかけた。
「簡単なことでいいんだよ。クリーニング屋に服取りにいったり、夕飯のおつかいしてきてほしいだけ。これから先俺たち缶詰状態だから、食事もろくすっぽとれないんだ。もしよかったらでいいけれど、気が向いたら、俺の家にきてくれよな?」
遊びにくるだけでもいいんだ、俺たち寂しがりやだから。環さんがやんわり笑って、そのまま車をまた出発させた。
小さくなった車を見送ったまま、僕は少し考える。
たしかにお小遣いは欲しいけれども、そういうのとは別に、環さんやカヴェリエーレといっしょにいるのも悪くないかもしれないと、ちょっと思ったのだ。
別れ際の環さんの寂しそうな笑顔が頭の中をよぎる。ずっとふたりきりだったのかな…仕事関係の知り合いはたくさんいるだろうけれども、忙しいとなかなか友達と会ったりできないのかもしれない。
家に帰るとお母さんから「相手のお宅にご迷惑ではなかった?」と聞かれた。
僕は咄嗟に、友達のお兄さんが車で送ってくれたと誤魔化した。
実際に嘘はついてないよね。カヴェリエーレは僕にとって友達だと思っていいだろうし、環さんは僕から見たら十分お兄さんなんだから。
一週間後、僕は塾の帰りに、環さんの家を訪ねた。
インターホンを押すと、暫くしてカヴェリエーレが姿を現す。
「あ……こんばんは」
「Buonasera.元気だったか?」
カヴェリエーレがやさしく笑いかけてくれた。僕は片手に持ったコンビニ弁当を彼に見せた。
「おー! まだ夕食食べてなかったんだよ。ありがとうな」
僕の頭を撫でてから、カヴェリエーレが部屋の中に入れてくれた。
「タマー、颯が来たぞ」
カヴェリエーレの言葉に、環さんが顔を出して嬉しそうな顔をした。
「ちょい待っとけ。弁当代とバイト代な」
財布をとりに戻った環さんが、僕からレシートを受け取って、少しだけ多めの金額を僕に握らせてくれた。
「これからもお願いしていいか?」
「中間テストと期末テストの期間はくることができないけれど、それでいいなら……」
「うん」
「あと、泊まり込みでのバイトはできない」
「わかった」
「料理作るのも苦手だし……」
そう言いかけた瞬間、後ろからわしっと頭を掴まれた。
「こーんな可愛いお手伝いさんがくるんだぜ? それだけで仕事張り切る気になるよな、タマ」
「そうだな。お前はたしかにそれだけで張り切りそうだな」
環さんが呆れたように笑って、そして僕は時給五百円で雇われることになった。
毎日毎日、部活が終わるとお弁当やお惣菜を買って、環さんの家に行く日常が始まった。
食べ物が飽きないように、なるべく重ならないものを選びながらスーパーを歩く日々が続く。週に一回は、クリーニング店に服を取りに行き、たまに部屋の掃除もさせられた。
僕がやれる手伝いなんてほんのわずかだけれども、カヴェリエーレは毎回僕に「よくやった」「がんばったな」と賞めてくれた。
次第と僕の最初のカヴェリエーレの印象も薄まっていった。
彼はたしかに格好いいし、やさしいし、話も上手で、いい男だった。
一ヵ月後、カヴェリエーレはイタリアへと帰ることになった。あとは環さんに着工を任せて、次の仕事に移るそうだ。
僕はこのときばかりは、寂しさで心が壊れそうになった。毎日話していた相手がいきなりいなくなることが、こんなに寂しいことだなんて思っていなかったのだ。
カヴェリエーレはやさしく笑って、「いつかヴェネツィアに来い」と言って、そして次の日から、ぱったりといなくなった。
それから二ヵ月後……街に大きな美術館が建った。
環さんが特別にオープン前に見せてくれたけれども、僕はこんなに綺麗な建物を見たことがない。
カヴェリエーレは偉大な建築家だったんだ! 僕はそのとき初めて、彼の芸術に感動した。
この感動を彼に伝えられないのが残念だった。すると環さんが、僕にこう言った。
「三ヶ月もお手伝いしてもらったんだし、今度の冬休みにでも、俺といっしょにイタリア旅行してみるか? もちろん俺が全額持つし、カヴェリエーレにも会いたいだろ?」
僕は大きく頷いた。大嫌いな期末テストさえ乗り切れば、あとは冬休みだ。
イタリアのクリスマスにはパネトーネっていうケーキを三人で食べようと約束した。
十二月の上旬、テスト休みの最中に、環さんが僕をドライブに連れ出した。
本当はテストがあるから遠慮したいところだったんだけれども、クリスマスプレゼントをひとつ買ってあげると言われて、物で釣られた。
繁華街の露店で格好いいシルバーアクセサリーを買ってくれて、ファミリーレストランで食事をした。
「そういやさー、颯って好きな人いるのか?」
ドリアを食べながら、環さんがそう聞いてきたので、僕は首を左右に振った。
「なんか……女子ってうるさいから」
「女子って言い方がいかにも中学生だよな」
「うるさいなあ」
やや赤面しながら、デザートのチーズケーキを食べた。
「やっぱこう、好きなのは女の子?」
「どういうこと?」
「お前ほど可愛い少年だったら、年上の先輩たちのぎらぎらした視線とか受けてるんじゃないかなーって。部活なんだっけ?」
「写真部」
「被写体にされたことは?」
「ないよ。うちの先輩たち写真も撮らずに雑談しかしてなかったもの。それも九月で引退したし。それに…」
言いかけて、口を閉じた。環さんが「それに?」と聞き返してきた。
「環さんやカヴェリエーレほどすごい人知ったあとだったら、他の男なんて普通に感じるし」
「女みたいなこと言いやがった」
環さんが呆れたといわんばかりの顔をして、僕を見つめて笑った。
「案外さ、お前が女だったりしたら俺たちうまくいったのかもなー?」
「たしかにね。僕が女だったら環さんのお嫁さんになりたいくらい言ったかもねー?」
冗談半分に軽口を叩きながら、僕はケーキの最後のひとかけらを食べた。
環さんの理想の女性、早く見つかるといいなあ……そんなことを考えながら。
冬休みになった。僕は買ったばかりのナイロンのバッグに、着替えを詰め込んでから成田空港へと向かった。
リムジンバスから降りると、既に環さんが待っていてこっちに手を振ってくれた。
搭乗手続きをすませて、飛行機に乗ると、 僕は時差のことも考えてすぐに仮眠をとった。それは環さんが、そうしておいたほうがいいと教えてくれたからだ。
ローマから新幹線のような特急に乗って、四時間ほど経てば、そこはもうヴェネツィアだった。
ヴェネツィアはとても綺麗な街だった。カヴェリエーレが言うとおり、水はたしかに少し濁っている。だけど異国情緒あふれる、古代の街並みなのだ。
「どうだ? イタリアは最高だろ」
水上バスから体を乗り出した僕に、環さんがそう言った。
「とても楽しい!」
「そりゃーよかった。カヴェリエーレもお前が来たと知ったら喜ぶだろうよ」
「まだ言ってなかったの?」
「いきなり行って驚かしてやろうと思ってさ」
悪戯好きそうな顔で環さんが笑った。水上バスは孤島について、そこからは環さんのクルーザーでさらに遠くの離れ小島まで行った。
こんな遠くにカヴェリエーレは住んでいるのか……なんだか岩山ばかりで、ちょっと怖いところだなあと思いながらその丘にある、一軒屋を目指した。
白い小さな建物の中に入ると、そこは埃をかぶったベッドと、キッチンとサニタリィがあるだけの狭い家だった。本も、パソコンも、何もない。
「……カヴェリエーレ、最近帰ってきてないのかな」
僕は心配になって呟いた。環さんはあまり気にしていないようで、今日は休むようにと僕に言った。
翌日、やはりカヴェリエーレは留守だった。環さんは僕を家の中に置いたまま、数日の食料を買ってくると言って外に出て行った。
クルーザーがないと、僕は外に出ることができないし、暇だなあと思いながらその日は一日中、部屋でごろごろとしていた。
帰ってきた環さんが、キッチンで僕の大好きなオムライスを作ってくれた。環さんは器用なのでオムライスにケチャップで顔が描いてあった。
「ねえ環さん、このケチャップの顔……怖いよ?」
「えー。ニコニコマークなのに」
歪んだ笑顔をしているオムライスをスプーンで崩しながら、僕は口に運んだ。半分くらい食べた頃だろうか……先に食べ終わった環さんが、こっちを見ているのに気付いた。
「なあ、颯」
「なに?」
「カヴェリエーレがここに住んでいるっていうの、嘘だって言ったらびっくりするか?」
僕はスプーンを動かす手を止めた。なんだって? 思わず眉根が寄る。
「どういうこと?」
「そういうことだよ。ここにはカヴェリエーレは住んでいない」
「じゃあ誰の家なの?」
「俺の、秘密の別荘」
環さんは、とてもやさしそうに頬笑んでいる。だけどその笑顔が、とても不自然に感じた。
「ずっとさ、颯は可愛いなって思っていたんだ。だけど俺、男とか駄目なほうだし、お前も女駄目なほうなんだろ? それでちょっと考えてみたんだけど……颯が女になったら俺たちうまくいくんじゃあないかって」
何のことを言っているんだ? 環さんはしらふで何を言い始めるつもりなんだ。
「イタリアの手術の腕って割と安定してるんだよな。だから痛いこととか特にないし、颯だったら絶対ベリッシマになる」
「つまりそれって……」
僕は自分の置かれている状況を確認したくなかったが、恐怖と戦った結果、その一歩を踏み出した。
「僕を性転換させるために、ここに攫ってきたの?」
笑顔で頷く環さんが、もうやさしいお兄さんにはとうてい思えなかった。
部屋に戻るとそこには女物の服が一枚置かれており、腹が立った僕はそれを無茶苦茶に引き裂いた。
何故僕が女にならなくちゃいけないんだ、僕のどこが女みたいだって言うんだ、世の中にはもっと綺麗な女の人なんてたくさんいるじゃあないか!
「家に帰りたい……」
はたして僕は無事に家に帰ることはできるのだろうか。ふと後ろを見ると、環さんが部屋の入り口にいた。その手に握られた、注射器に気付いた。
「何それ……って、うわ! やめてよ」
いきなり何の液態なのかすら分からないものを腕に注入されて僕は身を強張らせた。傷口を脱脂綿で擦りながら環さんは「変なものじゃあないよ。ただの女性ホルモン剤だから」と言った。変なものだよ!
「……本気で僕を女の子にするつもりなわけ?」
「ああ。本気」
「環さんくらいの美形だったら僕じゃあなくたって女の人なんてたくさんいるでしょう」
「まあ美人な女の人はいっぱいいるよ。たしかに」
環さんは寂しそうな顔をして、「だけど理想の内面を持った女性は見つからないんだ」と言った。
「だからって、僕みたいな男捕まえていきなり女に改造するっておかしいんじゃない?」
「でもな……颯、お前は、俺の、理想なんだ」
今度は、すごく穏やかな表情だった。恋人を慈しむような瞳で、僕を見下ろしている。
「俺のことを慕ってくれてるし、性格だって可愛いし、素直だし、とても純粋」
慕う……今の僕は、まだ環さんを慕っているのだろうか。
日本に早く帰りたい。環さんは僕の弱点を完璧に見抜いている。それは、僕が生粋の日本人であること。イタリアという地でまだほとんどイタリア語が話せないということだ。
この家には新聞紙どころか、本もパソコンも何もない。僕がイタリア語を覚えることを邪魔しているんだ。万が一ここから僕が脱出したとしても誰にも助けが求められないように。
「颯……まだ俺から逃げようとか思ってるの?」
「普通この状況で諦められると思う?ただ強制労働させられるとかじゃあなくて男の尊厳が失われようとしている事態で」
睨みつけてやると、環さんは少しだけ悲しそうな顔をした。環さんは本当に表情がよく変わる人だった。どの表情も僕はとても好きだったけれども、今はこの人を見ているのが、怖い。
「すごい、悪いことをしている気分になる」
実際に悪いことをしようとしている環さんが、僕を抱き寄せて耳元で囁いた。
「幸せにするから、愛しているから」
耳元で愛を囁く人に、僕は動くことができなかった。突き飛ばせばきっと手を離してくれるという確信があったけれども、怖い以上の感情が、支配する。苦しいまでに思いつめた、愛情。
ようやくの思いで突き飛ばし、近くにあった引き裂いた服を掴んで投げつけてやったら、それを手に取って環さんはショックを受けたような顔をした。
「お前……ヒス起こした女だってこんなことしないぜ? 恋人からのプレゼントなのに」
「環さんは別に僕の恋人じゃあない!」
「じゃあ誰か、お前のこと思ってくれてる女が日本にいるのか?」
いない、けど……だからってこの性別に未練がなくなるわけじゃあないでしょう? 僕生まれてきたときから男なんだし、それに疑問を持ったことなんて一度もないんだから。
「堂々巡りだな、この議論」
「……諦められるわけがない」
「俺も諦められない」
なんて身勝手な男なんだろう! この男に何かされるのだけは舌を噛んだって逃れたかった。
孤島での生活は、とても単調なものだった。
環さんはクルーザーの鍵を自分で持っているために、僕はこの島から出ることができない。
彼は朝の八時には仕事場に行き、そして定時になると夕食を作りに戻ってくる。
部屋には日に日に女物の服が増えていき、だけど無理にそれを着ろと指示されたことはない。ただ強制的な行為は、女性ホルモンを注射するということだけ。
僕の体は日に日に丸みを帯びていった。元々筋肉質な体をしていないほうだったし、顔も女顔。攫われてきてからどれくらい経ったのかはわからないけれども、一ヵ月後には 僕はもう、外見上は女とそんなに変わらなかった。
ひとつしかないベッドで抱きしめられて寝るのにはいまだ慣れない。
まだ……手は出されていない。
僕の体が変化するのを待っているらしいけれど、変化しなくても十五歳の誕生日には性転換させてやると言われ、僕は春の比較的早いうちにある自分の誕生日を呪った。どうせなら十二月とかなら良かったのに! と。
朝になると抜け出した環さんに隠れてそっと胸を触る日が続く。
まだ膨らんではいない……ずっと膨らまなければいいのに。そんな小学生の女の子が考えるようなことを考える。
環さんは、僕を閉じ込めているということ以外は今までとまったく変わらなかった。料理を作るのは上手だし、やさしいし、退屈なときには色々な話を聞かせてくれた。
だけど僕の気持ちは、もう環さんを大好きだという気持ちにはとうていなれなかった。
環さんは僕のことを抱きしめて、いつでも「愛しているから、大切にするから」と言う。だけど僕の幸せは、こんなところにいることじゃあないし、大切にされてるのも、愛されているのも分かっていたけれども、だけどそれだけじゃあ、満足しないのだ。
僕は僕のままでいたい。女の姿になって、スカートはいて、環さんの隣を歩きたいわけではない。
そういう意味で僕が女に生まれてたら環さんのお嫁さんになりたかったと言ったわけではなかったのだ。そんな常識すら通用しないような、壊れた人だとは思っていなかった。
カヴェリエーレは最初見たときには、とてもおかしな外国人に見えた。だけど彼は付き合って行くうちに、とても素敵な兄貴だということは十分わかった。環さんもそうだと思っていた。だけど環さんは、今、僕にとっては恐怖の対象でしかない。
単調な毎日がすぎていく中、僕は自分の誕生日がいつなのかわかっていなかった。
だけどその日は、唐突に訪れて、僕はある日もぐりの病院に連れて行かれると、全身麻酔で眠らされて手術を受けさせられた。
痛くないと言われていた手術だったけれども、終わった瞬間は下半身がずきずきと痛むし、そして僕はもう男でもなければ、女でもない、中途半端な生き物なんだと思うと悲しくなってきた。
誰も手助けしてくれる人はいない。誰も僕のことを知っている人もいない。
看護婦が僕の検診をするときに色々とイタリア語で語りかけてきたけれども、僕が言葉が通じないことを知ると、興味を失ったように仕事だけして個室から出て行ってしまった。
僕は孤独だった。僕の味方は今、誰もいない。
涙はでなかった。だけど何か、喪失感があった。性別を失ったとか、そんなものではない、人間の本質を信じるという心を失ったのだ。
退院後、僕はいつ自分が無理やり犯されるのか気が気でなかった。だからベッドに入るたびに、今日も無事でありますようにと願った。
だけど環さんは絶対にそういうことをしてきたり、強制するような人ではないのは、この一年くらいでわかっていたことだった。彼は僕の髪を梳いたり、いじったりしながら頬に口づけて、そして毎晩「愛している」と囁く。
本当にいとおしむように、慈しむように、僕のことを大切にしてくれている。
彼が僕に対してやった最低の冒涜行為は、たしかに許せないものだけれども、だけど環さんは、このイタリアの地で、誰よりも僕のことを大切にしてくれていた。
もうどうせ男には戻れないんだし、せめて環さんの気に入るような女にでもなろうかというそんなことも考えてはみたものの、はっきり言うならば無理だ。
なぜなら僕の心は、まだ男なのだから。
そんなある日、サニタリィルームにかけてある、大きな鏡を見た。
全身鏡に映っている僕は、とても綺麗な女の人にしか見えなかった。均整のとれた体と、やや童顔の顔。別にナルシストなわけではない。普通にそこに、女の子が立っていた。
僕はもう、体は女なんだな……そう感じた。
風呂から上がって、何を血迷ったのか、トランクスではなくショーツをはいてみた。さすがにブラはつけられなかったけれども、部屋にたくさんあった女物の服の中で、自分が女の子に着せたらとても可愛いだろうと思うようなものを選別し、ためしに着てみた。
そしてサニタリィルームの鏡の前に行く。
白いシフォンの膝丈スカートに、生成りのカットソー。鏡に映っている女の子は、とても可愛いのに、だけどその子にその服が似合っているとは思えなかった。だって顔がとても引き攣っているんだもの。
「……全然似合わない」
一言呟く。全身から力が抜けたように床にぺたんと座って、そして僕は力の限り叫んだ。
「中途半端なものにしやがって!」
どうせならば心まで女に性転換させてくれればいいのに。僕は男でもなく、女でもなく、環さんを嫌いにはなれず、だけど愛することもできない醜い生き物になりさがっていた。
その日、スカートをはいている僕を見て、帰ってきた環さんがびっくりした顔をしていた。
「……どんな心境の変化?」
「気分転換」
「無理すんなよ? お前スカートはくタイプの女じゃなさそうだし」
もう環さんの中では、僕は女なのだろう。たしかに体のつくりは女になってしまったけれども、だけど僕は男でも、女でもなく、鶴谷颯でしかないということしか、認識できなかった。
環さんは、就寝時に僕のことを抱きしめてからこう言った。
「なあ颯。お前がもしその気ならばさ、結婚しないか? ちゃんと世話するし、一生大切にするし、辛い思いなんて絶対にさせないから」
僕はその瞬間、堰を切ったように大声でわんわんと泣き始め、そして環さんの胸を叩いて罵倒した。
あんたは自分勝手だ! 環さんは自分のことしか考えていない。僕は普通に日本で高校に進んで彼女作って、大学に進んで就職して結婚する人生だってあったはずなんだ。全部奪ったのは環さんだ。僕の人生を奪ったのは環さんだ!
あらん限りの言葉を使って罵倒したのに、環さんは僕を抱きしめているだけだった。
本当に申し訳ないような表情をして、僕の頬をなでた。
「何か望んでいることはあるか?」と聞かれた。男に戻りたいと言いたかったけれども、まったく意味のないことなのはわかっていたから、だから日本に戻りたいと言ってみた。
だけど日本に帰してくれるどころか、この島からも出してくれそうもなかった。
この人の愛は、僕を愛している自分というところで止まっている。僕がどうしたいか、僕がどう感じているか、そんなことはどうでもいいのだ。
僕は日に日に、抵抗することの無意味さを知るようになった。
愛されるように無理に振舞う必要はない。だけど僕の思い通りになることなんて、何一つないことだって、長い月日で知っていた。
無意味に抗い、彼の機嫌を損ねる必要なんてまったくないのだ。
僕はときおりヒステリーになる日以外は、極力平常心で生活するように心がけた。
まったく何もない、単調な毎日である。心に荒波さえ立てなければ、何も自分に危害を加えるものはなかったことに気付く。
このまま僕が自分の今の立場を受け入れたら、もしかしたらこの孤島の外に出られるのではないだろうか。そうしたらカヴェリエーレに会えるかもしれない。彼は今の僕を見たらなんと言うだろう……訴えてやると言うかもしれないけれども、環さんを訴えることによって僕が得られるメリットは何もない。この孤島で受けた辱めの数々を法廷で口にするのだけは、死んでも嫌だ。
三日間、環さんが仕事場から帰ってこない日があった。
冷蔵庫に食べ物があったし、パスタの麺もあったから、食べるのには困らなかったけれども、なかなか帰ってこない彼が心配だった。
このまま何日も彼が帰ってこなかったら、今度は僕の身も危ないな…そういう意味でも心配だった。
環さんはその晩帰ってきた。疲労困憊した表情で、「今すぐ夕食作るから……」と言ったきり、後ろに向かって卒倒した。
僕は慌てて彼をベッドに運んで、頭の上に濡れタオルを置き、看病した。過労による、何かだと思うのだけれども、医者ではない僕にはそれがなんなのかわからない。
「環さん、電話! 医者に電話しなきゃ」
「駄目だ。俺が医者にかかったら、お前はきっと俺を捨てていく」
「環さん、今そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。しんじゃうかもしれないんだよ?」
泣きそうな表情の僕を見上げて、環さんは言った。
「颯を失うことのほうが怖いんだ」
本当に、自分勝手。自分のことしか考えていない環さん。自分のことすらまともに考えられない、馬鹿な男。
「なあ颯……傍にいてくれよ。ずっと傍に……いてほしかった。それだけなんだ」
本当に、それだけだったんだ。
疲れきった表情でそう呟いた環さんの顔に、僕の涙が落ちた。こんなときにまで、僕は彼の心配をしている。馬鹿な男と、馬鹿な僕。
「ねえ環さん、お願いだよ。僕のこと愛しているなら、僕が逃げないって信じてよ」
「だって……無理だろ? 俺はお前に散々酷いことしちゃったんだ」
「全部許すから。死なないでよ、お願いだから」
「颯」
まっすぐに、環さんの腕がのびて、僕の頬に触れた。頬に流れた涙を拭い去り、そして頬笑む。
「お前は、俺を許しちゃだめだ」
そのときの環さんの表情を、どんな言葉で表現すればいいのかわからなかった。
やさしいような、かなしいような、つらいような、さみしいような、あたたかいような、身勝手なようで、あまい表情。
環さんは「少し疲れた」とそのまま寝てしまった。
翌日、環さんが起きることはなかった。
僕は環さんの顔にハンカチをかけて、そしてお祈りをした。
僕は環さんがいない状態でここで生きていけるわけではない。生き残るためには、助けを探さなくてはいけない。
僕は環さんの鞄を漁って、中から携帯電話を発見した。
イタリアの携帯電話の使い方はわからなかったけれども、何度も試行錯誤で操作しながら、最後にやっとカヴェリエーレという言葉を発見した。
履歴からカヴェリエーレに繋ぐと、向こうから懐かしい声が聞こえた。
――……颯か?
「カヴェリエーレ、助けて。環さんが死んだ。ヴェネツィアのリド島からさらに南のところに監禁されてたんだ」
――すぐに行く。
電話が切れた。今のシステムならば、携帯電話の電波をつてにどこに僕がいるのかわかるはずだ。やっと、この孤島から出ることができる。
カヴェリエーレは、五時間後に駆けつけてくれた。
日本語のわからないイタリア警察のかわりに、僕の話を聞いてくれた彼は、環さんの顔を一発殴った。
「こんなのは、間違ってるだろ。タマ、これは『愛している』と言わないだろ? お前のしたことは、立派な犯罪だぞ。颯の人生メチャクチャにしやがって!」
カヴェリエーレは本気で怒った。僕のかわりに、本気で怒ってくれた。カヴェリエーレは僕のことを愛してくれていた。間違った愛し方ではなく、大人が子供を慈しむ目で、愛してくれていた。
事情聴取が全部済み、環さんの墓も作った頃の話だった。
僕はカヴェリエーレの家に仮住まいをして、少しずつイタリアの風土を学んでいた。
カヴェリエーレの彼女のアーダはとてもいい人で、僕がつらい思いをしただろうと気を使ってくれて、そして色々なことを教えてくれた。
カヴェリエーレは環さんが僕にプレゼントしたものを、みんな処分した。あいつの渡したものなんて絶対に身に着けるなと、僕にきつく言った。
僕は日本に帰ることを諦めていた。今さら帰ったところで、両親が泣いて、家庭がぎくしゃくするのは目に見えている。僕が受けた仕打ちも、たどった人生も、日本に帰ったところで修正不可能な域なのだ。
ここには新しい家族がいた。カヴェリエーレと、アーダ。それに事情を知らない近所の人たちも、とても親切だった。
ヴェネツィアの道を歩いていると、色んな男の人に声をかけられる。たぶん僕のことを女だと思っているのだろうけれども、それにも慣れた。「イタリア語わかりまちゅかー?」と赤ちゃん言葉で話しかけてくる失礼な態度にももう慣れた。
正直、両親に会いたくないのかと聞かれたら、会いたい気持ちはある。
だけど、ここは僕のことを知らない人たちしかいないから、だから、僕は新しい人生をまた歩めるんじゃあないかと思う。
僕の人生をメチャクチャにしてくれた環さんは今、ヴェネツィアの共同墓地に眠っている。
僕は月に一度は、その墓地にお花を添えに行く。
カヴェリエーレは何度も僕に「あそこには行かなくていい」と言った。
「タマのことを忘れられないのはストックホルム症候群だ」と説明もしてくれた。
たしかにそうなのかもしれない。僕にとって、あの孤島で生活した時間は、永遠に忘れられないものだろう。
だけど僕は環さんがやすらかに眠れることを祈っている。
あなたは僕を失いたくなかった、いっしょにいたかった、本当はそれだけだったんだよね。
やりかたは間違っていたけれども、だけど環さん、僕は最後まで、あなたが嫌いになれなかった。
環さんは理想の女性を探していた。内面の美しい、彼にとっての最高のベリッシマを。
次の来世でも、僕より先に生まれてください。そうしたら僕は女に生まれて、あなたの元に駆けつけます。
環さんが寂しくないように、環さんがもう間違った選択をしないように、僕があなたの心を、今度こそ支えてあげたい。
(了)