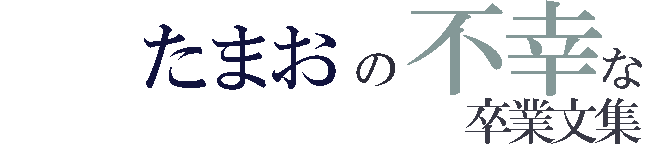
10/16
2学期中間テスト、篠宮さんの成績が20位以下に初めてなった。そして僕の成績も生まれて初めて7位という最低の記録をたたき出した。
「三芳は恋にうつつを抜かしすぎなんじゃあねぇの?」
クラスメイトの英田が僕の成績表を見て聞いてきた。
「僕が恋だって?」
「あの根暗な女に恋してんだろ」
「してないよ。そう思われたら心外すぎる」
「じゃあ何?」
「何って……」
同情。そうか、僕は彼女のことを心配しているつもりだったけれども同情していたのか。可哀想に、僕がめぐんであげなければ君は死んでしまう弱者なんだねと思っていたのだろうか。英田、お前は鋭い突っ込みをした。
「なんかほうっておけないんだ」
「それ気になるってことだろ?」
「まあそうだけど……」
「恋じゃあないのか?」
「絶対にそんな感情じゃあないよ」
もっと陰惨な感情だ。恋って相手も自分を好きになってくれないかなと思って気持ちを伝えたり知ってもらいたかったりするものでしょう? 僕は彼女に「三芳、あんたは不幸な男ね」なんて同情されたいなんて欠片も思わないし、そして僕が君のことを哀れんでいるなんてことも知られたくない。
隠し通さなくちゃいけない感情なんだ。
「胸が苦しくなったりしないか?」
「しょっちゅうするよ」
「それでも恋じゃあないって言い切る理由って?」
「聞きたいの?」
「聞きたい聞きたい。なあどうして?」
「彼女が死んでいる姿をよく想像するから。腹が餓鬼みたいに膨れ上がってあきらかに栄養失調って姿? 目が見開いててさ、何も見ていない空洞のはずなのにすごく絶望した色をしていてその姿が頭の中をちらつくたびに彼女の声でこう聞こえるんだ。『てめぇだよ三芳、おめぇが私を見殺しにしたんだ』って。僕はきっと彼女に呪われてるんだ」
僕の回答を聞いて英田が少し沈黙した。顔色がおかしいよ、英田。君も想像しちゃったのかな、あの根暗なくせに口うるさい女が何もしゃべらなくなっちゃったときのことを少しは想像しちゃった?
「……三芳、お前に何があったんだ?」
その日、僕は夏休みから今に至るまでの経緯を帰り道に英田に話した。英田はあのアホ面に渋面を浮かべてこう言った。
「俺たちって無力だな」
本当に、無力。
篠宮さん、僕たちは本当に無力な存在だ。