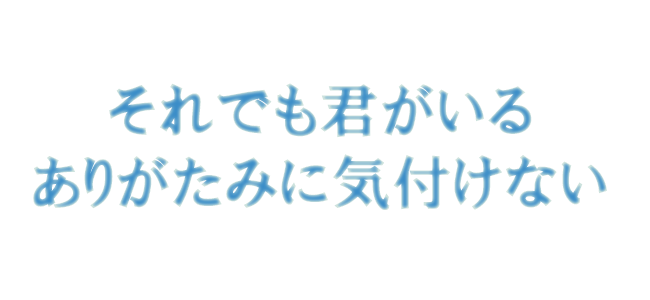
ボスのドン・白明に蝶恋を引き渡した直後の晩に会うのだけは避けたかった。
それなのにそんな日に限り、蝶恋は真夜中に黒狸の家の扉を叩いた。
「なんだよ?」
眠りかけていたタイミングで起こされて、黒狸も不機嫌だった。蝶恋は用事を言うよりも先に黒狸のだらしない格好を見て
「あんた、パジャマくらい買ったら?」
と言った。下はスウェットで上は昼間から着ていたシャツだ。汗でべたべたなシャツのにおいに蝶恋が顔をしかめる。
「鍵盗まれたみたいなのよ。部屋に入れないから今日泊めて欲しいんだけど」
「かまわないけれど鍵はまた嫌がらせで盗まれたのか?」
「知らない。お財布が無事だったってことはそうじゃあないの?」
蝶恋はおじゃましますも言わずに部屋に入ると、足の疲れそうなピンヒールを脱いだ。どこかのパーティー会場から帰ってきたばかりのようで、背中はばっくり開いた黒いドレスだし、長い髪の毛は華やかにアップでまとめられていた。
「髪の毛すっごく気持ち悪いんだけど、解くの手伝ってくれない?」
「ボンドで固めたみたいなアップだな」
「髪の量多いからそうするしかないのよ。あんた美容師志望だったんでしょ?」
高校生時代の話を持ちだされて複雑な気持ちになりながら、蝶恋の背中にまわり、髪の毛のピンを一本ずつ抜いていく。蝶恋はその間にコンビニで買ってきたらしい化粧落としでメイクをオフにしている。
彼女がすっぴんになった頃に髪の毛も解けた。まだスプレーで固めた跡がいっぱい残っている髪の毛を強引にブラシで梳こうとする蝶恋にシャワーを浴びるように言って、クリーニングに出したあとのシャツを一枚渡す。
「変な気起こさないでよ?」
「夜中に男の家来て『泊めて』って言ったら普通そういう展開になるぞ。いいから風呂入ってこい、俺は今不機嫌だからそういう気分じゃないし」
リビングの向こうで衣擦れ音が聞こえ、シャワーを浴び始める音も聞こえ始めた。黒狸は蝶恋が上がってきたときのために、レモンを搾り器で絞る。酒はパーティー会場で飲んできただろうからさっぱりしたもののほうがいいだろう。ミネラルウォーターとガムシロップでレモネードを作った。
蝶恋はタオルで髪の毛を拭きながら出てくると、黒狸が作ったレモネードを勝手に自分のものだと思ったらしく、一気に飲み干す。
「二日酔いに効くものある?」
「漢方薬でよけりゃ」
「あとお腹空いたから何か作ってよ」
「俺のお姫様でもないのに色々注文するんじゃねえよ」
「黙れ。お姫様にたかる害虫なんだから同じ地を這う虫けらがお似合いなのよ」
蝶恋の自分も相手も貶める言い方にどういう反応を返すべきか悩みながら、結局反応は返さずに冷蔵庫の中を確認する。蝶恋が隣から覗きこみ、中にあったハーブドライトマトを勝手に手にとった。
「あともう一品つまみね」
「はいはい」
晩酌だと思えばいい。アボカドとひじきをリコッタチーズで和えて、コンビーフとズッキーニのピカタを作ろう。しいたけのステーキも作ろうか。そんなことを考えながら冷蔵庫と乾物入れから必要な材料を取り出す。
蝶恋は勝手にカウンターに並んでいたウイスキーを手にとって色気のないマグカップに注ぐとストレートで飲み始める。あれだけ酒を飲んでいて太らないのだから、若いというのは素晴らしいなと思ってしまう。
さっと作ったつまみを持って行き、自分もグラスにウイスキーを注いで蝶恋のお向かいに座った。
黒狸は蝶恋が黙々とつまみを食べて、酒を飲むのを観察しながら、ウイスキーを飲んだ。蝶恋は美味しいとも、ありがとうとも言わずにどんどん平らげていく。黒狸はその様子をじっと見ている。
「何? 食べたいならそんな目で見てないで食べれば?」
黒狸の視線に気づいた蝶恋がそう言う。食べたいから見ていたと思われたようだ。
「俺のありがたみがわからない蝶恋さんと、蝶恋のありがたみがわかってない俺だよなあと思っただけ」
「あんた料理を作っただけで偉そうね」
「夜中にゲリラ訪問してきたお嬢さんに服を貸して風呂を貸して料理を作って二日酔いの面倒を見て、これからベッドを貸してやるんだぞ? しかも男女だというのにセックス抜きでだ」
「うん。あんたとしちゃ偉いわ」
「普段プチ迷惑かけてくるのはお前のほうだよな」
「そうね」
蝶恋はもぐもぐしていた口をやめ、ごくんと飲み込むと続きを話した。
「でも、女に嫌われるたびに迷惑かけるのはあんただわ。ライラのときも、ミシェルのときも、ネフリータのときも、あとこの前の女の名前は初めて聞いた」
「そんなもんだろ? 俺が迷惑かけるのって」
「あんたはメンタル的にぺしゃるときだけ私に迷惑かけるのよ。そんなネガティブなときだけ連絡とられて私があんたの印象よくなると思わないで欲しいわね」
口ではそう言いながら、蝶恋は黒狸のふるまった食事を家族の作ってくれたもののように食べていく。
「我侭な妹みたいなもんなのかな」
「じゃああんたは世話の焼ける兄だ」
「そこまでお前のことぞんざいに扱ってたっけ? 俺」
黒狸が思い出そうとしても思い出せない恨みつらみがあるのだろうか。蝶恋はひじきのサラダに箸を伸ばしながら言った。
「あんたが14歳、私が10歳のときに言われた言葉覚えてる?『うわ、汚いガキだな』だよ」
「……。悪かった。あの頃はいじめっこだったんだ、俺」
「かと思ったらあんたが18歳、私が14歳のときには『蝶恋ちゃん美人になったね。いつセックスしよう?』だよ」
「いや、高校生の時はなんかそういう病気にかかるんだ」
「あんたが20歳、私が16歳のときには私が家出してあんたのことを頼ったわ。『悪い。彼女が嫉妬深いから他探して』はあ?」
「うん。心細い16歳にひどい仕打ちだった」
「かと思ったらその直後にネフリータみたいな小さい子連れ込んでるじゃない。私が注意したら『小さい子に嫉妬するなんて見苦しいぞ』勘違いするな」
「そのとおりですね。すみません」
「あんたが22歳、私が18歳のときはアル中のライラとあんたは付き合ってたわ。彼女から酒を取り上げたら『大嫌い』って言われてそれが縁の切れ目。『俺は酒以下か!?』って腹立ててたけど、当時のあんたと酒なら、私も酒のほうが慰めてくれると思うの」
「非常に心苦しい限りです」
「私が20歳になってあんたが24歳のときはごく普通の家庭で育ったミシェルと付き合っていた。でもわかってると思うけれども彼女は……」
「うん、なんであんなメンヘラにコンバートされたんだか……」
「突然変異だったわ。狐が憑いたとしか思えない。つまるところあんたは『俺、蝶恋のこと好きになったからお前とは別れる』と言った。あんた私が嫌がらせ受けたこと知ってる?」
「知らなかった。すまん」
「28歳になってついに同居していたネフリータにまで『好きな男ができたからここにはもう来ない』って言われてあんたが言った言葉が『あのクソアマ』だよ。お前自分の年齢考えろ? うら若き18歳の美少女が28歳のおっさんを相手するとしたらお金持ってるからだよ」
「おっしゃるとおりです、おっしゃるとおりです」
「そして31歳。お前の最低男恋愛碌が更新された……」
「はい」
もう最後の返事はシンプルなものだった。本当に蝶恋には迷惑をかけたという再認識と、自分が他の女性からどう見えていたかという再認識。黒狸はため息をつく。好きでこんな性格なわけじゃあないが、どうしてかまっとうに生きられない。
「どう? 私、これだけあんたに迷惑かけられてもあんたを見捨ててないって超慈悲深い女神だと思うの」
「おっしゃるとおりでございます。蝶恋様」
「うん。わかったら疲れたから肩もんでもらいたいわ」
「おみ足もお揉みいたします」
「あんたの誇りのなさとプライドの高さってすごく扱いづらいわ」
蝶恋の後ろに回って肩をさわると、たしかに張っていた。揉む力を強くすると蝶恋がちいさく悲鳴を上げたので、少し軽めにつかむ。
「おっぱいでかいと肩凝るって本当?」
「本当」
「しかも最後すごく垂れるって本当?」
「お母さんいないんだっけ? うん、最後はもうアメリカンクラッカーだよ」
「その頃はもう揉んでくれる相手もいないからいいんじゃね?」
「おっぱい垂れないかしら。おっぱいだけで決める馬鹿男が減って助かるんだけど」
「俺がおっぱい欲しいくらいだ」
「変態発言また現れた」
蝶恋の肩や腕の凝りをほぐしてやったあと、彼女の反応がないので小声で名前を呼んでみる。反応はない。
寝てしまったんだなと思い、抱き上げてベッドに運んだ。
シャツの上からもわかる胸のふくらみと、身長の高い女性ならば当然、足りない丈。腕を持ち上げたら下着が見えるだろうなと思いながら、ブランケットをかけようとした。
蝶恋の口がむにゃむにゃと動き、黒狸の名前を呼んだ気がした。
「呼んだか?」
彼女が何か言ってるが、聞き取れなかったので唇間近に耳を近づけてみる。
「死ね」
ひどい寝言だった。思わず眉がひそまったのが自分でもわかる。蝶恋の額におやすみのキスをして、ブランケットをかけた。
翌日、床で寝ていた黒狸を蹴った蝶恋を睨み上げるのが目覚めだった。
鼻は卵焼きのバターのにおいを嗅ぎ分けて、起き上がってみると久しぶりにごはんを作らず、外食でもない人の作った朝食が出てきた。
黒狸が仕事にでかける準備をするためにスーツに着替えている間、蝶恋は食器を洗っていた。蝶恋がシャツを脱いで昨日のドレスに着替えたり化粧をしている間、黒狸は漢方薬と栄養ドリンクとサプリを二人分用意していた。
漢方薬を飲み、栄養ドリンクでサプリを流し込み、二人鏡合わせのように向かい合う。
「ネクタイまがってる」
「チーク濃ゆすぎ」
お互いにひどいところを指摘しあって、黒狸はネクタイを直し、蝶恋はチークをはたいた。
「じゃ、行ってきます」
「泊めてくれてありがとうね」
ようやくお礼を言ってくれた蝶恋に「どういたしまして」を言って、鍵を閉めて二人で家を出た。紅龍会とまったく逆の方向に蝶恋は歩き出す。黒狸はそのまま仕事に向かう。
結局、蝶恋はお礼を言ってくれたけれども、黒狸は謝るだけでお礼は言えなかった。
いつもありがとう、これからもいっしょにいられれば、と。
(了)