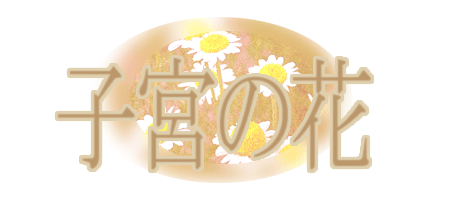
カモミールの花
翌日の朝、冷えたポトフを食べる気にはならなかった。床には何が起こったかもよく理解していなかっただろう老婆の死体。
それを見てギーの中にあるものは、もうこれは死んでいるという認識だった。それ以上感情移入しすぎても辛くなるのがわかっている。
フェリクスに連れられて外に出ると、車を磨いていたリヤードが「おはよう」と言った。リヤードは少し不機嫌そうだった。
「どうしたの、寝不足?」
フェリクスに質問されて、リヤードが口をへの字に曲げる。
「俺はばあさんを殺す必要性なんて感じなかった。それだけだ」
「まーだそんなこと言ってるんだ。やな奴」
「お前がやな奴だ」
フェリクスがこっちを向いて
「先生は俺の味方でしょ?」
と聞いてくる。昨日脅しておいて自分の味方になれという矛盾っぷり。
「済んだことは取り返しがつかないですからね」
「そーそー」
無難な答えを選んだギーにフェリクスが笑顔で頷く。リヤードは納得していない様子だった。
車に乗り込む。律儀にシートベルトをつけてからリヤードは車を発進させた。
「今日は南東に向かうぞ」
もうこの頃になると車がどっちに走るかはリヤードが決めていた。
検問に引っかからぬように大きな道を避けながらどんどんと南東へと進んでいく。
「腹が減ったな」
昼に差し掛かる頃、リヤードがそう呟いた。
「俺はお腹空いてないよ?」
「お前は殺したばあさんのポトフをぺろりと食べただろうけどな、俺はそんな神経図太くないんだよ」
「変なの」
「お前が変なのだ」
リヤードは近くに店を見つけて「あそこで何か買ってくる」と言った。
「お金使うと足がつくんじゃない?」
「脱税した金だぞ? 番号が残っているわけがない」
リヤードは金を掴むと買い物に出かけ、食料を暢達してきた。
「ギーも腹減ったろ?」
彼はクーペの中にハムとチーズが挟まれただけのサンドイッチを寄越した。口に含んで初めて、自分もお腹が空いていたことを思い出した。あっさりと胃の中に収まったあとは少しだけ空虚感が紛れる。
しばらく車の中は無言だった。フェリクスが暇を持て余してか、ギーに「何か話そうよ」と言った。
「僕が逆らったり口答えしたりすると、人が死ぬんでしたら、黙ります」
ギーがそう答える。フェリクスは「ふーん」と呟き、こう言ってきた。
「先生の脚をぶち抜かないのは歩くのに不自由だと逃げるのに苦労するからだよ。先生の指を折らないのは泣かれたり叫ばれたりすると面倒だからだ。先生を殺さないのはまだ利用価値があるから。じゃあ先生の舌を抜かないのは何故だと思う? 話を聞いてほしいからだよ、先生」
つまりその理由が何もなければ、遠慮なく殺すということだ。先日の老婆のように。
フェリクスはこう言っている。話し相手になってくれないならば危害を加えると。
「何が話したいんですか? 今まで面接中に話したことと同じ内容ですか?」
「ああ、こんなに殺したんだよってこと? あの殺した人数が毎回違ったことに先生気づいていた?」
「てきとうに言っているんだろうなとは思っていました」
「殺した人、ひとりひとりのことなんてどうでもいいもの」
フェリクスは笑う。
「だって、誰でも自分の人生が一番大切でしょ? 人のことを本当に考えられる人なんているはずないんだ」
「そうかもしれませんね」
「きっと先生も俺のこと気持ちの悪い殺人鬼だと思っているんだよね?」
「そんなことは思っていませんよ。そう感じましたか?」
「ううん、なんとなく言っただけ」
この会話を刑務所の中で聞いたとしたら、カウンセリングがうまく効果を現しはじめたと思っていただろう。今は彼の話の内容に興味を持つよりも、時間稼ぎ的な思考のほうが先にくる。
「ねえ、先生。世の中は平等だと思う?」
「フェリクスは不平等と感じているんですか?」
「だって酷いよね。俺のことをあんな豚箱に押し込むんだもの」
「それはあなたが犯罪を犯したからじゃあないでしょうか」
ギーの言葉にフェリクスは目を細めた。
「それでも、不平等だよ。俺は別に豚箱に入りたかったわけでも、人を殺したかったわけでもないもの」
無差別殺人鬼だというのに、人を殺したくはなかったと言いはじめるフェリクス。彼はさらに話を続けた。
「俺の家ね、親父がすぐ殴ったりする悪い奴だったの。母さんはサン・ドニ門の近くで娼婦をやって家計を支えていた。商売道具の顔に傷がつかないようにいつも顔をかばっていた。だから顔以外のところに傷がいっぱいついていた」
フェリクスの顔はなんともやるせない、どうしようもなく悲しい、だけどなんともならないといった表情だった。
「母さんを守るために、俺は親父が寝ている隙に枕を押し当てて窒息死させた。俺は英雄だと思った。母さんを救ったんだ、これで母さんは普通の生活に戻れるって。だけど母さんは俺のかわりに罪をかぶって刑務所に投獄された」
ギーはリヤードがバックミラー越しにこちらを見ているのに気づいた。話は続く。
「孤児になった俺をいじめる奴はいっぱいいた。だけど俺は母さんががんばっているのに、俺ががんばらなくてどうする? って必死に耐えたんだ。がんばればきっと未来が開けるとその頃はまだ思っていた。母さんが服役を終えればまたいっしょに暮らせると思っていた。……母さんが病死したって手紙が孤児院に届いた。俺は孤児院を抜け出して、墓地を見に行った。カモミールの花が咲いていた」
彼がカモミールの花に執着するのはそこが原因らしい。絶望に見開いた青い目がこちらを見つめている。
「孤児院に戻った俺は独房のようなお仕置き部屋に入れられた。ここでがんばる理由がなくなった俺は家出をしたんだ。きっと新しいところに行けば変われると思った。だけど住所のない奴を働かせてくれる場所がどこにある? せいぜいあって、タダ働きさせたい奴らばかりだ。飢えて寒くて、もう死んじゃうっていうときに住所を貸してくれるって奴が現れた。俺は初めて友達ができたと思った。すごく感謝したんだ。ところが稼いだ金を全部盗まれた。最初は何も言わなかったけど、何度も盗まれたから問い詰めるしかなかった。あいつは開き直って笑い、『どうせお前は行く場所なんてないんだ』と言った。だから殺した」
当時のことを思い出したらしく、フェリクスの唇がぶるぶると震えている。怒りで震えているのか、悲しみで震えているのかはわからなかった。
「俺はどうせ待っていても捕まることがわかっていた。だけど酷いだろ? 俺は何度もやり直そうとしたんだ。そのたびに周りが俺を傷つけたんだ。世の中には不条理なことがいっぱいあるって、あいつらに知らせてやりたかったんだ」
「だからアパートの非常階段から銃を乱射したんですか?」
ギーの質問にフェリクスは低く「そうだよ」と答えた。
「罪もない市民がたくさん殺されたって報道されてたね。あいつらは俺を傷つけたのに、その罪は問われない。俺は何度もやり直そうとして無駄だったのに、今さら刑務所で更生しろって言われている。うんざりだ、俺以外の誰になれって言うつもりなんだ? 俺のこの苦しさに蓋をして、別人になれってか」
絶望に染まった目がギーを見つめた。
「俺は死に場所を探しているんだ」
そうしてリヤードに向かって
「カモミールの咲く場所に連れて行け」
と言った。車は静かに南へと走り続ける。