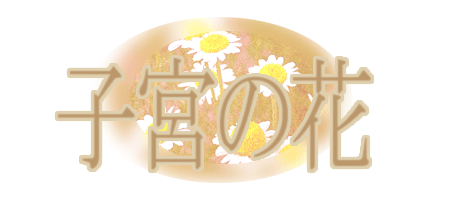
アランの言い分
三日目。レインマンの言った番号の金が使われた場所が割り出された。
そのときカメラに映っていた車を追跡する方向に警察は動き始める。
「とりあえず今は"待ち"の時間でしょうね」
レインマンは隠れ家に使っている宿屋で待っていたシャリーフとアランにそう言った。
アランはしばらく沈黙し、部屋を出て行こうとした。
「どこへ行くつもりですか?」
「ここにはお前がいれば事足りる」
「だからアランはギーくんを探すと? あなたが動き回ったくらいで見つかる範囲にいるとは思えません。ここにいたほうが確実に情報は入ってきますよ」
レインマンは不思議に思い、アランに聞いた。
「どうしてそんなにギーくんのことを心配しているんです?」
アランは鼻で笑う。
「思考が読めるくせにそんなことを聞いてくるのか」
「馬鹿みたいに彼の心配で頭が埋まっているから聞いているんですよ。誕生日を祝ってくれたのがそんなに嬉しかったんですか?」
ギーがアランの誕生日を祝ってくれたことは、ふたりだけしか知らないはずだ。アランは自分の思い出を勝手に漁られたことに腹立たしさのようなものを感じながら言った。
「誕生日は嫌いだ。私があいつに執着するのは、拒絶されないからだ」
「拒絶されない? 彼はただ単に、無難な答えを選んでいるだけであって、あなたのことを認めているわけではありませんよ?」
「だからなんだ。拒絶されない、それだけで十分だ。やり直すために何か力を貸してほしいと頼んだことなんてない。ただ傍にいてほしいと願っただけだ」
レインマンの中にアランの感情が流れ込んでくる。
心を踏みにじられた幼少時代。心を閉ざした少年時代。人を殺した青年時代。
どの時代も彼のそばにやさしい言葉をかけてくれる人はいた。だけどみんな離れていった。みんな彼に愛想を尽かして最後は捨て台詞を吐いて去っていく。まるで親切にしてやったのに、真人間にならなかったアランに「恩知らず」と言っているようだった。
暗闇の中に小さな子供がいた。周りを死んだような感情たちに囲まれて、怯えている少年だ。たぶん小さい頃のアランだろうと思った。
その少年は泣きじゃくりながら、こう言うのだ。
「傍にいてよ。ひとりぼっちだ」
と。誰も彼がいる闇の深さまで下りてこられなかった。
彼は傷つくたびにさらに深淵へと潜った。もう誰の声も届かぬよう、もう誰にも傷つけられないようにと。
そうして誰も助けられない深さまで堕ちてしまった。
レインマンが自分の感情を読んでいることに不愉快さを覚えたアランが顔をしかめる。
「ギーくんが特別なのは、それが理由ですか」
「何がだ?」
「彼しかその深さまで下りてこられる人間がいないんですね」
アランにとって、相手の顔が確認できる距離まで近づいてきたのは、ギーしかいないのだ。暗闇の世界にふたりぼっちとも言える。
アランは静かに口を開く。
「それまで人間と物の差なんて、動くか動かないかだけだった。あいつは生きている。あいつを見てはじめて人間を人間だと思ったんだ。私を傷つけることしか言わない人形たちじゃあなかった」
アランは「もういいだろ?」と言った。レインマンが何も言わなかったので部屋を出ようとする。
「俺も連れていけ」
後ろからシャリーフが声をかけた。
「フェリクスが行きそうな場所を思い出したんだ。案内できるかもしれない」
「連れて行こう」
アランとシャリーフが部屋を出て行った。
レインマンはシャリーフが何を考えているかが読めた。しかし何も言わなかった。どのみちギーが見つからない限り、困るのはアランも自分もなのだ。
アランがシャリーフを連れて行くというならば、それはアランの責任だ。