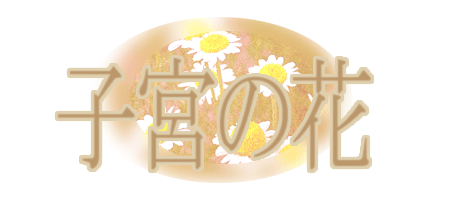
何も感じない
車はゆっくりと南に走る。気候があたたかくなって、花のちらほら咲く道をさらに南へ。
「あなたのお母さんの墓地はどちらにあるんですか?」
ギーがフェリクスに質問した。フェリクスはリヤードが買ってきたチョコレートを口に頬張りながら
「区画整理をするとき移動されたっきりわかんなくなった」
と答えた。ハンドルを握るリヤードが
「あそこなんてどうだ?」
とフェリクスを呼んだ。遠目に見える丘に、カモミールの群生が見えた。
車はゆっくりと丘を登り、止まった。
リヤードが車を降りる。続けてフェリクスも。ギーもいっしょに車を降りた。
春風が頬をやさしく撫でる。カモミールの花の林檎のような、可愛らしい香りが鼻腔をくすぐった。
カモミールのほうへと歩いていくフェリクスを見た。なんとも言えず懐かしそうな表情をしている。
「綺麗だ」
一言、彼がそう呟いた。
「ここでなら、死んでもいい」
しばらく、三人でその丘からの眺めを見ていた。プロヴァンスの春は美しい。寒い冬を越えて、訪れた春を一面の花たちが祝福しているようだった。
死に場所を選ぶならば、自分もこういう場所を選ぶだろうとギーは思った。
「なあ、本当に死ぬのか?」
沈黙を破ったのはリヤードだった。頭をガリガリと掻きながら、車を振り返る。
「だって、俺だけじゃ使い切れないくらい金あるぜ? あんたの人生を立て直すのには十分じゃないか」
「あげるつもりですか?」
「少しだけならいいじゃん。独り占めは好きじゃあないし、アッラーは金持ちは誰かに与えるように教えている。苦しかった過去のために死ぬなんて馬鹿みたいじゃん、あんたいくつだよ? 俺より若いんだろ。顔もいいし、可愛い彼女ができる。そしたらきっと、今度こそいい家族ができるよ」
リヤードがにっこりと人懐こい笑みを見せて言った。フェリクスはなんだか複雑そうな顔で笑った。自分の幸せな姿が想像できないのかもしれない。
こんなとき、ギーは自分が何も感じていないことを疑問に思う。不幸な過去を持っている犯罪者なんていっぱいいると思ってしまう。
その中のひとつがどんな終止符を打とうとも、事件簿のひとつで終わりだと思ってしまう。
「あんたも何か言ってやれば?」
ふいにリヤードに話題を振られた。どう答えればいいのかわからなかった。立場的には出頭するように言うべきなのだろう。少なくとも、リヤードのように無差別殺人犯を野放しにする方向に誘導するわけにはいかない。
何もいい言葉が浮かんでこなくて困っていると、フェリクスがいきなり機嫌を損ねたようだった。
「先生は、俺なんて死ねばいいと思っているんだろ」
「え、そんな……」
そんなこと思っていないと言おうとして黙る。本当に微塵もそんなことを考えていないと言えるだろうか。少なくとも彼が死ねば、この事件は終わりだと考えている自分がいる。
フェリクスがこちらに銃口を向けてきた。先に動いたのはリヤードだった。フェリクスの銃を取り上げようともみくちゃになりながら、パン、と銃声が鳴る。
「ああっ」
脚を撃ちぬかれたリヤードが声を出して踞った。フェリクスは起き上がると、リヤードを殺そうと銃を構えた。
これが終わったら自分の番なのかな。などとぼんやり考えているとフェリクスがギーを見てくる。
「止めないのかよ。こいつは先生を助けようとしたのに」
人でなし。とフェリクスが呟く。
「正直に言いますよ。僕は何も感じていません。リヤードが死のうが、あなたが死のうが、僕に危害が加わらない限り何も感じない奴ですよ。だから僕に腹が立ったなら、僕に後悔をさせたいならば、その銃口はこちらに向けるべきだ」
フェリクスは銃口をリヤードからずらし、ギーに向けた。
「あんたはきっと、そうやって人に同情したようなフリをして、理解者のフリをしてきたんだろうな」
呪うような顔というよりは、羨むような表情だと思った。
「囚人の中でもあんたは人気者だったよ。俺が死んでも喜ぶ奴しかいないのに、あんたが死ぬとみんな悲しむだろうさ。あんたが何も感じていなかったって、みんな悲しむんだよ。なんであんたは好かれて、俺は好かれない? どうしてあんたは愛されて、俺は愛されない? ちょっとだけ愛想がいいだけじゃあないか。俺がちょっと不器用なだけじゃあないか。俺だってあんたみたいにやさしい言葉をかけられれば変われたかもしれないんだ。誰かにやさしい言葉をかけても、なじる言葉しか返ってこない環境でなければ違ったんだ。俺の居場所はどこにある? まだ生きて、あと何回傷つけばいい? 俺の絶望がわかるか。あんたを傷つけても何も感じないけど、責められれば苦しいんだ」
非常に身勝手といえば身勝手だが、本音といえば本音だろう。フェリクスは涙を流して訴える。
「みんな俺を物以下にしか扱わなかった。あんただけが俺を責めなかったんだ。あんたに死ねって思われたら俺は本当に死ぬしかない。あんたが悲しんでくれないなら誰も悲しんでくれないんだよ。先生、俺に『生きろ』と言ってくれ。あんたを恨みたくないんだ」
銃口を向けて、彼が生きるよう説得するんだと脅している。そうするぐらいしかお願いの仕方を知らないのだろうこともわかっていた。そしてそのとおりにしなければ、自分の命もリヤードの命も危ないこともわかっていた。
「別に僕はあなたに死ねとは思っていません。あなたが生きていてくれればそれは嬉しい。あなたが犯罪をやめてくれれば嬉しい。あなたが出頭してくれればもっと嬉しいです」
だけど死んだって何も感じやしない。
この冷めた感覚をどうすればいいのかギー自身が理解できずにいる。自分のどこかが麻痺しているのではないかと思った。
「何もわかっちゃいないんだな、先生」
フェリクスが悲しそうに呟いた。
「そんな多くは望んでいないんだ。幸せになりたいとも、やさしくされたいとも思っていなかった。ただ『生きてほしい』と望んでほしかっただけなのに」
それすら、叶わないのか。と唇が動いた。銃口は静かにフェリクスの口の中へと収まった。小さな「パン」という音と共に、たくさんの人間を殺した男の一生に幕が下りた。
カモミールの群生地に飛び散った頭部を見ながら、ギーはため息をついた。安堵からなのか、それともなんとも言えないやるせなさのためからかはわからなかった。
「大丈夫でしたか?」
リヤードに声をかける。彼は自らシャツを破いて止血をしながらギーを睨みつけた。
「この、人殺し」
何のことだかわからず、固まっていると、さらにリヤードの言葉は続く。
「フェリクスを殺したのはお前だ」
「犯罪者のひとり死んだのが何だっていうんですか? 彼は一般市民をいっぱい殺したじゃあないですか。あなたも見たでしょう?」
「あいつはお前が愛情を与えさえすれば変われたんだ!」
リヤードが腹を立てたように怒鳴った。ギーもこの言葉にはムッとする。
中途半端な愛情ではないものを与え続ける難しさも知らずに、無責任に言うリヤードに腹が立った。
「心理学も知らずに、カウンセラーはいかなるときも相手を癒すべきだって言いたいんですね。あなたは」
リヤードに自分が物のように扱われていると思った。自分だって腹が立つことだってあれば、どうでもよくなることだってあるというのに。
リヤードは立ち上がると、脚を引きずりながらギーに歩み寄ってきた。
「あんたはそういう風に、感じたことを口にできるんだろうがな、あいつはずっと、感情を踏みにじられる立場にいたんだ。そんな理不尽な立場にいたんだ」
だからハイソは嫌いなんだ。とリヤードは呟いて車のほうへと歩いていった。
世の中を見渡せばまだそんな立場の人間たちだらけだ。ギーは負け組と言っても真の負けだらけの人生というわけではない。世界には踏み台にされるために生れてきたとしか思えない人生の人間がたくさんいる。
ちょっとやそっとの愛情で救えるものではないというのはわかっている。そうして自分が生半可なやさしさを見せたことがフェリクスに希望を持たせてしまったことも。
そうして、フェリクスは世の中には誰も味方がいないことを知って絶望して死んでいった。
彼が悪かったのかと、問う。
自分が悪かったのかと、問う。
社会が悪かったのかと、問う。
答えは出なかった。強いて言うならば、善が悪いという答えにギーは至った。「悪」というレッテルを張られた者たちはそこから更生する機会を与えられない。
いつぞやチェスターといっしょに議論したアンパンマンとバイキンマンの話を思い出した。あの世界に善が存在しなければ、悪も存在しなかっただろうと。
立ち尽くすギーの耳に車の音が聞こえた。しかしリヤードが去る気配は見えない。もう一台車が丘に乗り上げてきた。
車のドアが開いて、知らない男とアランが出てきた。
「もう終わったよ」
リヤードがハンドルに寄りかかったまま、アランにそう言った。
アランは地面に横たわったフェリクスの死体を一瞥すると、棒立ちしているギーを見た。
「無事だったか?」
「はい。大丈夫です」
「そうか」
アランが安堵のため息をつくのがわかった。
「今度こそ死ぬんじゃあないかって、心配した」
何故アランが自分の心配をするのかはよくわからなかったが、それは真意な気がした。
だけどその言葉を言われる資格は自分にはないとギーは思った。