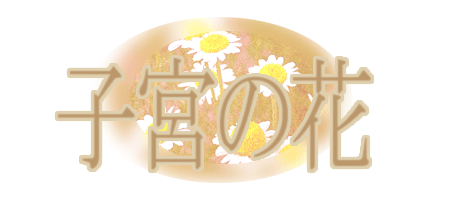
それでも何かを感じている
後ろで銃を構える音がした。見るとシャリーフが、フェリクスの銃を拾って自分に向けていた。
「金はどこだ?」
おそらくジェルヴェの脱税した金のことだろう。
アランがギーを庇うように前に出たので、シャリーフは銃口をアランに向ける形になった。
リヤードは様子を見ている。シャリーフに車の中だと言ったらリヤードが危ない。だけどこのままではアランが危ない。
どちらが死んでも、ギーにとってはどうでもいいことだった。しかし両者ともなぜか自分を守ろうとした。
無意識のうちにギーの体がアランの前に出る。銃口は再びギーに向いた。
「銃、こっちにください」
静かに、シャリーフに語りかける。
「金のありかを言えって言ってるんだよ!」
「そんなもの、途中で隠してきましたよ。いつまでも持ち歩くと思うんですか?」
「じゃあその場所まで連れて行け」
「連れて行くから、まずは銃を下ろしてください」
シャリーフの視線が一瞬リヤードのほうを向いた。おそらく彼が銃を構えているのがわかったのだろう。そのままギーはシャリーフに飛びついた。
「リヤード、そのまま撃ってください!」
リヤードはその言葉に、迷うことなく引き金を引いた。脇腹のあたりを熱いものが突き抜けていく。弾はそのまま貫通してシャリーフに当たった。
どさりと倒れて、痛みに身体を丸めた。
「乗せろ! 近くの病院まで連れて行く」
リヤードの声が聞こえる。自分の身体を誰かが持ち上げた。そこで意識を手放した。
ギーは暗闇の中に立っていた。
自分の腹に痛みがないことを不思議に思う。もしかしたら自分は死んで地獄に落ちたのだろうか。
「罪状は偽善者……でしょうか」
とりあえず罪もない一般市民という言葉は自分に適しているとは思えなかった。不意に自分の指を引っ張る誰かに気づく。
少年だということに気づいた。彼は無言でギーの指を引っ張りながら、暗闇の中を突き進む。ギーはその後ろをゆっくりついて行った。
「あの、あなたは?」
少年は振り返ると、無表情のまま「知る必要はない」と言った。
「目が覚めれば、きっとわかる」
やがて、暗闇の終点まで来たところに梯があった。
「これを登れば助かる」
「はあ」
ギーは少年を振り返った。
「あなたもこの暗闇からいっしょに抜け出しませんか?」
少年は目をぱちくりとさせて、不気味に笑った。
「もしこの梯、二人で登ったら重量オーバー。ひとりしか助からないものだとしたら、どうする?」
「一人ずつ登るじゃあだめですか?」
「それはタイムオーバーだとしたら?」
「それは困りましたね」
とは言え、あまり困っているわけではなかった。梯にかける手を止めて、こう言った。
「じゃあ、寂しくないように二人で暗闇の中にいましょうか?」
ギーがそう言ったと同時に、梯がするすると引き上げられていった。あまり未練のない様子のギーに、少年が首を傾げる。
「お前は助かりたくないのか?」
「あなたを置いてひとりだけ助かるという選択肢はなしですね。暗闇の中でも二人でいれば寂しくないかもしれないし」
ハハハ、といい加減に笑って、ギーは小首を傾げる。
「あなたもひとりは寂しかったでしょう?」
少年は唇を噛むと、ギーを見上げた。
「寂しかったよ」
「来るのが遅くなってすみませんでした」
「遅いよ。俺、もう今年で三十六歳だ」
「そんな年齢でしたか。僕より年上ですね」
「もっと早くに会えればよかったのに」
「ごめんなさい」
「でも。それでも……会えてよかった」
それから少年の言葉をしばらく聞いた。
父親と母親はよく喧嘩をしていたそうだ。小学校で家族の絵を描くように言われて、それで賞をとったのだとか。それを持ち帰ったら、両親も喜んでくれると思った。仲好くなってくれるかもしれないと思ったそうだ。
夕食を作っている母親に絵を見せようとしたら、あとで見ると言ってくれた。そうしてそのままその絵は埃をかぶったままだそうな。
「俺の絵、見てくれる?」
少年が画用紙に描いた絵を見せてくれた。青いクレヨンで描いてあるのが父親だろう。赤いクレヨンで描いてあるのがおそらく母親だ。その真ん中に緑色のクレヨンで少年の絵が描いてある。
「本当は仲好くしたかっただけなんだよ。みんな、最初は仲好くしたいと思っていたんだ」
少年はそうギーに言った。
ギーはこの少年の正体に薄々気づいていた。静かに彼の言葉を聞いた。彼の心の声にも耳を傾けた。
踏みにじられた心、かけられた罵声、自らの吐き捨てた呪いの言葉たち。その中にただひとつの真実があるとしたら、きっとこのくらい単純なものだろう。
みんな仲好くしたかったはずだ。
それぞれの事情が許さなかったり、それぞれの感情が許さなかったりしたこともあっただろう。だけど最初から人を殺そうと思う人間などいるはずがないのだ。
「やっと伝わった。俺の本心」
少年が涙を流して、笑った。少しぎこちない笑い方だった。笑い方がわからないのかもしれないと思った。
「さようなら、ギー」
名前を呼ばれたと同時に、襟首をつかまれるような感覚があった。暗闇の底はどんどん遠のき、みるみるうちに上まで引っ張りあげられる。
「ちょっと、痛いですよ」
襟首を引っ張る誰かさんに声をかける。
男は振り返ると、いつもの髭面をしかめて言った。
「いつまであそこに居る気だったんだ?」
「ええと、一生」
「馬鹿か。お前は犯罪心理学者だろう。ひとりの犯罪者の一生に取り込まれてどうする」
「そういうこと言いますか。あなたの子供の頃って可愛かったのにー」
ぶーたれたギーに、アランは「ふん」と笑った。そしてギーを光の入り口目掛けて投げ飛ばした。
――生きろ。
最後に彼の声が脳内で木霊する。
この言葉をフェリクスは欲していたのだろうと思った。死んでほしくないと心から願う感情。
ところが目が覚めたときにギーの目に映ったのはレインマンだった。
「夢を見ていました」
「のんきなものですね。死にかけたというのに」
レインマンはため息をつく。ギーは天井を仰ぎながら聞いた。
「アランはどうしましたか?」
「自ら警察に出頭しましたよ」
「今回は悪いことをしていないのに?」
「今までの罪を償うためにです」
彼の心境にどんな変化が訪れたのだろうと思いながらギーは身を起こしながら言った。
「色々、複雑な気分です」
「その複雑さをレポート用紙でありったけ説明するとしたら何枚くらい必要ですか?」
「たぶん五枚いらないと思います。意外と単純なのかな……?」
「その単純さを説明しようとしたらきっと五枚越えますよ。人間単純すぎず複雑すぎず丁度よくできているんです」
なるほどそうかもしれない。レインマンは何も説明しなくたって、ギーの心の中が読めるのだ。何が言いたいのかあっちに整頓してもらったほうが早いかもしれないという気すらしてくる。
「とうとう無口になるどころか代弁させるつもりですか。このものぐさ男」
レインマンに叱られた。ギーはどこから話すべきかわからない自分の心情をとりあえずごちゃごちゃ話して結論を出すしかないようだと、自分の醜態を晒す覚悟をした。
「僕って冷血漢なんですよ」
「そうですね。今頃気づいたんですか?」
「ええ、今頃気づきました。殺人犯が死んでも眉ひとつ動かさないし、ゲイの友達の恋人をこのあと見に行かなきゃいけないことで気が重たいったらない」
「僕の恋人を紹介して欲しいならばあとで紹介しますけど、無理に見なくてもいいですよ。怪我治すほうが先でしょうに」
レインマンが低い声で呻いた。たしかに怪我を治すほうが先だ。
「他には?」
「僕はぶっちゃけカウンセラー向いてないんじゃあないでしょうか。相手をまともにしようとかいう気、まったくありませんし」
「むしろ熱意のありすぎる性格矯正マシーンなカウンセラーにあなたはかかりたいんですか? たしかに質のいいカウンセラーではありませんが、質の悪すぎる勘違いカウンセラーではないですよ。あなたは」
たしかに性格矯正マシーンと化したカウンセラーにかかりたいとは思わない。ギーは少し沈黙し、さらに言った。
「僕って患者さんたちのことまったく考えていないんですよ。とりあえずお給料が約束されていればいいんです」
「そりゃあ、まったく考えていないのは問題でしょうけれど、ボランティア精神でやるには骨が折れる仕事でしょうに。お金貰わないとやってられないのも確かです。無償の愛や無償の奉仕なんて、理想でしかない」
レインマンはばっさりと切り捨てるように言った。そのとおりだ。別に自分が常に無償の愛や奉仕をし続けなければいけない義務などどこにもないのだ。
「僕って冷たい奴なんですよ」
「先程も聞きました」
「それなのに、みんな僕のことをやさしいとか勘違いして、僕に余裕がないときに勝手に『最近つめたいね』みたいに裏切られたような顔するんです」
「そのみんなって言うのは具体的には犯罪者たちのことですよね? 言っておやりなさい。『僕はあなたたちのママンではありません』と。少なくともマリー・ルイーズや僕はあなたに過分なやさしさなど期待していません」
「だけど、裏切られたような顔をされると、僕が悪いような気がしてくるんです」
「あなた本当に心理学を習った人ですか? そんなの相手の心理操作です。罪悪感を植えつけることであなたが思うとおりの反応をするように仕向けているだけじゃあないですか」
「わかってますよ。わかっていても、僕が悪いんじゃあないかって気がしてくるんです……」
レインマンはギーになんて言ってやるべきかわからず沈黙した。
ギーが人に心を開かないのは、傷つくのがわかっているからだ。今、少しだけレインマンに心を開いているのは、レインマンがそれだけ信頼されていると思っていいだろう。
学問でわかるような答えを欲しているわけではないのだ。そしてギー自身が欲している言葉があるわけではない。
要はこう言っているのだ。
「どうすればいい?」
と。しかし具体的に「これについてどうすればいい?」という質問形式でないと、レインマンも漠然としすぎて答えを出しようがない。
だけどギー自身が何について聞きたいのか自分でよくわかっていないのもわかる。しかしそれについてお付き合いしていると、彼の縫ったばかりの傷口に響くのも事実だ。
「あなたの責任ではない。あなたの中途半端な態度に感化されて改心する奴もいるんです。悪いばかりではないですよ」
結局、話題を打ち切ることにした。ギーは少し納得していない表情だったが、何に納得していないのかも理解していなかったから引き下がるしかなかった。
その話題が途切れた頃だった、個室の引き戸が開いて、リヤードが顔を出した。
「なんだよ。俺より先にそっちの男のほうに行くわけ?」
リヤードが眉をひそめてレインマンにそう言った。このふたりは知り合いなのか? とギーが首を傾げると、レインマンは立ち上がってリヤードを睨みつける。
「金に目が眩んで脱獄囚に協力するような恋人と巻き込まれた同居人だったら、もちろん同居人を優先ですよ」
ちょっと待て、恋人だと? ということはレインマンの恋人というのはリヤードのことだったのか。とギーが思っていると、リヤードは
「俺はそいつを守ろうとして怪我したんだぞ? 胸が痛まないのか、エミール」
と言った。
「あなたは脚を撃たれただけ、ギーくんは腹部をあなたに撃たれたんですよ? 怪我の重さだってこっち優先して当然でしょうに」
「さてはお前、俺のことどうでもいいと思っているだろ」
「今はそう思っているかもしれませんね。正直呆れていますよ。タクシー業クビになったそうですね? 本末転倒ですよ。お金が欲しいんなら言ってくれたら差し上げたのに」
「『言ってくれたら差し上げたのに』ってなあ。お前のその金のありがたみのわかってないあたりが嫌いだ。俺の劣等感をびしびし刺激するような大盤振る舞いなあたりがな!」
「悔しかったら正攻法で出世しなさい。貧乏人」
それは言いすぎじゃあないだろうか。とギーが止めようとしたら、リヤードが先にぷっつんした。
「誰もが学校へ行けるだけの金があると思うなよ! てめぇのそういうところが嫌いなんだ」
「学校に行きたいなら学費くらい出そうじゃあありませんか。あなたがその年齢で高校に行くのが嫌なだけでしょう」
「俺個人を馬鹿にする分には構わないが、お前の態度は貧困層全部を馬鹿にしているんだよ。それが腹立つって言ってるんだ」
「勘違いしていませんか? 僕はあなたのことを馬鹿にしていませんし、貧困層を馬鹿にしているわけではありません。僕が嫌味な貴族かぶれでも、親の七光りでも構いませんよ。金が必要ならば利用すればいいのに。僕はあなたとうまくやっていきたいのに、なんで僕のお金を嫌うのかよくわかりません」
レインマンってそういうところ無神経そうだものなあ……とギーは思った。リヤードの気持ちもレインマンの気持ちもわからなくもないが、なおさらこのふたりは恋人同士としてうまくいかないのではないかという気がしてきた。
「それで、掘り出したお金で何を買いたかったんですか?」
レインマンの質問に、リヤードが黙り込む。小声で何か呟いた。
「聞こえません」
「てめぇ、心ん中読めるんだろ?」
「あなたの心の声は読めませんから」
「プレゼントだよ! てめぇに家賃立て替えてもらったり、防寒着買ってもらったりしてばかりじゃ申し訳ないから、なんか景気よくぽーんと買ってやろうと思っただけだって」
リヤードが逆切れしたような口調でそう怒鳴った。レインマンがいよいよ呆れたような顔をした。
「あなたは、僕が汚れたお金で買ったプレゼントで喜ぶとでも思ったんですか? 人から奪った金で買ってもらっても嬉しくないです。見栄はらなくていいですよ、何もいりませんから」
「……。お前さ、人の気持ちが読める占い師っての、嘘だろ」
今度はリヤードが呆れたように呟いた。たしかにささやかなりにプレゼントをあげようと頑張ったリヤードが可哀想すぎるとギーも思った。
「お前は俺の気持ち考えたことあるのか?」
「わからないから理解したいって言ってるんじゃあないですか」
「察しろよ。エンパスの能力が使えないだけでここまで無神経になれるお前が化け物に見える。いっそエンパスより恐ろしい」
「エンパスだからって何でも察することができると思ったら大間違いですよ。みんな僕に対して言葉で説明するのを端折りすぎです!」
それは逆切れだ。とギーは感じる。そもそもあれだけ心を読み取る能力があるのを不気味に思わない周囲に感謝するべきだろうとすら思うのだが。
リヤードが舌打ちをすると言った。
「口にしなきゃわかんないって言うなら言ってやるよ。お前が、好きだから、なんか喜ぶようなことを、してやろうと、思ったんだ! たしかにモラル的にはちょっとよくない方法だったと思うけれども、俺の気持ちをちょっとは考えろ」
リヤードは「わかったか?」とレインマンに聞いた。すごい剣幕で喧嘩を売るように言われて気おされたレインマンはこくんと頷くのが精一杯だった。
「ったく、なんでお前みたいな性悪占い師が好きなのかわからん」
ぶつぶつ呟きながらリヤードが外に出て行った。目の前で盛大な男同士の痴話喧嘩を見せ付けられて、ギーが沈黙していると、レインマンがギーを振り返って言った。
「性格も根性も悪くても好かれる人もいるんですよ、僕みたいに」
ギーはレインマンのそのポジティブぶりにびっくりした。
「だからあなたも、いい人が苦しいならばやめちゃえばいいと思います。やめたところで、あなたは僕より性格の悪い男にはなりませんよ」
「……わかりました」
どう努力してもレインマンよりもふてぶてしく生きることもポジティブに生きることも自分にはできそうもなかった。