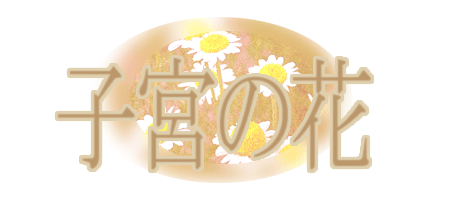
初めて人間だと思った
その日、ギーは留置所を訪れた。目的は、来週にはアメリカ政府に引き渡されるアランに会うためだ。
「坊やのほうから会いに来てくれるとは思っていなかったよ」
アランはいつものように不気味に笑ってそう言った。
「といっても、私のほうから君に会いに行くことはもう出来ないがね」
「あはは。差し入れにフィナンシェ焼いてきました」
美味しそうなバターの匂いがする紙袋をアランのほうに引き渡す。そこからが本題だった。
「どうして出頭する気になったんですか?」
「それも悪くないかな、と思ったんだよ」
「でも、死刑になるかもしれないんですよ?」
「もし死刑になったら、坊やはもう私の翳に怯えずすむだろうな」
ククク、と笑うアランにギーが笑わずにいると、アランは真顔に戻った。
「あまり面白くはありませんでしたよ?」
「冗談を言うのは苦手でね」
「真顔でたまに変なことは言いますよね。あなたって」
「たとえばなんだね?」
「『青い目玉ってどんな味がするんだろう』って、露店で青い卵買ってきたりとか。自分が監禁されているときに自分の目と同じ色の目玉焼きが出てくるんですよ? いくらトリッキーなお菓子に目が慣れていたって、あの目玉焼きはいただけませんでした」
「味は普通の目玉焼きだったがな」
「意外と美味しかったですよね」
またアランとの会話がずれた方向に進みそうになった。慌てて軌道修正する。
「死にかけたとき、夢の中にあなたが出てきたんですよ」
「ほう。夢に出てくるまで想われていたとはな」
「ええ。これくらいの可愛い少年でした。僕に家族の絵を見せてくれて、『本当はみんな仲好くしたかったんだよ』って教えてくれたんです。それがあなたの本心かどうかはわかりませんが、僕は小さな頃のあなたに、犯罪心理学者として忘れちゃいけないことを教えられたと思ったんです」
「忘れちゃいけないこと? それはどんなことかね」
「みんな人の子だってことです。最初は愛されることを信じて生れてきたんですよ。傷ついたりして少しずつ歪んでいったかもしれないし、残念な結果や取り返しのつかないことをしでかしたかもしれないけれども、それでもみんな人間だったんだってことです」
「……そうかもな」
アランの少し照れてぶっきらぼうな返事に、ギーは笑った。
「画家として人物画を描いたのは、お前が最初で最後だ」
笑っていたギーに、いきなりアランはそう言った。
「人が初めて人に見えたんだ。お前に会えてよかった」
ギーは笑うのをやめて、瞼を少しだけ伏せた。
「僕はそんな言葉をいただけるほど、いい人じゃあないんです」
アランは鼻で笑うと頬杖をついて言った。
「立派な坊やになんざ興味はない。お前はいつだって食い意地の張ったプロファイラーだった。明日の命よりも今日の食べ物って男だろうに。その少しズレた神経が好きなんだ」
「人間、どこが好かれるかわかりませんね」
ギーが複雑そうな顔をした。
「もしよかったら、獄中でも絵を描いてください。画家と知り合いだったのに、その人の絵が一枚もないなんてなんだか勿体無い気がして」
「アパートにある絵をてきとうに持って行け。私は画家としては死んだも同然だ。売れば高い値がつくだろう」
「あれはほとんど警察が持って行っちゃったんですよね」
「そうか。勿体無いな」
アランは残した絵にさして興味がなさそうにそう呟いた。
「手紙を出すよ。届くかどうかはわからないが」
そこで面会時間は終わった。
留置所をあとにすると、外で待っていたマリー・ルイーズがガレットを手に近づいてきた。
「ギー、終わったの?」
「はい、終わりました。何のガレットですか?」
「チーズとレタス」
「美味しそうですね。一口ください」
「食べたいならば自分で買いなさいよ。私はこれひとりで食べたいの」
ガレットをかじりながら先を歩くマリー・ルイーズの後ろをついていく。歩幅はギーのほうが大きいため、すぐに追いついた。
「そういえばギーは兄さんの恋人に会ったんでしょう? どうだった?」
「金にがめついけれども、悪くない男でしたよ」
「本当? 兄さんと釣り合うような男だったわけ?」
「さあ、どうでしょう。少なくともエミールの無神経っぷりに彼が愛想を尽かさないあたり、懐の深い男だと思いますが」
「ふうん。じゃあ様子見かな」
ぱくぱくとガレットを食べながらマリー・ルイーズがそう呟く。ギーは我慢できなくなって隣からそのガレットに噛み付いた。
「ああっ!」
「あ、美味しいですね」
口をもぐもぐ動かしながらギーがそう言うと、マリー・ルイーズは
「私、ひとりで食べたいって言ったのに! この食い意地張りまくり男っ」
と言って大きく口を開けると残りを全部食べてしまった。
「そんなにお腹空いていたんですか」
その質問にマリー・ルイーズは何かを言おうとしていたが、口の中の食べ物でしゃべられないようだった。
「今日の夕飯なんだろうなあ」
ギーはそう呟きながら駅のほうへと歩いていった。ようやく口の中身を飲み込んだマリー・ルイーズが後ろからついてくる。
「ギー、なんで女の子とふたりで歩いてるのに夕飯のこと考えているのよ!」
「えー。お腹空いたからですよ。早く帰りましょう」
ここでいっしょに食事をしていこうという展開にならない鈍い男にマリー・ルイーズはため息をついた。
今日も食事は仲好く三人で取ることになりそうだ。