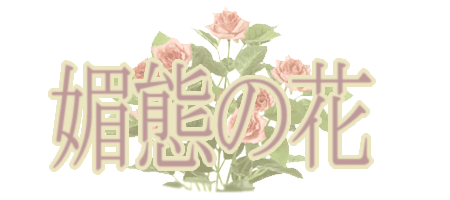
05/10
シャンティーは、パリから少し北のところにある、美しい街だ。上流貴族の優雅な暮らしと聞けば、思わずこんな風景を思い浮かべるのではないだろうか。
懐かしいフランスに到着してすぐに、レインマンを迎えにきた車にギーは思わず息をのんだ。
「リムジン……」
「初めて乗りますか?」
レインマンは慣れた様子でリムジンの後部座席に入ると、ミネラルウォーターをグラスに注いだ。
「ギーくんも飲みますか?」
「あの……レインマンの家ってもしかして、すごくお金持ち……なんですか?」
「なんだったかなあ……公爵だったか侯爵だったか」
「爵位あるんですか!?」
「昔は、ですけどね。フランスの爵位制度がフランス革命のときに撤廃されたのはあなたも知っているでしょう。とはいえ、ボードレール家はけっこう古い家系ですよ。ああ、ギーくん。僕のことはレインマンでなく、エミールと家族の前では呼ぶように」
「エミールさん……」
記憶の彼方にあったレインマンの本名を思い出しながら、呟いてみた。
森の中の緑道を車が走る。レインマンの実家が近づくにつれて、ギーの心臓は緊張でばくばく言いはじめた。
やがて、大きな塀が見えたと思ったら鉄格子をガードマンが開け、さらに奥へと車は進み、百メートルほど行ったところにあった屋敷の前で止まった。
「お疲れさまです、ギーくん。ここが僕の実家です」
豪奢な建物に唖然としているギーにレインマンが声をかけた。運転手がギーとレインマンの荷物を外に運び出したので、ほぼ手ぶらで屋敷の中に入った。
「ただいま帰りましたよ」
レインマンが大声でそう言った。
二階に続く長い階段を、ベージュのパンツを履いた女が下りてくる。
「兄さん、お帰りなさい」
「マリー・ルイーズ、お久しぶりです」
再会のキスをすませると、マリー・ルイーズはギーを見た。
「初めまして。今日からしばらくお世話になる――」
「ううん、言わなくてもいいのよ。あなたのことは夢の中で何度も見たから、今日が初めましてじゃあないの。よろしく、ギー」
「……よろしくお願いします。マリー・ルイーズ」
マリー・ルイーズはレインマンとあまり性格が似ていないのだな、と思った。フランスにいた頃のレインマンの話は聞いていないが、十八でアメリカに渡ったきり一度も戻っていない実家である。レインマンはもしかしたら妹か、または家族が苦手なのではないだろうか。
自由に使ってよいと案内された部屋は、四十平方はあるかと思う大部屋だった。
既に届いている荷物の荷解きをしたあと、自分の荷物の半分はお菓子を作る道具だったことに気付いて、やはり自分は犯罪心理学者よりもパティシエになるべきだったかもしれないと思った。
「イタリアのおばさんの家に大人しく住むべきだったかなあ…」
あまりにも分不相応すぎる家具に囲まれて、ギーはため息をついた。蹴飛ばして何か壊してしまったら弁償なんて話にならなければいいけれども、と思いつつ。
窓から外を眺めると、綺麗な庭園が広がっていた。その端のほうに、小さな硝子張りの温室を見つけた。
「……薬草園?」
部屋を出て、階段を下りて庭のほうへと向かった。近づいてみるとそこはやはり薬草園で、小さい頃見慣れた花や草がたくさん生えていた。
温室を外から眺めていると、後ろから声をかけられた。
「ハーブに興味があるの?」
振り返るとマリー・ルイーズがいた。手にはバスケットと鋏。
彼女は温室の扉を開けると、ギーを手招きしてから中に入った。
「何を摘むんですか?」
「メリッサよ」
「レモンバームですね。僕の子供の頃のハーブ園にもありました」
「兄さんはメリッサの香りが大好きなのよ。少しスパイシーで、甘くて可愛い香り」
メリッサを摘みながらマリー・ルイーズは言った。
「ねえギー、私があなたに贈った香水、気に入ってくれた?」
「あ……まだ使っていません」
「あなたのために私が作った香水よ。是非使ってちょうだい」
「ちょっと、香りが色っぽすぎるんですよね。僕、香水ってウッディ系しかつけたことなくて」
「だめだめ。あなたはもっと大胆な香りつけなきゃ。あの香水もローズとジャスミンとイランイランで作ったのよ? どう? あの香りつけて落とせない男はいないわよ」
「男落としてどうするんですか」
ギーがげんなりしたように呟いた。マリー・ルイーズはバスケットを持ったまま立ち上がると、じっとギーを見つめた。
「もしかして、兄さんの恋人じゃあないの?」
「は? いえいえ、違います。エミールは僕の命の恩人であって、それ以上の関係ではありません」
「そうなの?」
「そもそも、何か勘違いされているみたいだから言っておきますけど、僕は女じゃあありません。男です! 女顔だからそう思われても仕方がないけれども」
マリー・ルイーズは呆れたように「知ってるわよ」と言った。
「兄さんがここ追い出された理由知らないの? エミールは同性愛者よ。お父さんに勘当されてアメリカに渡ったの。行方を捜すまでにどれだけの金を探偵に払わなきゃいけなかったかわかって? 父さんが死んだ今ならば、誰も兄さんを責めたりしないわ。もちろんあなたも」
「いえあの、本当に僕はエミールの恋人ではないんですよ」
しどろもどろにギーは言った。
マリー・ルイーズはつまらなさそうな顔をして、「あなたなら兄さんにいいかもと思ったのに」と呟いた。
冗談ではない。早いところ新居を見つけて出て行かねばどういう展開になるかわからない。そう思って部屋に戻った。
不動産の電話番号を電話帳で調べている最中、扉をノックする音が聞こえて、半分だけ扉が開いた。そこから滑りこむようにレインマンが入ってくる。
「片付けは終わりましたか?」
「ええ、あまり荷物を持ってきていなかったので」
「もう新居を探しているんですね」
電話帳を片手に持っていたのでそう言われた。ギーがレインマンをやや警戒するように見たので、レインマンはため息をついた。
「何をマリー・ルイーズに言われたのか僕が読み取れるのを忘れてますか?」
「あ……すみません」
「僕はあなたをとって食うために家に呼んだわけではありませんよ。分別はあるつもりです。あなたが新居を見つけて出て行くまで何もしませんから、そうせかせかしないでください」
「はあ……すみませんでした」
信じていいのかわからなかったが、とりあえず謝ることにした。信じると言っても信じないと言っても、レインマンの場合心を読み取るから関係ないわけだが。
「僕は今日一気に信用を落としましたね。マリー・ルイーズめ、余計なことしてくれましたね」
「マリー・ルイーズはあなたの味方のように思えましたが?」
「ただ単に広い屋敷に使用人と自分しかいない環境に耐えられなかっただけですよ。女性が家督を継げない時代でもないのに、わざわざ僕を探して呼び戻すなんて」
「家督、継ぐつもりですか?」
「そのつもりですよ。いちおう一族の長男ですからね」
レインマンは扉に手をかけて、振り返った。
「もうすぐ夕食です。食卓へ来てくださいね」
そう言うと扉を閉めて出て行った。
大金持ちの食べる食事というのは特別豪勢なものなのだろうかと思ったが、彼らは健康嗜好らしく、サラダと玄米のオードブル、それと羊肉をレモンとバジルでローストしたものが出された。もちろんチーズとデザートもたっぷりと出た。
「ギーくんはいっぱい食べてもいいんですよ? 何か作らせましょうか?」
「は? いえいえ、十分いただきましたので」
「でもあなた食べるの好きなほうでしょう。あとで外食に出たりするとけっこうな手間ですよ」
「僕のことをいやしん坊だと思っているみたいですけれども平気ですよ。本当大丈夫ですので」
ギーとレインマンのやりとりを聞きながらマリー・ルイーズがくすくすと笑った。
「ふたりともとても仲がいいのね」
「からかうものではありませんよ、マリー・ルイーズ。あなたのせいで僕の信用はがた落ちなんですからね」
軽く叱るように言ったレインマンにマリー・ルイーズは不思議そうに首をかしげる。
「兄さんは黙っていてもバレることを黙っておくつもりなの?」
「なんで黙っていてもバレるんですか、バレるわけないでしょう」
「だってギーが恋人でないってことは、この屋敷に男を連れてくるつもりでしょう?」
ぶっ、とギーは飲みかけていた紅茶を吹きかけた。レインマンは頭が痛いといった顔をして、「そんなことはありません」と言った。
「いえ、エミール。僕に遠慮しているのであれば僕はゲイに偏見はありませんのでご遠慮なく」
「ギーくんまで何言ってるんですか。帰ってきて早々そんなことするわけがないでしょう」
呆れたようにレインマンは言うと先に席を立った。
「怒らせちゃいましたかね……」
「兄さんが怒ったところなんてほとんど見たことはないなあ」
「ほとんどってことは、たまには怒るんですか?」
「一度だけね」
マリー・ルイーズはバスケットの中からマシマロをひとつ摘み、食べながら言った。
「うちのお父さんが、無理やり女の人と結婚させようとしたときに、そりゃあもう腹を立ててね」
「そうなんですか?」
「父さんが強引すぎたのよ。勝手に段取りつけて無理やり何度かデートさせて、そこらへんはエミールもお父さんの顔を立てて付き合ったけれども、その三ヵ月後には結婚させようとしたんだから」
「……。随分強引だったんですね」
「ほら、兄さん美形だし、性格だってそんな酷いわけじゃあないし、相手の女性はけっこう本気だったかもしれない。だけど兄さんもひどいわよね、きちんと相手の女性と決着をつければいいのに、一日で荷物をまとめてアメリカに行っちゃうんですもの」
「お父さんはそのぅ……けっこう厳格な方でしたか?」
「まずホモセクシュアルなんて受け付けないタイプね。ママンが離婚した理由もなんでも四角四面に判断しかできないからじゃあないかしら」
「なるほど、そうだったんですね」
レインマンはかなり苦労したのだな、と思いながらマリー・ルイーズに別れを言うと自室に戻った。
やることがなかったのでラジオのニュースを聞きながらメールチェックをしていると、チェスターから一通きていた。
――無事ついたか?
そういえば着いた連絡をいれていなかったと思い、メールを返信したあとに暇をもてあまし、風呂場に向かった。
熱いシャワーを浴びて髪の毛を洗い、服を着替えて部屋に戻った。電気を消したはずなのに部屋の電気はつきっぱなしになっており、中を覗くとレインマンがいた。
「何か用ですか?」
「暇だったので親睦を深めにきただけですよ。シャワー浴びてきたみたいですね、あなたも暇だったんでしょう」
図星を突かれて、口をつぐむ。レインマンが椅子に座っているので自分はベッドに腰掛け、向かい合う。
「考えてみれば僕はギーくんの過去を勝手に読み取りましたけど、あなたは僕についてほとんど知らないに等しいですよね。平等とは言いがたい」
「じゃあどうしようって言うんですか? 僕にあなたを質問攻めしろって言うんですか?」
「ゲームをしませんか? あなたプロファイラーの卵でしょう。僕にいくつか質問をして僕を分析してみてくださいよ」
「あのですね……」
呆れたようにギーは言った。
「FBIのプロファイリングは犯人の性的ファンタジーが現場にない限り使い物にならないんですよ。カンターの捜査心理学においてもほぼ同じことが言えます。あなたの読心術と僕のプロファイリングをいっしょにしないでください」
「同じようなものだと思いますよ?」
レインマンは悠然と頬笑んで言った。
「僕はその物質に触った人の記憶を読み取ったりしますが、それはただ触れば伝わってくるものではありません。その人は普段どんなことを感じているのか、どんな家族構成なのか、どんな過去があるのか、想像するんです。その想像がただの想像でなく事実と近いというのがエンパスの能力の基本ですから、それってプロファイラーと同じじゃあないんですか? 犯人の残した証拠からその犯人がどんな人間なのか想像するという意味では」
「たしかにそうですけど……僕の能力はレインマンのそれよりももっとお粗末なものですよ」
「そんなことはないですよ。あなたはとても知的です。会話を楽しんでいるんですから、そんな正確にやろうと思わずゲームだと思ってください」
ギーは困ったようにため息をつくと、近くにあったメモ帳を取り出した。
「これに、犯人の前提で何か犯行声明文を書いてみてください」
「面白そうですね。やりましょう」
あっさり了承するとレインマンはさらさらとペンで文章を書いた。
「どうぞ」
渡された文章を見るとそこにはこう書かれていた。
「かわいいナンシーちゃん、
白い下着を身につけて、
お鼻は赤く、
手足はなく、
長く立っていればいるほど
丈が短くなっていく
ナンシーはだあれ?
私はだあれ?」
「うわあ」
思わず頬が引きつる。マザーグースのろうそくの歌だ。
「これ五分で思いつくってどんな頭しているんですか? レインマン」
「犯行声明文ってどういうものか思いつかなかったので」
「かなり猟奇的ですよ。この犯人像は間違いなくサディストの気があります、あと演技じみた性格をしていて、何かを演出するのが好きなタイプです。自分のことを相手に知ってもらいたいと思う反面、相手に必要以上に自分の情報を与えない」
「あー、けっこう僕ってそういう人ですよ」
レインマンがにこにこしながら言った。
「でもそれって素人でも分析できる範囲ですね。もうちょっと詳しい情報はないんですか?」
「筆跡が跳ねたりのびたりけっこう自由な感じがします。これはZタイプの文字に分類されるために比較的普段はおおらかで、堂々としているタイプです。交友関係で問題を起こすことはほとんどありません。誤字がないところから通常の教育を受けているかそれ以上、あとこれは基本かもしれませんが男性ですね。僕にわかる範囲はそれくらいです」
「じゅうぶんじゃあないですか」
レインマンは拍手をして、にこにこ笑った。
「そして最後に呑みこんだ言葉、言ったらどうですか?」
最後に呑みこんだ言葉、と言われて思わず息を呑んだ。しかし隠すのは無理だとわかっているので仕方なく、「エディプスコンプレックスがありますよね」と言った。
「エディプスコンプレックス?」
「幼児が同性の親を憎んで競争することで、異性の親の愛を求める傾向にあることをそう言うんです。レインマンは男性ですから、この場合はお父さんが敵視する対象ですね。母親の愛情は適切だと感じても父親の愛情を適切だとはあまり感じない、また父親があけっぴろげに愛情を表現すると困惑するけれども、自分自身が父親に愛情を表現することにも困惑したりしませんか?」
レインマンは神妙な顔をして、沈黙すると
「なんで僕のお父さんとの関係を見てきたように当てちゃうんでしょうね。現代の心理学ってすごいなあ」
と呟いた。
「僕の父親は立派な人でしたよ。だけど僕は父のようになりたいわけではない。今でこそ愛されてないなんて思っていませんが、だからといって許せるわけじゃあないあたりが、僕の了見の狭いところですよね」
「自分の心を整頓するのにはすごく時間がかかるものですよ。だって、誰もが自分自身の人生の当事者ですから」
レインマンはふっと笑って
「ギーくんはやさしいですね。僕はそうはなれそうもありません」
と言った。ギーは不思議そうに首をかしげる。
「僕のレインマンのイメージって、けっこうやさしい人なんですけれども、違うんですか?」
「やさしい? 僕が。自分のことをやさしいと思ったことはありませんね。礼儀正しいと思ったこともありませんよ。父親から見たら僕は失敗作だし、僕自身も色々失敗していると思っています」
「そんなこと、ないです……」
レインマンが自分自身を卑下しているだけだというのに、なぜかギーまで悲しい気持ちになってくる。
レインマンはその感情を察知したかのようにやさしく頬笑んで、手を軽く振った。
「ほら、暗い顔しない。大したことじゃあないんですよ、僕って十五歳くらいから夜遊びが激しくて家にはまったく帰ってこなくて、男たちの家を泊まり歩くような奔放な子供だったので、だから色々順調にきた人生とは違うって、それだけです」
ギーが目を白黒とさせていると、レインマンは調子に乗ってぺらぺらと話した。
「あなたは知っているかどうか知りませんがね、割と男同士の世界っていうのは欲望の世界でもあり、男女以上に面倒な世界でもあってですね……責任とれだの、浮気がどうのだの、けっこうまだるこしいんですよ」
「いや、それは、女性の場合でも責任とれだの浮気がどうだのってあると思いますよ?」
「そうでしょうか? 女の子はけっこう恋愛に自由だと思いますけれどもね」
「そうかなあ……」
納得がいかない、という表情のギーにレインマンは笑った。
「あなたは恋に対して真面目そうですよね」
「え? ……僕の恋愛遍歴の記憶を勝手に覗きましたね!」
赤面して腹を立てるとレインマンはくすくすとおかしそうに笑った。
「アメリカからイタリアじゃあ遠いですけど、フランスからならちょっとじゃあないですか。どうですか? 大学生時代のガールフレンド、待っているかもしれませんよ?」
「あのですねえ……」
ギーは自分をからかうレインマンに何か言ってやろうかと思ったが、結局言い返せる言葉が見つからなかったのでかわりにため息をついた。
「忘れられていますよ。四年もアメリカにいたんですから」
どうせ、レインマンのように奔放な恋など、自分にはできやしないのだ。