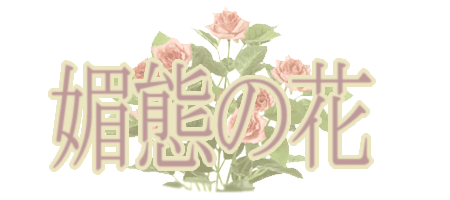
05/11
翌日から職探しが開始された。ギーは「ショコラのお家」の息子である。できることならばスイーツ店で働きたいと思って最初にパリのパティスリーを当たった。
「ショコラのお家の息子? へえ、随分昔の話持ち出すね。お菓子づくりは得意なのかい?」
最初はみんなこう言う。
「ためしにお菓子を作ってもらおうかな。カトルカールは焼ける?」
そしてだいたいお菓子を作らされる。
「うーん、家庭の味としては美味しいけれども、店に出すには今一歩だね。君くらいのお菓子を作れる人、パリにはたくさんいるから」
試食されて、だいたいそういう結論に至る。
三軒回っただけで手には焼いたばかりのお菓子の紙袋が三つ。これ以上回っても同じ答えが返ってくるのだろうと思い、仕方なく職業斡旋所に向かった。
最初はお菓子屋かプロファイラーとしての仕事を探したが、そう簡単に転がっているわけもなく、この際贅沢なことは言っていられないと事務や販売の仕事も探してみた。
自分でもできそうな求人をプリントアウトして、屋敷に帰る前にカフェに寄った。
本当はテラス席がいいが、席代をそんなに払っている余裕はなかったので立ち飲みの席で珈琲を啜る。
自分の他にもうひとり、立ち飲みの席には女性がいた。歳は大学生くらい、白いシャツと紺色のタイトスカート姿だった。その顔に見覚えがあって、ギーは名前を呼んでみた。
「フランチェスカ?」
「へ?」
クーペのサンドイッチに噛み付いていたフランチェスカが振り返る。
「……うっそ。ギー?」
「はい。そうです」
「やだ、いつ帰ってきたのよ!」
フランチェスカが嬉しそうにそう言った。彼女はギーの親戚だ。ギーがイタリアに留学していたとき、彼女は逆にお菓子の作り方を習いにパリまできていた。
「つい昨日アメリカから帰ってきたんですよ。お久しぶりです、その後コモに帰ったと思っていたのですが、ずっとパリ暮らしですか?」
「一度パリの空気に慣れると田舎ってどうも苦手でさー。親といっしょだと門限とかもうるさいしね」
フランチェスカが「あはは」と笑った。
「でもよかった、元気そうね。アメリカはどうだった?」
「思ったよりも食事が不味かったのが印象的です。ケーキのトリッキーなデコレーションが忘れられません」
「ギーは相変わらず食べ物のことだけね」
「そういうフランチェスカの噂はタルティーニ家でよく聞きましたよ。イチジクの干菓子を全部食べてお腹を下したとか」
「それ言ったのお母さんでしょう。あの人昔の話すぐに持ち出すんだから」
フランチェスカが少し拗ねた顔をして、それからギーに聞いてきた。
「フランスには一時帰国?」
「いいえ。しばらくはフランスで過ごすつもりですよ。仕事だって探しています」
鞄の中にあった求人の紙を見せると、フランチェスカは思いついたように言った。
「ギーは犯罪心理学のスペシャリストだよね? 私の大学の心理学の臨時講師とかどうかな」
「あるんですか? そんな職業」
「ねじ込むのよ。犯罪心理学のスペシャリストはうちの大学いないから、もしかしたらOKもらえるかも」
フランチェスカは大学と彼女の電話番号を手帳に写すと、それを千切ってギーに渡した。
「気が向いたら、電話して」
「ありがとうございます」
「じゃ、私、今から友達の家に行くから、また今度ね」
フランチェスカは手を振って別れを言うと雑踏の中へと消えていった。
ギーはてのひらのメモ用紙を見つめた。大学で犯罪心理学を教える程度だったら、本格的に怖い目にもあわないだろう。
ボードレール家に帰るとマリー・ルイーズが「どうしたの? そのお菓子」と言ったので、お菓子の紙袋を彼女に渡した。
「カトルカールと、フィナンシェと、マシマロです」
「大好物だわ」
「僕の作るお菓子は家庭の味でしかないらしいです。でもいいんです、美味しく食べてくれる人はいっぱいいたので」
「あとでお茶の時間にしましょう。ミントを摘んでくるわね」
マリー・ルイーズと別れたあとは自室に戻り、まず教えてもらった大学に電話をした。
犯罪心理学の臨時講師として雇ってもらえないかと交渉してみると、「正規の教授でなく、あくまでパートタイムでいいならば考える」と言われた。
電話を切って、パートタイムとしての収入がどれほどのものになるのか少し考えてみた。とらぬ狸の皮算用ではないが、多めに考えても、一人暮らしをするのには少し心許ない収入だ。
もうしばらく、ボードレール家にお世話になる必要がありそうだった。