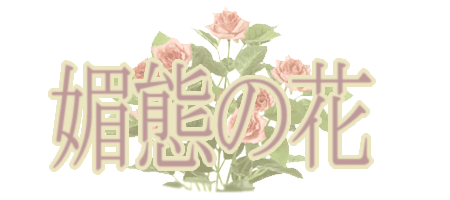
05/12
その日の朝、レインマンはいつもと違うギーのスーツ姿に目をぱちくりとさせた。
「面接ですか?」
「ええ。大学で臨時講師のパートの仕事があるそうなので」
「そうですか。受かるかどうか占ってさしあげましょう」
ちょうどタロットカードで朝の練習をしていたレインマンがカードを並べはじめる。
「結論から言いますと、受かります」
ギーがホッと胸をなでおろすと、続きがあった。
「仕事自体はうまくいきますよ。そしてあなたと縁の深い人に出会うとでています」
「それはきっとフランチェスカのことですね」
「ギーくんのフランスでの交友関係までは僕は知りませんよ。ほら、バスが出る時間まであと五分切りましたよ」
「あっ」
腕時計を確認して、急いで階段を駆け下りると、「昨日のマシマロは美味しかったですよ」という声が後ろから聞こえた。
屋敷からゲートまで百メートルはあると思われる道を全力で疾走し、ぎりぎりバスに間に合って飛び乗った。
呼吸を整えてからネクタイを直し、バスで五分の距離を揺られながら移動した。窓の外に青々と茂った森が見える。ここら一帯の景色はフランスの中でも特に風光明媚なところだろう。
パリに住んでいた頃は電車で一時間ない距離のところにこんな綺麗な景色があっても見向きもしなかった。アメリカから戻ってきて思ったことは、やはりフランスは美しい国だということだ。
フランチェスカは都会が好きだと言ったが、ギーは田舎のほうが好きだ。そして故郷が好きだった。
大学での面接は緊張することなく話せて、その場で採用が決まった。やはり受かると思いながら話をすると自信たっぷりと話せるものだ。行きがけのレインマンの占いに感謝しながら面接をした教室を出た。
さて、せっかくだから大学の中を見て回ろうかと思い、講義を行っていない教室や、庭を散策してみた。
だいたいの地理を把握したときだった。ギーは自分の目を疑った。裏庭で掃除をしていた清掃員が、自分に危害を加えた人物に見えたからだ。
「あれ……?」
いくらなんでもこんなところにアランがいるはずがない、と思って空を見上げ、もう一度掃除夫を見た。間違いなくアラン=アレキサンドラだった。
ふと、ずっと凝視していたからだろう、アランもこちらに気づいた。
思わず踵を返して逃げようとした瞬間、ものすごいスピードで追いついてきたアランに腕を掴まれ、物陰に引きずって連れて行かれた。
「久しぶりじゃあないか、坊や。こんなところで会うなんて偶然に感謝しなくちゃな」
「あのあのあの、僕は何も見ていません!」
「何怯えている? あのログハウスでは食事も与えたし風呂もあっただろう。首輪をつけられている以外不自由はしなかったはずだ。私は紳士だったと思わないかね?」
その首輪が最も紳士らしくないものではないかと反論できず、涙目でこくりこくりと頷くと、アランはギーの胸元の匂いを嗅いだ。
「知らない香水だな」
「知り合いの調香師が調合してくれた香りです」
「薔薇の香りが随分強いな。他の香りはジャスミンと……うーん、わからん」
そう昔でない時期に自分を監禁した男に、胸元に鼻を押し付けられて匂いを嗅がれるというのがどんなに怖いかアランも体験してみればいいのに、と思う。アランは顔をあげるとギーににやりと笑いかけた。
「ギリシア時代、海からアフロデーテが誕生したとき、大地が負けじと美しいものを産みだしたとされているのが薔薇だ。ジャスミンはインドでは恋人から貰う愛の証とされている。両方とも香りに催淫作用があり、古来より閨に使われていた香りだ」
だからなんだ、と思った矢先、アランは低いくぐもった声で言った。
「誰を落とすためにつけている?」
「少なくともあなたではないですよ。僕は本当ただもらった香水を使わずにいるのは勿体無いと思ったから使っただけでして」
「そうかね? 坊やにはよく似合う香りだと思うよ」
アランはそう言うと体を離した。
「とはいえ、逃亡先でまた遭遇するとはびっくりだったな」
「ええ、本当世の中何があるかわかりませんね」
「警察に私のことを言ったりしたら、どうなるかわかっているだろうね? 地の果てまで追ったってお前に報復してやるからな」
「言いません、言いませんってば」
首を左右に振ると、アランはひとしきりギーをいじめたことに満足したようで、そのまま仕事場に戻っていった。
手首を見るとすごい握力で握られていたせいかうっ血している。アランは逃亡してきたと言ったが、パリでもやはり人を殺しているのだろうか。
(だとしたらなんだって言うんですか。あいつが人殺しだろうとなんだろうと、僕の身に直接被害がないならいいじゃあないですか)
そう開き直り、小走りにアランのいた裏庭から逃げた。