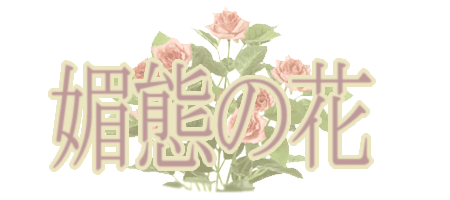
05/13
リビングでギーがアルバイトの求人雑誌を真剣に眺めていると、マリー・ルイーズが「もう仕事は決まったんじゃあないの?」と聞いてきた。
「決まったことは決まりましたが、パートタイムの収入だけじゃあ一人暮らしは難しいので、あともうひとつくらいアルバイトを見つけないと」
頭をがしがしと掻いて時間の融通のつきそうな仕事を考えるが、どの仕事もけっこう常勤に近い。大学の講師をしながらやるのには少し向かないような気がする。
「家庭教師のアルバイトとかどう?」
「は?」
「ボードレール家ってけっこう顔が広いのよ、お父さんのお陰なんだけれども。ちょうどパリに家庭教師を募集している家庭がふたつあるの。もしあなたがよければだけど、家庭教師ならば実入りもいいし、大学の講師の仕事といっしょにやっても差し支えがないんじゃあないかしら」
「助かります」
マリー・ルイーズは頬笑んで、そして真剣な顔をして言った。
「ギー、無理やり出て行こうなんて考えなくていいからね? 兄さんだって私だってあなたと仲好くしたいんだし」
「いえいえ、だとしてもずっとお世話になっているわけにはいきませんから」
彼女は少し残念そうな表情をして、リビングにある電話を手にとった。しばらく女同士らしい姦しい会話が聞こえたと思ったら、家庭教師の話になり、最後にお礼を言って電話を切る。
「OKみたいよ。住所教えるね」
メモ帳に住所を書いてくれた。ひとりはモンマルトル、もうひとりはレ・アール地区だ。
「とりあえず顔合わせだけして、やっていけそうか確認してきてくれる?」
「そんな問題児なんですか?」
「ギー、問題を抱えていない子供なんていないわよ? みんな多かれ少なかれ親の悩みの種なんだからね」
なるほど、違いない。レインマンだって昔は問題児だったのだ、マリー・ルイーズにしろ何か問題を抱えていたのだろう。
「それじゃ、がんばって行ってきてね」
ギーの頬に軽くキスをしてからマリー・ルイーズは庭に出て行った。
自室に鞄を取りに行く間に少し考える。自分はどんな子供だっただろうかと。とりたてて目立つ行動もしなかったが、大人しすぎるのが親の悩みの種だったかもしれない。友達と遊ぶよりも草花を育てるほうが楽しいと言ったときに親が変な顔をしたのを思い出し、少し苦笑いした。
「思い出し笑いですか?」
「うぉわ!?」
苦笑いした瞬間にレインマンに話しかけられて心臓が跳ね上がるかと思った。
「び、びっくりするじゃあないですか」
「廊下でひとりにやにやしている友達見たら突っ込むのが僕ですので。あと草花と語らうのも大切ですが、やはり友達も大切だと思いますよ? あと適度に遊び歩くことも」
「わかりましたよ、今日は遊んで帰ってきますから」
「門限は十時です」
「なんですかそれ、今日日高校生だってそんな門限守らないでしょうに」
呆れたように呟いて屋敷の外に出た。空が青く、いい天候だ。初夏を知らせる強い風が頬を撫でる。とても心地よい。
バスで五分、電車で四十分の距離を移動したあとは、坂やら階段の多い道を延々と登った。
道の途中では大道芸人が芸を披露していたり、画家が絵を並べていたりする。モンマルトルは昔から芸術家たちの集まりやすい村だ。ゴッホとロートレックが出会ったのもここだし、ドガが踊り子を描いていたのもここだ。そしてユトリロの愛した村ということも忘れてはならない。
モンマルトルという名の由来は二つある。ひとつは初代パリ司教聖ドニが殉教した地域という意味で「殉教者の丘(モンス・マルチルム)」が訛ったという説、そしてもうひとつはローマ神話のマルス神を祭った山、モンス・マルスからきたという説。
メモ帳の住所の家を見つけて、呼び鈴を鳴らした。しばらくしてそばかすの女の子が顔を出す。
「デュピュイトランさんのお宅ですか?」
「ええと、家庭教師の……?」
「はい。家庭教師のギー=ワロキエです」
「え、うそ。すごく格好いい! あがって。今珈琲入れるから」
ギーをリビングに迎えいれてから珈琲を入れつつ彼女は「あ、私オリアーヌ! よろしくね」と名乗った。
珈琲といっしょに出てきたローズマリーのクッキーを齧りながら、ギーは質問をした。
「オリアーヌは何の勉強をしたいんですか?」
「英語。まったくわかんなくて」
オリアーヌは肩をすくめて笑った。
「でもよかった。ねっとりしたハゲが家庭教師だったらどうしようかと思っていたの」
「あはは。ハゲていても教えるのが僕よりも上手かもしれませんよ?」
「私は教えるのが上手なハゲよりもあなたのほうがいいわ」
ぱちん、とウインクをされてギーは苦笑いをした。この歳の頃の女の子はませているとは聞くが、本当にそのとおりだ。
オリアーヌとしばらく会話をしたあと、次の家に移動する時間がきたので別れを告げて次のラミー家に移動した。
レ・アール地区はモンマルトルとは随分雰囲気が違う。モダンな建物とショッピングセンターが立ち並ぶ近代的な町並みだ。
ともかく人ごみが多いポンピドー・センターの前を横切り、マレ地区との中間にある家をやっとの思いで見つけて呼び鈴を鳴らす。しばらくして中から小太りなおばさんが顔を覗かせた。
「こんにちは。今日から家庭教師をやらせていただくギー=ワロキエです」
「ああ、ボードレールさんのところの? あがってくださいな」
おっとりとした口調でそう言うとギーを子供の部屋まで案内してくれた。
「ルノー、家庭教師の先生が来てくれましたよ」
部屋の扉をノックして、おばさんが扉を開ける。中に入った瞬間少しだけ息を呑んだ。壁一面にアニメのポスターが貼ってある。
(うわあ、すごいなあ……)
オタクへの偏見はないつもりだったが、実際にその実態を目の当たりにすると複雑な気分になる。
「あとでカフェオレをお持ちしますね。ルノー、ギー先生とお話をしていてちょうだい」
パタン、と扉が閉まる。
デスクの前にはやや小太りの、だけど利発そうな少年が座っていた。
「えっと……今日から家庭教師をすることになったギー=ワロキエです。ルノーくん、よろしく」
「この部屋の感想どう思った?」
「は? ええと、すごいコレクションだなあって。集めるの大変だったでしょう」
「馬鹿にしているくせに」
低くそう言うとルノーはくるりと背を向けてギーを無視した。居心地の悪さを感じながら、てきとうに部屋の隅にあった椅子を手にとって座る。
「僕も中学生の頃いっぱい部屋にポスター貼りましたよ?」
「どんなポスター?」
「お料理の作り方が書いてあるやつとか、好きなイラストレーターの絵画とか」
「それ女の子みたい」
「ええ、だから男の友達を部屋に入れるのは頑に拒否し続けました」
正直にそう言ってみる。ルノーはギーのほうをちらっと見て、ため息をついた。
「でも先生はきっと、女の子は部屋に入れたでしょう」
「そうですね。女の子のお友達のほうが多かったです」
「僕は男にも女にも気持ち悪いって言われるよ」
「そうなんですか?」
「気持ち悪いでしょう。こんなにいっぱい美少女アニメのポスター貼ってあるなんて」
ギーは改めて部屋の中を見渡す。たしかに女の子のイラストが多いかもしれない。
「僕はちょっと前まで犯罪心理学をやっていたんですけれどもね、真性の気持ち悪い人っていうのは、本当に手がつけられないことを学習しましたよ」
「それって僕のこと?」
「いいえ。僕の気持ち悪い人の定義は、『人間を見てもそれを物と同等かそれ以下にしか認識できない人』です。同じ人間だとしたらそんなことできない、と思うようなことを平気でする人たちですね」
ルノーは何を考えているのかわからない視線でギーを見つめた。
「それでもそんな僕に気持ち悪いと思われた人たちもですね、実際にお話をうかがう機会があったりすると、色々考えているんだなってことがわかるんですよ。身勝手でも、本人たちなりに考えたり、傷ついたり、しているんですよね」
「でもそいつら、みんな重罪人でしょう?」
「そうです。実際にやった行動は許されるものではありません。ただ僕は、そういう気持ち悪い人を研究するのを仕事にしようと思っていた気持ち悪い人ですので、ルノーのアニメが好きって気持ちなんて可愛いものだと思いますよ」
そう言われてルノーは警戒したように顎を引いた。
「どうせ、お世辞だよ」
「まあもうちょっとお付き合いしてみてから合わないと思ったらクビにしてくれて構わないので」
にっこりと頬笑みかけると、ルノーは引きつった笑いをした。
「帰って」
辛辣な一言にギーは苦笑いして、鞄を持つと「また来ますね」と言った。
部屋を出ると、カフェオレをふたつお盆に乗せた母親がいた。
「まだうまく打ち解けられないみたいです」
苦笑してそう言うと、ルノーの母親は笑って
「あの子の家庭教師は長続きしないので有名なんですよ。ちょっと神経質でしょう? あまり気を悪くなさらないでね」
と言った。
「いや、でも頭のよさそうな子でしたよ」
「頭はいいんだけれども、友達が出来ないんですよ。家族以外の誰とも会話しないのはよくないでしょう? ですから家庭教師ならば、せめて勉強の話くらいするかしらって思って」
「ははは」
ていのいい面倒見役を押し付けられたわけか、と思いながらルノーの母親と学校での彼の様子や成績などを聞きだした。
「ではまた、来週来ますので」
「よろしくお願いしますね」
ラミー家を出たときには既に夜になっていた。シャンティーは深夜まで三十分置きには電車が出ている。バスはないにしろ、歩けない距離ではない。
レインマンに夜遊びをしてくると宣言した手前、バーにでも寄って行こうかと思ったが、先ほどのルノーやその母親とのやりとりで精神的に相当疲れたらしく、今から遊ぶ余力などないな、と実感してそのまま大人しく駅へと向かった。
「おかえりなさい。夜遊びはしてこなかったんですね」
レインマンがにっこり笑ってそう言った。
「夕食まだでしょう。ちゃんととっておいてありますよ?」
「いえ、食欲がありません」
部屋に入るとばったりとベッドに倒れた。妙に疲れたみたいだ。後からレインマンが入ってきて、憔悴しきった様子のギーを見た。
「かなりネガティブなエネルギーをかぶってきたみたいですね」
「そうなのかな。ただ会話しただけなのに妙に疲れました」
「そういうのは僕よりもマリー・ルイーズのほうが得意なんですよ。ちょっと待っていてくださいね」
レインマンは扉を半分開けたまま姿を消した。しばらくしてマリー・ルイーズが小箱を持って入ってきた。
「ギー、兄さんから話を聞いたわよ。ラミー家のネガティブかぶったんだって?」
「そんな言い方をあの人はしたんですか?」
「息子さんよりお母さんのほうがヤバいってエミールは言ってたわね」
「見たこともない人をヤバい人扱いってエミールも失礼な人ですね。大丈夫です、少し休めば回復しますから」
「リフレッシュするいい方法知っているのよ。とりあえずこれ飲んで」
ペットボトルに入れられた琥珀色の液態を突き出されてギーは「何かの薬ですか?」と聞いた。
「エキナセア茶にセージとペパーミントとレモンバーベナをいれたものよ。心も体もしゃきっとしたいときはやっぱりこれ」
ペットボトルの蓋を開けて飲むと、ハーブティー特有の清涼感のある香りが冷たさとともに流れ込んできた。
「美味しいですね」
「でしょう? エキナセア茶はインディアンのハーブとも言われていてね、インフルエンザにさえ効くって言われているの。セージは神経のバランスを整えるのにとてもよくて、古くから……」
「――長生きしたい者は五月にセージを食べよ、と言われていますよね」
「なんだ知ってるんだ」
「ちょうど五月ですよね。コモに住んでいた頃、五月になると両親が僕にセージ茶を飲ませていつもそう言っていたんです」
懐かしむようにそう言うと、マリー・ルイーズは「ご両親は今もコモで暮らしているの?」と聞いてきた。
「いえ、両親は少し前に火事で亡くなりました」
「ごめんなさい。つい、知らなくて」
バツの悪そうなマリー・ルイーズに頬笑みかけて、ペットボトルをもう一度呷る。喉にひんやりと広がる香りが疲れをやさしく癒してくれる。
「ギー、服脱いでちょうだい」
「は?」
「オイルマッサージするのよ。ジュニパーベリーで体の疲れを全部とるの」
「いえ、いいですよ。自分でやりますから」
「四の五の言わないものよ。私のマッサージの腕は免許とっているくらいなんですからね!」
どう言ってもやる気のようなので、仕方なく上半身だけシャツを脱いだ。
マリー・ルイーズは手にオイルをつけると耳の裏から首、肩にかけてを丹念にマッサージしはじめた。
「ギーって全然筋肉ないよね」
「バレましたか?」
「兄さんより胸板薄い人初めて見たかも」
「見てのとおりモヤシですので、モテませんよ」
マリー・ルイーズと会話をするのは楽しい。しばらく歓談を楽しんでからシャワーを浴びたら、心も体も信じられないほどリフレッシュしていて、なんだか先ほどの疲れが嘘のようだった。
少し離れたところにあるレインマンの部屋をノックすると、彼の部屋は少しだけ暗くしてあり、アジアの音楽が流れていた。
「瞑想中でしたか。失礼しました」
「いえ、いいですよ。今日の分はこんなものなので。用事があって来たのでしょう?」
「ええ、まあ……やっぱりお腹が空いたので冷蔵庫のものを食べてもいいか許可を貰いに」
頭を掻いて笑うと、レインマンはくすくすと笑って胡坐を解くとキッチンまでいっしょに行き、冷蔵庫から鱈のオーブン蒸しと五穀米のリゾットを出した。
「レンジ借りていいですか?」
「どうぞ。ワインは何がいいですか?」
「てきとうに安いハウスワインでいいですよ」
ハウスワインといってもボードレール家で飲むものは質がいいことを知っていたのでそう言った。レンジの中からトマトとチーズの香りがぷんぷんしてくる。先ほどまで食欲がなかったのに今ではお腹が空いてたまらない。
「鱈に合わせてシャブリにしますか? それともリゾットに合わせてフィクサンにしますか?」
「二杯飲みます。各料理に合わせて」
「ギーくんはのんべえですね」
「なんですか、たった二杯でのんべえって」
レインマンがグラスを二つ取り出しているのでわざわざグラスをかえてくれるのかと思いきや、冷蔵庫の中からチーズも取り出した。
「僕もお腹空いたので」
「あなたこそのんべえじゃあないですか」
呆れたようにギーがそう言うと、料理の匂いに釣られたらしいマリー・ルイーズも顔を覗かせた。
「あ、ふたりで晩餐なんてずるい! 私のグラスも用意して」
結局この日も、三人で食卓を囲むことになった。