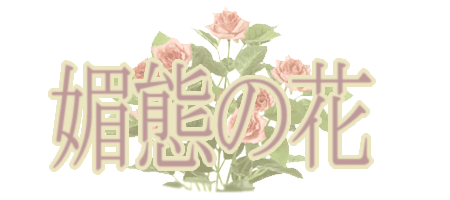
06/19
目が覚めたとき、いつもの豪奢なベッドではなく、普通の簡素なベッドだったこと、そしていつもと風景が違うことに、ギーは改めて引っ越したことを実感した。
「ギー、洗濯物干しておいて。あと郵便物届いたら受け取っておいて。夕飯の材料は私が買ってくるから、いっしょに作りましょう」
フランチェスカは早口にそう言うと大学へ行ってしまった。ギーは改めて、使用人のいない生活に戻ってきたことを知った。安心するような、面倒のような気持ちになる。
とりあえず言われたとおりに洗濯物を干して、郵便物がないか確認し、遅めのブランチをとってから家庭教師の仕事に出かけた。
ルノーはとても賢い。だから授業の間、ルノーは自習をしているに等しく、ギーにはほとんど質問をしない。
「先生、」
別に「先生と呼べ」と言ったわけではないが、彼もいちおう自分のことを先生と呼ぶ。
「なんですか?」
「先生には恋人ができたの?」
ふと、自分の左薬指に視線がいく。これのせいか。
「いえ、恋人を作りたくなかったので、先約がいるフリをしているだけです」
「ふーん」
ルノーはシュークリームのようにまんまるくふくれた顔でこちらを見て、言った。
「それ、外したほうがいいと思うよ。大切な人を逃すことになる」
「大切な人……ですか?」
「そんな人はいないと思っていてもね、ある日突然できたりするもんなんだよ」
恋の話に疎いルノーが真面目にそう言った。
「ルノーも好きな人ができたとか?」
からかい半分にそう言ってみると、彼は頬を染めて「僕のことはどうでもいいでしょ」と言った。ルノーも十五歳である。これからたくさん恋をする年頃だろう。
「大切な人を逃すことになる」とルノーは言った。その夜、ギーはその言葉を反芻していた。自分にとって大切な人って誰だろう、と。
マリー・ルイーズやレインマン、チェスターは大切な友達である。だけど自分にとって、そこまで重要な位置にいる人、というわけでもない。最終的に家族と同じくらい大切にできる人が誰かいるのかと考えたとき、そんな存在が今自分のところにひとりもいないことを知った。そして、そのかけがえのない存在を火事で失ったことも。
「ギー、鍋のパスタソース、もしかして作ってくれたの?」
部屋の扉が開いて、明日の朝食用にと作っておいたパスタソースについてフランチェスカが聞きに来た。
「ええ、朝から作るのが面倒だったので」
「たしかにね。味見したけどとても美味しかった……やだ、泣いていたの?」
ふと自分の目から涙が伝っていたことに気づき、ギーは目をこすった。
「ちょっとだけ、昔のことを思い出して」
「環境が変わってちょっとナーバスになっているのかしら」
「そんなんじゃあありません。ただ、フランチェスカといると、妙に懐かしさがこみ上げてきて」
何故そう感じるのかわからない。フランチェスカとギーは幼い頃は遊んでいたが、歳をとってからいっしょに暮らしたことはない。だけど彼女といっしょにいると、昔の思い出が、家族がいた頃のことが、思い出されるのだ。
「もう、僕の家族はいないんだって。ひとりぼっちなんだって思ったら……」
フランチェスカは優しくギーを抱きしめると、言った。
「私がいるのにひとりぼっちなんて言う口はこの口かな?」
軽く茶化すように言ったあと、真剣にギーを見つめてくる。
「私がギーの家族になってあげる。コモの私の両親もあなたの家族よ? 傷が癒えていないのはわかるけれども、いっしょに克服していこうね」
やさしい言葉だった。フランチェスカに会えてよかったと思った。