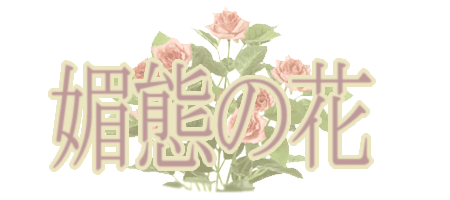
06/23
さて、猟奇殺人事件が起きた今となっては、まず確かめておかなければいけないことがある。それはアランが白か黒か、ということだ。
翌日はアランのアパルトメントを訪れた。彼が黒だった場合自分が殺される可能性も視野にいれたが、彼の自分に対する執着ぶりと、ギーが秘密を漏洩しないことを彼が知っていることから、たぶんそれはないと判断した。
アパルトメントの呼び鈴を押すと、彼はしばらくして顔を覗かせた。
「おや、坊やかい」
「こんにちは。お約束どおり遊びにきましたよ」
「日曜日だというのに、友達と遊んだり彼女とデートしたりはないのか。こんなおじさんのところに遊びにきて」
アランは苦笑いしてギーを中に招き入れた。
アランが紅茶を入れている間、部屋の中を見渡すとこの前のクロッキー画に油絵で着彩してあった。絵の中の自分は、まるでフェルメールの絵画のように澄んだ目をしている。彼には自分がこんな風に映っているのか、そんなことを考えた。
「お茶が入ったよ」
「ありがとうございます」
入れてもらった紅茶に一口だけ口をつける。自分から来たのだから、中に薬が入っていることはあえて想定にいれないことにした。
「何のためにここに来たのか当ててあげようか」
アランがにっこり笑って言った。
「昨日の猟奇殺人事件について、私が犯人か聞きにきたのだろう」
嘘をついて誤魔化すべきかどうか考えたが、結局そこに話題を持っていかなければならないので「そうです」と呟いた。
「結論から言うと、私は犯人ではない」
「何か根拠になるものってありますか?」
「そうだな。まず被害者が自分の好みじゃあないよ。たしか少女だっただろう? 私は子供を殺すのだけはどうしても苦手でねえ……大人ならば男でも女でも構わないのだけれども」
最後のあたりはそれもどうかと思ったが、子供は殺さないということはわかった。
「その答えを聞いたらもう帰るというわけではないだろう?」
「……他に何を話せというんですか?」
「今回の事件に対する坊やの見解を教えてもらいたいな。私の答えと照らし合わせてみたい」
ギーは紅茶を一啜りしてから、言った。
「ピッキュアリズム、サディズム、少女愛、性嗜好はこんなところです。悪魔崇拝のスタイルは実際の魔方陣を見たわけではないので判断できませんが、おそらくは自己流のものだと思っています。いちおう強姦殺人事件として警察は動いているようですが、少女を被害者に選んだこと、あまり痛めつけずに殺したこと、強姦としては未遂に終わっていることを考えると……犯行は人を殺すことに興味があったということでも、行為を強要しようとしたことにも属さず、なんらかの実験的儀式に殺人が必要だったと考えるのが普通の流れだと思います」
「犯人像は?」
「独身の男性、年齢は二〇〜四〇の間くらい。エディプスコンプレックスのある、秩序型の犯人。職業は専門職である可能性が高く、おそらくパリ市内に住んでいます」
アランはにこにこ笑いなが、言った。
「それで私が犯人かもしれないと坊やは思ったわけだね?」
「ええまあ……そうです」
「期待に添えないようで悪いが、私は犯人ではないよ。そして私の予想と君の予想が随分違うことにとても残念さを感じている」
「と、言いますと?」
「君はもっと殺人者の気持ちの分かる子だと思っていたよ。私が人を殺すのに快楽しか感じないように見えたかね? 人を殺すという昂揚感にあとにくるのはなんだと思う?」
「罪悪感? ……そんなわけありませんよね」
「そんなわけないな。感じるのは恐怖だよ。自分のやった行いに対しての社会からの報復へ恐怖を覚える。だから隠蔽しようとしたりするわけだろう?」
たしかにそのとおりだが。
ふいにアランは立ち上がると、ギーの隣にやってきた。
「まず先に言っておくが、私は君を傷つけるつもりはない」
何を言い出すのか、と思った瞬間、腕を掴まれて床に押し倒された。とっさのことで反応が遅れている間に近くにあった電気コードで腕を縛りあげられ、目と口を手で塞がれる。アランを蹴り上げて逃げようとしたら上手に脚の間に躰を割りいれて押さえつけられた。
心臓がばくばく鳴る。目隠しはそのまま、口を塞いでいた手を外し、その手がギーのシャツの釦に手をかけた。
「やめてください!」
「ほら。こういう風に両手両足の動きを奪われて、目隠しをされて、服に手をかけられたら君はどうする? 大声で叫ぶだろう」
アランは服にかけていた手を止めて、目隠しをしていた手を外すと縛っていたコードを解いてくれた。
「被害者が何故叫ばなかったのか、それが気にならないかね?」
「殺されたあとに脱がされたからですね」
「ということはネクロフィリアの可能性を視野に入れねばならないだろう。もちろん実験的な儀式という可能性も十分考えられるが」
アランは何事もなかったかのように椅子に着席した。
「坊や、いつまで床に転がっている気だね? 座って落ち着きなさい」
誰のせいで心臓がこんなに高鳴っているとおもっているのだろう。倒れた椅子を元に戻し、ギーも座って紅茶を飲んだ。
「どうもこの事件、解せんのだよ」
「どういうことですか?」
「色々詰まりすぎている気がしないか? 簡単にあげるだけでサディズム、ピッキュアリズム、ネクロフィリア、悪魔崇拝、少女愛があるのだよ。これから導き出される結論は?」
「変態の犯行ですよね」
「そのとおり。一般人も警察も性嗜好異常者の犯行だと思うだろう。だけど考えてみたまえ、君はアダルトビデオを借りるときになんとなく好みの女性というものがないかね?」
「借りたことがありません」
「君が不能者だとは知らなかった。失礼」
「違いますよ。健全ですけど興味がないだけです」
「興味がないというだけで不健全だ。ともかく、一般人にも自分の好みの性嗜好というものが存在するはずだ。同様に殺人者にも性嗜好のスタイルというものがあると思う。ところがどうだね、今回の事件。これでは棚に並んでいるアダルトビデオを全部借りているのと同じくらいすべてのジャンルが詰め込んである」
「つまりこれは、何かのカモフラージュではないかとアランは言いたいわけですね?」
「そのとおりだよ、坊や。これは性嗜好異常者の犯行ではない」
それがアランの結論か。たしかにギーの推論とは真っ向から反対だ。どちらが正しいというのは今の段階ではわからない。
「じゃあ……アランは誰が犯人だと思いますか?」
「さてね。そんなのは警察に任せておけばいい話だ。私が犯人でないことがわかればそれで問題はなかろう」
今の流れから考えると、アランは完璧に白と見ていいだろう。そのあと軽く世間話をしてから適度なところで切り上げてアパルトメントを後にした。