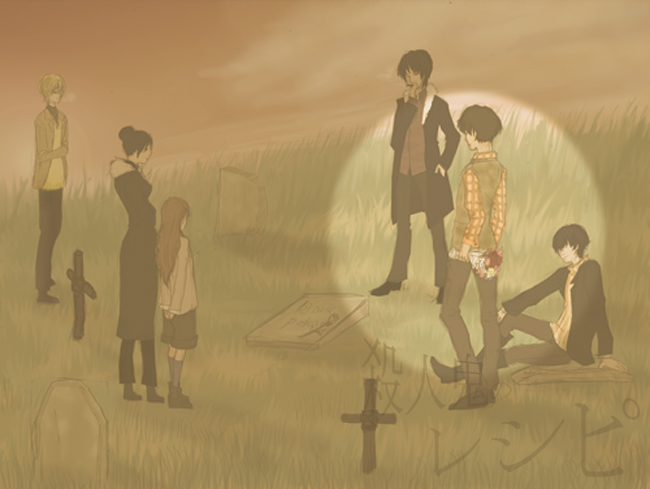
01 「箱庭の楽園」
今となって考えると、学んでいた学科も違ったのにどうして話す機会があったのだろう。
同じキャンパスの中を歩いているうちに、自然と目にとまった彼女は、男性のようなベリーショートの黒髪で、ぴっちりとしたスーツを着ていた。
最初に目をとられたのは猿鷲(エンジュ)のほうだった。
早足に歩いていく、メンズの香水をつけた彼女を目で追ってぼーっとしているものだから、狗琉(クリュウ)は笑った。
「今の人みたいなのが好みなのか?」
「いえ、そういうわけでは。綺麗な人だなって、つい。クリュウ、見ましたか? 今の方、どこかのモデルさんかと思いました。身長も僕と同じくらいありましたよ?」
「ハイヒールのせいだろう? ぼやっとしてないで帰るぞ」
クリュウの母親はマフィアのボスと結婚した。その男は女癖が悪く、他の女を妊娠させてしまい、クリュウは母親ともども家を追い出された。
クリュウの母親が死んでから、すぐに父親はエンジュを紹介してきた。一人で暮らさせるのはさすがに気がひけたということだろうか。
碌な勉強もしていないエンジュが読み書きくらいはできるようになるまで付き合っているうち、二人は無二の親友のようにいつも一緒に行動するようになった。
エンジュは少し翠のかかった艶やかな黒髪の持ち主で、自分よりもがっしりとした体型だった。十一歳で既に身長は一六〇あった。彼の身長はクリュウが大学に行くようになった十七歳の頃には一八〇をこえていた。東洋の人間としてはかなりの長身である。
しかし一八〇をこえたあたりで伸びは悪くなって、クリュウが大学を卒業する二十の頃には身長は同じくらいになっていた。
エンジュは経済の講義を聴いている最中、いつも欠伸をしている。
飛び級をしたクリュウについてきているだけなのだが、いちおう授業を受けているのだし、学費はきちんと二人分払ってある。
どうせだから聞いていればいいのに。そう思うクリュウの横でうとうととしながらも、それでも講義を受けているのだ。
その横に座っていた女がエンジュの首をいきなりひっぱたいたものだから、エンジュが涙目で叫びそうになりつつ飛び起きた。
彼が抗議しようとした瞬間、それが前に見たモデルのような女だと気づいて開きかけた口がぴたっと止まった。
「蚊がとまっていたの。伝染病怖いし」
眉を少しも動かさずに彼女はそう言った。
エンジュが首を押さえたまま呆気にとられている。
クリュウはこんな瞬間まで女に惚けられるこの男はマゾかもしれないと思った。
ふと彼女のつけている名札を見ると、K・イーリーと書かれていた。イーリー……ウナギか、自分の他にもかわった苗字の者はいるんだな。そんな理由で、偶然クリュウはその名前を覚えていた。
月日は流れて、クリュウ=ポスカトは大学院に進んだ。
街中を歩いていたときに、髪の少し伸びたK・イーリーが上司らしき男といっしょに歩いているのを見かけた。彼女の胸には真新しい弁護士バッヂが輝いていた。
(弁護士になったのか)
ポスカトで女性が男性の就くような高給取りの仕事に就けることは珍しい。
頭のよさそうな女性に見えたが、きっと優秀なのだろう。そんなことを考えながら、自分は市場で買ったハムと野菜の入った布袋を持ち直して主夫業のために家に帰る。
エンジュは煮物しか作れないのだ。美味しいものが食べたかったら自分で炊事をするしかない。
ポスカトという街について少し説明しておこう。テールで一番北にあるスノースタリン大陸の一番西、山あり谷ありのさらに先にある小さな街だ。
交通の便がよくなったとはいえ、こんな辺鄙なところがどうして栄えているのかといえば、タータ山脈の影響で温泉が湧いているからだ。人々のほとんどは温泉業と関りがあり、お湯は蛇口を捻ればどこでも出てくるが、逆に水はお金を払って買わなければいけない。
だいたいは温泉の水を湯冷ましにして、水は買わない人たちが多い。
テールで少し大きな集落に行けば当然、そこを牛耳っている組織がある。ここ、ポスカトで一番偉いのは温泉の権利をもっているポスカト家だ。ポスカト家はもともとはただの地主だったのだが、今ではマフィアとして扱われることが多い。
クリュウの父親にあたる狗零(クレイ)はこの十五代目のボスにあたる人物だ。
ポスカト人の大半は今では名前を共通語で書く。だからクリュウも自分の名前を「狗琉」と書くことはあまりない。画数が多いし、相手が読めない場合もあるからだ。
ポスカト家の大半は名前の一部に「狗」の文字が入っている。これは最初に愛犬が温泉を見つけたからとか、犬のように鼻が利くからとか、まことしやかに色々仮説があるが、初代が何を考えたかはともかく、今はただの風習のようなものだ。
この文字を名前に入れられるのはポスカト家の直系だけと決まっているため、クリュウはポスカトのどこに行っても、ポスカト方言で名前を書くとすぐにポスカト家の人間だとバレてしまう。
さて、実際にはポスカトマフィアの権力などまったく持っていないクリュウが持っている財産は、実は意外と多かった。
それは彼が数字にとても強いことが由来している。彼は株に投資し、稼いだお金で大学の費用を払い、生活していた。
クリュウはあまり権力志向があるほうではなかったし、お金に困ったこともなかった。 だから本来ならば、ポスカトマフィアのボスの座なんて誰がなってもよかったのだ。
クリュウが二十一歳になったとき、父親が死んだ。
ばりばりに働いていきなりある日脳卒中で倒れて、そのままぽっくりだったので、遺書も見つからない。
結局誰が相続するかで大揉めに揉め、裁判沙汰にまで発展した。
クリュウは特に交友関係が広いわけではない。味方といったらエンジュくらいだった。
「誰か腕のいい弁護士って知り合いにいましたっけ?」
別に自分がポスカトマフィアの頭目にならなくたって、食うには困らない。
しかしエンジュは自分に雇われているわけではなく、ポスカトマフィアの所有物だった。
自分の意志で雇われた者ならば自分の意志でやめることができるが、奴隷に人権という考えが存在するかと聞かれれば、少なくともポスカトでそういう考えは通用しない。
下男は下男、下女は下女。一生下働きをさせるだけの存在。結婚も働く場所も、主人の言うとおりにするというのが常識だった。
つまり、エンジュを法律上も人間として正当に扱うように書面を作るためには、まずクリュウがポスカトマフィアのボスになる必要があったのだ。
先に他の相続候補者が各弁護士事務所を押さえてしまっていたので、今から声をかけても徒労に終わるだけだと考えた。
しかし自分の法律の知識なんて大学の教養授業で受けた程度の内容しかない。専門書を読み込むにしたって腕のいい弁護士と争って勝てるような気はしなかった。
「腕がいいかどうかはわからないが……一人だけ知り合いはいる」
自分の考えている人が自分に協力してくれるかはわからなかったが、他を当たっても無駄ならば可能性の低さは一緒だ。
「どなたですか?」
エンジュがお向かいでお昼のサラダを食べながら聞いてきた。
「お前が気にしていたあの美人だよ」
ポスカトのどこにいるかということは、情報屋に金を握らせればわかった。今はツァイという男の事務所で働いているらしい。
しかしその事務所はもう別の男に押さえられているのを知っていたので、事務所に掛け合うのは難しい。駄目元で直接本人に相談してみることにした。
住んでいる場所は意外と近く、弁護士が住んでいる家といえばもっと小綺麗なのかと思いきや、普通のアパートだった。
夕方に訪ねてみたが留守にしていた。しばらく待ってみるが、一向に帰ってくる気配ではない。
「もう八時ですよ。出直しませんか? せめて夕食だけでもとってもう一度うかがうとか……」
たしかに少し腹が減った。もう一度訪問し直すほうがいいかもしれない。そう思って、ドアの前から立ち上がった時だった。階段を登ってくる足音にエンジュが反応する。
髪を高くひっつめた彼女――カエデ=イーリーが、階段を上ってきたところで足を止める。
冬は寒いし、夜は危ないこの街でかなり遅い帰宅である。
「あなたたち……」
そんな夜遅くに、自宅前で張られていたら誰でも警戒するだろう。慌ててエンジュが両手に何も持っていないことを証明する。
「あの、僕たち怪しいものじゃあないんです。ただ……」
「弁護士を探しているんだ。金は十二分に払う」
クリュウが単刀直入に切り出した話にカエデの形のよい眉がぴくりと跳ねた。
「いいよ。ちょっとここで話すのもなんだから、中で聞くことにするわ」
彼女は内容も聞かずに、最初にまずOKを出した。
部屋の中は酒瓶とビールの缶がごろごろと転がっていた。
居間のテーブルの上にあったゴミをざっと腕で払いのけてからカエデは座った。他の椅子を指し、
「てきとうに座って」
クリュウはてきとうに椅子を引っ張ってきて座ったが、エンジュの椅子はなかったので隣の部屋から座卓を持ってきて床で話を聞くことにした。
簡単にポスカトマフィアの上層部の説明と親族の説明、父親が三回結婚した話や、死んだ話などをした。
カエデも新聞を読んでいるようなので、このニュースは知っているという。ツーカーで話が流れていく中でエンジュだけが取り残されていた。
「つまりいくつにも派閥が分かれていてはこの勝負はつきにくい。この訴訟を起こした、父の補佐をしていた狼虎(ロウコ)という男が一番危険だ。あとはきっとその配下に回るんじゃあないかと考えている」
「あなたの仲間はエンジュ以外にはいないの?」
「わからない。親戚といえば、戸籍上私の義母にあたる三番目の後妻の梢(コズエ)さん……彼女は今回中立の立場に回るらしい。あとは二番目の後妻が産んだ弟がいるらしいが、こっちはどこに住んでいるかさえわからない」
「そう……」
「引き受けてくれるか?」
「そうね。私今日解雇されたばかりなの。だからあなたに雇われてもいいわ」
解雇された、という言葉にクリュウが反応した。
「どんな理由で解雇されたんだ?」
「上司がしつこく交際を迫ってきたのよ。ちょうど壁に貼り物していたから、画鋲を男のアレに刺してやったらそれが原因で破傷風になっちゃって、切断する羽目になっちゃったんだって」
えげつない内容にエンジュがうわっと顔をしかめた。
クリュウはたいして気にはしていないようで、
「それは災難だったな」
と言った。災難だったのはどっちなんだろうとエンジュが複雑そうな顔をしているのが目の端に映った。
時間はまったく無駄に使えない。
翌日はクリュウの自宅に全員集まってから会議がはじまった。
「ここ、お酒はないの?」
あたりを見渡すようにしてカエデが呟いたので、エンジュが慌ててワインを取りに行こうとしたが、クリュウが止める。
「仕事の間はやめよう。終わったら一番いいのを出す」
「そう、じゃあまずそっちに取り掛からないとね」
カエデはボールペンを口に咥えると、どこから取り寄せたらしい資料をあれこれと広げて説明をはじめた。
既に混乱しはじめたエンジュをクリュウはちらりと見る。
「お前に情報収集を任せる。行って来い」
「あ、はい。わかりました」
急いで靴を履くと出て行くエンジュを見送りながらカエデは手をひらひらと動かした。
「エンジュはいないほうがいいかもね」
「つまはじきにするのも可哀想だろう?」
もともとエンジュの問題で今こんなことをやっているのだ。当事者には当然いてもらわなければならない。
しかしエンジュは家を出て十五分、経つか経たないかの頃に戻ってきた。
振り返りもせずにクリュウは聞いた。
「随分と帰りが早いな。情報は集まったのか?」
「ええまあ、一応は」
カエデがエンジュをちらりと見てから、ふと顔をあげた。その反応を不思議に思ってクリュウも後ろを向くと、なぜか紙束をもったエンジュがいる。
「……随分と効率よく仕事してきたみたいじゃない?」
カエデが胡散臭そうなものを見るように言った。
「そこのところを右に曲がったところでよくわからない男の集団に囲まれて、もらいました」
「なんだ、怪文書か?」
「いえ……味方だと言っていました」
フローリングの床にあがってくるのにもエンジュは靴を脱ぐ。今では土足の習慣のほうが根強いポスカトで、律儀なものだ。
「正確にはロウコの敵というべきでしょうか」
「ロウコの?」
鸚鵡返しにカエデが問う。エンジュが頷いた。
「なんだかロウコがボスになられると困るらしいんです。一人は臭くて、一人はハゲてて、ひとりは老けていました」
悪臭、ハゲ、おじいちゃん。頭文字をとるとAHO。そんな考えが頭の中を通過していったが、黙っておく。
「どれが一番偉そうだった?」
まず誰がリーダーか知るべきだとカエデが質問すると、エンジュは少し首をひねり
「三人とも仲がよさそうでした。同僚というべきかな。でもそうですね、ちょっと歳のいってそうな方が指揮っていたような気もします」
おじいちゃんが司令官。そんなことをクリュウは考えた。
カエデとクリュウに紙束を渡しながら、エンジュは補足説明に入った。
「その老け面がクリュウの義理の弟を知っているらしいです」
資料に目を通すのはカエデに任せて、クリュウはエンジュのほうを向き直った。
「……弟のことを?」
「ええ。見たのは何年も前だそうですが、内気な大人しい子だったみたいですよ。名前はビョークというそうです。猫に狗と書いて、ビョーク。クレイさんがクリュウにつけた名前と同じ狗の字です」
なるほど、狗の字が入っているということは間違いなくポスカト家の血族なのだろう。
エンジュは続けた。
「今はアキエというひとつ年上の青年と暮らしているらしいです。ビョークのほうの消息はさっぱりですが、このアキエという人物は今、外語大学に通っているそうです。すごくたくさんの女の人と遊んでいるらしく、外国語にはすごく詳しいとかで、あとヘサの訛りがあるとかないとか……僕言語に詳しくないからわかんないんですけど」
監獄都市、ヘサの名前が出てきてクリュウは首を捻る。ヘサは世界中の犯罪者たちを管理している大きな監獄だ。あそこは貧富の差が激しい都市だから、アキエは何か事情があってこちらに来ているということかもしれない。
「まぁいい、続けてくれ」
「でも筆記の日だけ彼の行動がおかしいらしいんです。まず喋らないそうで、あと女性を邪険にするそうです」
「たとえば?」
マーカーでアンダーラインをひきながらカエデが口をはさむ。
「毎日話していた女性がその日も講義の合間にアキエと話をしたら、てきとうに頷くだけで全然話を聞いている風ではない……怒った彼女が『なんとか言ったらどう?』と聞いたところ、訛りのないきれいなメカポリス語で一言、『死ね』と言われたそうです」
「なんだそれは」
怪訝に眉をひそめるクリュウにエンジュは続けた。
「あとこっちは単語でなく、ちゃんとした会話なんですけど……ショックだったから覚えていると言っていました。アキエに『結婚したいな』と言った方がいたらしいんです。『アキエはどう思う?』と聞いたらにっこり笑って『結婚してもいいよ。それってその気になれば合法的に強姦できる女を一人確保したっていうだけであって、別に俺がてめぇに束縛されるわけじゃねぇしな』と答えたらしいです。他にも衝撃的な名言の数々がありますが……」
「いや、もういい」
頭を抱えてクリュウが手で制した。
「弟の力は借りないことにする」
「そうですか。まぁ参考までに、クレイさんが亡くなられてからアキエは休学届を出しています。アキエは僕と同じく、ポスカトマフィアの“所有物”ですから、もしかしたらなんか命令がでたのかもしれませんね」
「それはないだろう。まだポスカトの頭は決まっていない」
ポスカトマフィアには上下関係があまりない。一番偉いボスがいて、あとはみんな同じようなものだ。そこに若干の年齢差や経験はあったとしても、それ以上でもそれ以下でもないのだ。
「じゃあもしかしたらビョークがアキエのために休学届を出したってことは考えられませんか? どこか事件に巻き込まれない場所に避難したとか」
「先ほどの話を聞いている限りじゃ、アキエという男はそんな守るべき人格でもなさそうだが?」
「それがですね、老け面の人曰く、『この筆記の日にきている人物こそ、ビョークなのではないか』だそうです。アキエとビョークは、理由はわかりませんが、同じ顔をしているらしいんです」
「……おもしろいな」
「おもしろいですよね」
二人で言ってみたが、とりわけ面白いかと聞かれたら、そうでもなかった。
そこでカエデが紙束に目を通し終わったらしく、紙にメモらしきものを走り書きした。それをエンジュに渡し、
「そのままもらった証拠を使うなんて危ない真似できないわ。この内容、確かかどうか幾つか調べてきてもらいたいの」
「あ、はい。わかりました」
エンジュは靴を履くと玄関の扉を蹴っ飛ばして出て行った。
◆◇◆◇
アパートの扉を開けっ放しにしたまま、エンジュはやや急ぎながらメモをチェックした。
カエデの文字でやって欲しいことが色々と書いてある。それをポケットに入れて、少しスピードを落として歩き出した。
そのとき、今度は最初の角を右に曲がる直前に、細道から手が伸びてきた。
反射的にそれをよけたが、それだけでなく嫌な予感がしてしゃがむと、何か高速で頭の上を掠めていくような気がした。
「あれー、避けられた?」
暗い細道から銃身の鉄色が光った。
背を向けて逃げたところで後ろから撃たれるのが関の山である。家の中に逃げ込めば別だが、それではクリュウとカエデが危ない。
エンジュはそのまま銃を持った人物へと距離を詰めて、掌を胴に繰り出した。その先があたるかあたらないかの寸前に、男は後ろへと飛んで距離をとり、着地すると同時にハイキックがエンジュの首あたりに飛んでくる。今度はエンジュがバックステップで後ろに逃れた。後ろに下がった瞬間、どん、と誰かの肩にぶつかる。
「よーし、ビョーク、そこまでだ」
背後の男が銃を持った青年をビョークと呼んだ。
エンジュの肩を馴れ馴れしく掴む男の顔も前方の男の顔も、同じ造りだった。どちらも身長は自分よりも低く、肩幅も自分よりない若い。
しかしその瞬発力と、否応なしに掴まれて放さない腕力はどこから生まれてくるのだろう。自分だってマフィアの仕事に従事し始めた頃から、訓練を怠ってなどいないのに。
エンジュの顔を検分しながらアキエと呼ばれた男が言った。
「若ハゲって聞いたけど、この頭カツラか?」
ぐっ、と頭皮をひっぱられる。
「やー違うっしょ。俺は臭いって聞いたけど」
くん、と鼻を鳴らしてビョークがかぶりを振る。
「間違えたのかな?」
「こっちに行ったって聞いたのに、ガセかよ」
エンジュを挟んで、ふたりの青年はそんな話をしている。
先ほど自分に資料を渡していった男達の話をしているのだろう。ふと自分がポケットに突っ込みかけていたメモが地面に落ちる。それをビョークが拾うと目を通して笑った。
「お前の知っていること全部話してみ?」
「俺たち年頃でちょっと遊び足りねぇんだ」
背後の男も声をはずませつつそう言った。生きて帰られるんだろうか、エンジュは息を呑む。
◆◇◆◇
三日経っても、一週間経とうとした今でも、エンジュは帰ってこない。
クリュウは内心苛ついていた。しかし公判をむかえる前に無駄なプレッシャーをカエデに与えるわけにはいかないので表面的には静かである。
酒瓶を持ち上げてカエデが呟いた。
「……二十年。自分とほとんど歳のかわらない酒なんて持っているんだ」
「それはエンジュと同い年の酒だ」
「そして私たちが大学を卒業した歳でもあるわけか」
荒削りの氷にウイスキーを入れたグラスを小突き合わせ、二人は一気に酒を嚥下した。
ふぅ、と息をつく。
「……明日が公判だな」
「エンジュ帰ってこなかったわね」
「証拠品の確実性に欠けているが……そのまま使うしかないな」
その言葉に反応するように、カエデがクリュウに向かってグラスを投げつけた。
クリュウは避けたが、後ろののほうで硝子が飛び散った音がする。
苛ついているのはカエデもいっしょなのだ。
肩で息をするようにして、カエデが訊いてきた。
「ずっといっしょに暮らしていたんでしょう? エンジュが心配じゃあないの?」
「心配だよ。だが――」
「明日の公判のほうが心配だって言いたいの?」
突き刺さるような言葉にクリュウはどう答えようか少し躊躇して、そのまま素直に言うことにした。
「君が心配だ」
「私の心配なんてしなくたっていいわ! 今までだって男と対等に渡り合ってきたんだもの」
「無理してないかって、それだけだ。怒ることはないだろう?」
クリュウは肩を竦めて続けた。
「エンジュのことだが、別に君が仕事を頼んだから失踪したわけじゃあない。あいつはあれでいて、すごく反射神経がいいんだ。ロウコ側の人間であいつを捕まえたりできる奴はいないさ」
カエデは黙って玄関のほうに歩いていった。
「ついてこないで」
まさか明日に裁判を控えて、エンジュを探しに行くほどカエデは馬鹿じゃあないだろう。
そうわかっていたので、クリュウはカエデが泣きにいくのだろうと思って、ほうっておくことにした。
◆◇◆◇
「うっ……」
玄関から出てすぐのところで、カエデは口元に手をあてた。
こんなに高精度な酒を飲んだのは、たぶん生まれて初めてだろう。
このレベルの酒を惜しげもなく振舞えるこのクリュウという男は、既にマフィアのボスなどにならなくても、十分に暮らしていくだけの力がある。
どうしてこの裁判に勝ちたいのかと聞いた時、クリュウは「失いたくないから」と答えた。
失うもの……これだけのものを持っている者が失うのを恐れるもの。
この暮らしを捨てたくないのかと聞かれれば、そんなことではないことは、この一週間共に暮らしていればわかった。クリュウは金はゲームぐらいにしか思っていない。失ったところで「そういうこともある」程度でとぼけてしまいそうだ。また稼げばいいと、言うのだろう。
また新しく手に入れればいい、それでは済まないもの。彼が恐れているのはエンジュの喪失だ。
「自分の不注意で……」
カエデは低く呟いた。だがエンジュを今探しにいくわけにはいかなかった。
もしエンジュがロウコ側によって連れ去られたのだとしたら、なおさらここで自分までもがいなくなるわけにはいかない。そうしたら本当にクリュウはひとりきりで戦わなければならなくなるからだ。
だが自分がいることが本当にメリットになるのだろうか。クリュウを瞞(だま)しつづけているこの自分が。
このまま失踪してしまいたい気分になったところを本当に手伝ってくれる二人組が現れることになるとはカエデは思ってもいなかった。
カエデが部屋に戻ろうと背を向けた瞬間だった。うしろのほうから男の手に口を封がれ傍道のほうへと連れ去られた。
壁に一度強く押し付けられて、声をあげようとしたところで今度は違う男が口を封いだ。
女の手かと思うほどやわらかな手だ。しかしその手の主の目はぎらぎらとどぎつく赫(かがや)いていて、カエデは黙った。
「お前が声を出そうとするかどうか、隣のこいつにはわかる。わかった瞬間にお前を殺すからそのつもりでね。オッケー?」
声を封じたまま、男が念を押す。カエデは一度、肯定いた。
口を解放されて深く呼吸をした。小さな声で訊く。
「あなた達……ロウコの手先?」
ザクッ、と耳すれすれの壁にナイフがめりこむのを目の当たりにしてカエデが息を呑む。
隣の男がそうするのを見透かしたかのように話していた男は続けた。
「俺言ったよね? 声だすと殺されるよって。でもまぁ俺たちはロウコの手先じゃあないんで」
「俺たちの正体は都合よく忘れておけよ。なぁビョーク?」
「名前を呼ぶな、馬鹿」
爛々とした紫の目と昏い紫の目の二人が目を見合わせた。
一見したときにはこの喋っている男のほうがヤバそうだと思ったが、もしかしたら本当に危ないのは隣の男なのかもしれない。
ビョークと呼ばれたこの男……本当にビョークという名前だとしたら、クリュウの義弟だ。
たしかに歳の頃も髪や目の色もあっている。しかしこんな場でわざとらしく自分の名前を呼ばれてそれに呼応する、その態度そのものがあざとい。
おそらく本物のビョークに濡れ衣を着せるか、それでなかったらとりあえずその場を凌ぐための偽名に実在する人物の名前を使った……そんなところだろう。
それにしてもここは血腥(ちなまぐさ)い。何がこんなに臭っているのだろう、と隣を見ればそこにはひとつの死体が転がっている。
「あ、それリハーサル」
「うろちょろされちゃお話するのに目ざわりでしょう? こいつがロウコの手先」
リハーサルと言ったのは隣の男、淡々と話しているのはビョークのほうだ。
ビョークは隣の男を顎でしゃくって言った。
「でもその死体は俺が殺ったけど、こっちの馬鹿はそんな楽に死なせちゃくれないから気をつけてね。そんなこんなでほんだーい」
やっと本題に入った。ビョークがかったるそうに話し始める。
「俺たちさー、ここ最近ストーカーにあって困ってたわけよ。そんで邪魔だから殺そうと思って、そいつらのことを調べているうちにポスカトマフィア遺産相続訴訟に巻き込まれたことに気づいてね、あんたらのこととかもついでに調べちゃってさー、カエデのことも勝手に調べたわけよ。そしたらあんたが最初に言ってたらしい『破傷風で男のアレ切断になっちゃった』ってやつ? そんな奴誰もいねぇじゃん」
「――!?」
「心音が高なってまた正常に戻っていったな。図星ってところか?」
まるで心臓の音を聞いているかのようにもう一人の若い男が言った。それにビョークが頷いて、続ける。
「まぁそれで俺たち、もしかしてって思ったわけだけどさー、まさかカエデ、クリュウの依頼を引き受けたふりして既にツァイの事務所が引き受けたロウコの依頼のお手伝いしていたり? 味方のはずの弁護士が負けるつもりでいるなんて普通思わねぇよな?」
「これは由々しき裏切り行為ですねー? ビョーク先生」
「だーかーら……俺の名前を呼ぶな、アキエ」
隣の男の名前はやっぱりアキエでいいようだ。
カエデの勤めているツァイの事務所は既にロウコの弁護を請け負っていた。だから本来ならばカエデは敵側のはずだったのだ。
しかし何がなんでも勝っておきたいロウコ側の提案を受けて、ツァイがたまたま同じ大学を同期で二年飛び級して卒業したカエデに、「クリュウになんらかのアプローチをかけて向こうの代理人になって、うまく負けろ」と命令したわけである。
ポスカトで女を雇用してくれる場所は少ない。女が大学を出るのも教養とハクをつけるようなものだ。
そんな環境の中で雇用主からの命令は絶対であり、逆らうことはそのままクビを意味している。次に雇ってくれる場所を探すのは難しい。カエデは渋々承知した。
とはいえ、女の弁護士を代理人にしてくれる依頼人なんてまだ少ない。
どうしようかと思いながら自宅へ帰ってきたらなぜか噂のクリュウがいるじゃあないか。しかも向こうから自分にアプローチがかかった。
カエデはこんなにもうまく話が運んでいいのだろうかと思いながらも引き受けたのだ。
アキエが話題を戻した。
「まぁそんなこんなで……俺たちの目的なんだけど」
「俺たちはただクリュウががっかりするのを見たいだけなわけ」
「そんで今そっちのエンジュがいないだろ? これでカエデまで居なくなったらあいつ孤立無援で明日の法廷だなー……ってのを最初考えたんだけど、これ没」
「あいつ隠し事されんのが一番嫌いらしいのよ。潔癖主義っていうかきれい好きっていうかさー」
「だから次に考えたのがこのまま明日からの訴訟で負けてもらうってことだ」
「結局お前がやっている行為に勝ることは思いつかなかったわけ」
この双生児のような二人が交互に言う言葉を聞いて、自分がいかにクリュウを裏切りつづけてきたかがわかった。
「結局お前がやっている行為に勝ることは思いつかなかった」という言葉が脳に黴のようにこびりつく。
まだ言い足りないのかビョークがポケットを漁りながら続けた。
「でもさー、お前が万が一にでも勝とうなんて気ぃおこされちゃ困るからさぁ……はい」
そうしてカエデの手に握らされたもの、それは紙だった。メモ帳のような切れ端だ。エンジュに自分が手渡したものだった。
「何なのかわかったみたいだぜ?」
「あのエンジュって男、あまりお前の好みじゃなかったろ。生かしてあんだろーな?」
「顔がなー、尻のさわり心地はよかったんだけどな…」
「そこじゃねーよ。生かしてあんのか?」
「……まぁ適度にいたぶって生かしてある」
「聞いたとおりだ」
最後の言葉はカエデのほうに振られたものだった。ビョークが優婉と微笑む。
「つまり俺はこう言えばいいの? エンジュの命は俺たちが預かった。生きたまま返してほしけりゃ言うこと聞けってさ」
「遅かったな」
部屋に戻ると既に硝子は片付けてあった。 テーブルの上には新しいグラスに琥珀色の液態が入っている。
カエデが手にとると、クリュウは小さく「今度は投げるなよ」と言った。
一気にそれを呷っても、まったく酔えなかった。もとから酔えないのだ。酔って忘れたいことがあると強いものをどれだけでも飲むが、まったく忘れられない。現実はいつもすぐ隣にある。カエデは呟いた。
「……なんで女に生まれてきたのかしらね」
「女性では不満か?」
「男に生まれてきたらこんなに苦しまなかっただろうなって」
「男に生まれてきた者の中にはまた女に生まれたかった奴もいるかもしれないがな……たしかにポスカトで女性の社会的な立場はまだ弱い。ジオのように女の姓を子供が継ぐようにすれば少しは変わるかもしれないが」
女は自分の生んだ子供を自分の子供と認めないわけにはいかない。
男の姓を受け継ぐ制度だからこそ男は自分の子供が誰で、誰が長男なのかを知る必要があるのだ。
クリュウは続けた。
「残念なことだがカエデ、女性の性を売り物にしている商売が一番女性の社会的立場をあげることに一株買っている。昔男の所有物だった女性が、自分は自分のものになったわけだ。もっとも……セーレ貴族の夫人になりたかったと売春婦たちは言うかもしれないが」
そこで一呼吸おいて、クリュウは言った。
「今の君たちのありかたに未来の双肩がかかっていると考えるならば、それだけでも胸を張っていいんだ。カエデの生き方だって、私の母親だって。私たち男は自分の性別について疑う余地もなく毎日働きどおしだ。自分の存在理由なんて考えたこともない男が大半だろうさ」
現代史と地域の勉強をしたときに、クレイが三度結婚したことは知っていた。
家族は知らない義理の母と弟だけだと言っていたクリュウの、本当の母親はどんな人物かはわからないが、病死したそうだ。
クリュウは最後に「それがたまに羨ましい」と笑った。
この男を敗訴させることが自分の社会的に生き残る道だと思っていたが、そんなことは既にどうでもよかった。
この男が大切に思っている家族を取り返すためならば、敗訴だろうと勝訴だろうとなんでも奪い取ってやるとカエデは決めたのだ。
翌日の天気は雨だった。エンジュは寒い思いをしてないだろうかとカエデは心配になる。
一刻も早く負ける必要があるが、クリュウに不自然に思われてはいけない。
法廷に向かう道で向こう側からツァイとロウコが歩いてきた。黒髪に黒目、どこにでもいるポスカト特有の黄色人種である。
少し歳のいった、いかにも一流の地位といった身なりの男だ。
「ドレスアルカロイドのスーツとは随分と値の張るものを着ているな。クリュウ」
「そちらの型は見ないものですね」
「オートクチュールだからな」
クリュウとロウコがそんな会話を交わした。別に自慢したいわけでも相手の服をけなしたいわけでもない。ただお互いの正装に対しての感想だ。
ツァイがカエデの隣にきた。ツァイは小男で、カエデやクリュウと身長差がある。
「カエデ、今日はめずらしくタイトか?」
「……新調してくださった方がいたので」
「ああ。クリュウ、お前が買ってやったんだろう」
ロウコが揶揄するように言った。
タイトスカートからのびるバックシームのはいったストッキングの脚線を眺めるロウコの間に割り込むように立って、クリュウはしれっと言った。
「就職祝いです。働くとなるとスーツがいりますから」
「お前が新しいエンプロイヤーというわけだ」
「そうです」
「まあお前ぐらい投資で荒稼ぎしていれば、一人二人雇っていても平気で食わせていけるんだろうな。若いってのに生意気だねー、お前は失敗したこととかないんだろう?」
「ありますよ、少しならば」
「少しか……」
貯金するという感覚さえ生まれないくらい稼ぐのは楽だとクリュウは話していた。カエデがまだ見習いで、仕事がもらえないうちから、あちらは贅沢三昧だったようだ。
ふとロウコは周囲を見渡した。
「あの普段ついてまわっている従者はどうした?」
従者とはたぶんエンジュのことを言っているのだろう。クリュウはエンジュが誰に攫われたのか知らない。もしかしたらロウコが攫ったと思っているかもしれない。
「小用を頼んでいまして」
「そうか。クリュウ、お前もしかしてあいつがマフィアの所有物だからその所有権を手に入れたくて闘うって言うんじゃあないだろうな?」
今回の目的はほとんどエンジュのためと言ってもいい。ロウコは続けた。
「くれてやるよ、あんなものでお前が退いてくれるんだったらな」
“あんなもの”と言われてもクリュウは別段動じた様子は見られなかった。
「正直お前は失うものも少ないだろうが、私は部下もたくさん抱えているもんだからな。この訴訟が長引くと回収の目処やその間の時間の損失が惜しいんだ。お前が辞退してくれるならば示談が成立する。そうだろう? そっちのカエデが優秀なのもツァイから聞いている。示談になればお互い悪いようにはならないさ」
「……たしかにそのとおりかもしれませんね」
クリュウは呟いた。示談になるとしたらどうなるのだろう、エンジュは敗訴しないと返ってこないというのに。
「しかしマフィアがこれからもそうやって生きた人をトレードしていくのだとしたら、その楔をはなつことができるのは私しかいないでしょう」
「回収の目処はあるのか? 投資家さん」
「いえ、まったく」
そこでロウコは沈黙し、「あーもう、これだから若造は……」と頭を掻いて参った、と笑った。
「じゃ、法廷でな」
ロウコはツァイを顎でしゃくってから法廷の中へと入っていく。
ロウコは特に感じの悪い男というわけでもなく、ボスになれば案外うまくまとめていったりするのではなかろうかとカエデは感じた。むしろこのクリュウの性格のほうこそ投資家や、ましてやマフィアのボスには向いていない。
クリュウは肩を竦めた。
「一見馬鹿げた投資も嫌いじゃあない」
「……クリュウ。聞くけれど、エンジュの無事と奴隷制の解放、あなただったらどっちをとるの?」
「考えたこともなかったが聞くまでもないだろう、エンジュの無事だ。言っただろう? 男は自分の選択したことの『本当の理由』なんて考えないと。つまるところ男はほしいものを手に入れていこうとした結果自分たちの社会的地位を危ぶまれているわけだ。女性にとってこれはチャンスだぞ?」
わかりにくかったが、最後のはクリュウの冗談のようなものだ。
自分のほしいもののためには今ある地位も財産も何も顧みないからこそ、この投資家は成功してきたのかもしれない。
クリュウは微笑んだ。
「さて、行こうか」
「行きましょう」
いざ、負けに――
長引くと社会的に見てポスカトの景気が一気に低迷するのはわかっている。
だからこそ判決はきっかり一ヶ月で出すというのは事前の打ち合わせで決まっていた。
カエデは負けるのを結論にして闘っていたので、まったくもって予定通りに進んだ。
クリュウに怪しまれることも判事に怪しまれることもなかった。そういう意味ではカエデは優秀な弁護士だったのだ。
判決は言うまでもなく負けだった。
閉廷の合図が鳴ってもクリュウとカエデは暫く法廷に残った。
「エンジュはどうしているんだろうな……」
ぼそっとクリュウが呟いた。
この一ヶ月ずっと心配してきたことだろう。 審議の結果なんかよりもクリュウはそっちのほうが心配だったはずなのだ。だがこの一ヶ月、二人の間にエンジュの名前は一回ものぼらなかった。
「きっと無事だから」
約束どおりにエンジュが返ってくるかどうかなんてことはわからなかったが、もう死んでいるかもしれないなんて言えるわけもなかった。
法廷の入り口ではツァイがいた。切れ長なつり目の男が待っていたよと言わんばかりに言った。
「おわりだ、帰るぞイーリー」
「……なんのことだ?」
クリュウがツァイに聞き返す。ツァイは長身のクリュウを見上げると言った。
「イーリーはうちの部下だからね。訴訟はおわった、返してもらう」
「そちらにはもう解雇されたんだろう? 私の部下を貸してほしいと言うのならば、こちらはそちらのように人の貸し借りはしない主義なのでね。本人の意思で行くというなら別だが」
「解雇したふりをしただけだ。こっちの勝訴のためにな。イーリー、お前から説明するか?」
振られてカエデは黙りこくった。その様子でクリュウはなんとなく察しがついたのだろう。少しだけ顔が翳った。ツァイが提言する。
「そちらの言うとおり本人に決めさせようじゃあないか」
このままクリュウといっしょに仕事をしていけたらどんなに楽だろうかと思ったが、ここまで暴露された手前、クリュウといっしょに行動するというのは無理な話だった。
先に歩き始めたカエデの後ろに残されたクリュウ。ツァイが去り際に彼にこう言った。
「茶番はおしまいだ」
それで終わるはずだった。
しかし茶番はおわらなかった。
「茶番はおしまいだぜー? カエデ」
へらへらとしたひょうきんな声が聞こえた。この声はアキエのほうだろうか、向こうから見覚えのある双子が歩いてくる。
この前とは違ってアキエらしきほうはブルゾンを着て、ビョークのほうはロングジャケットである。その後方からはエンジュの姿も見えた。
ツァイを挟むようにしてビョークとアキエは立ち、そして背後のエンジュを振り返って言った。
「ほら、約束。エンジュは返してやるよ」
「誰だ? お前たち」
訝しむようにツァイが呟く。ぎらぎらとした目の青年が答えた。
「俺たちのこと? ビョークとアキエだよ」
まるでもう世界を“俺たち”と“その他”にへだてたような口ぶりだった。二人にとって大切なのはいかに自分達が愉しいかだけであって、あとはどうでもいいのだ。
ツァイのことはとりあえず相手にしないことにしたらしく、二人はクリュウのほうに説明した。
「カエデは俺たちにエンジュを人質にとられていたんだよ」
「要求は簡単、敗訴だ」
「恐い顔しなくてもこのとおりエンジュは無傷ー」
「エンジュを返した今、別にこのチビに付き合う必要なんてねぇぞ。カエデ」
口々に話すものだから、服装が同じだったらどっちがどっちだかきっとわからなくなるだろう。
ツァイが激昂した。
「馬鹿なことを! イーリーは私の事務所から貸しただ――」
何か話そうとした瞬間に素早くアキエとビョークが同じタイミングでツァイの口を封いだ。
「しーっ、しゃべると殺しちゃうよ?」
「でもしゃべらなくても死んでもらうけどね?」
そうしてカエデとクリュウのほうを向く。
「ほら行けよ、ぼさっとすんな」
「お二人とも、おつかれさーん」
へらへらと笑うふたりがそう言った。
クリュウが自分のところまで歩いてくるとそのまま背中を押して、ツァイやビョークたちの間を通り抜けた。
エンジュとすれ違う時だけ、
「茶番につき合わされたお礼にそいつがどうなったか見といて、あとで教えてくれ」
「あ、はい」
クリュウに背中を押されて、カエデは歩き出す。
「私、あなたに謝らなきゃ」
カエデの言葉に、クリュウは少し頬笑み、
「その謝罪は受け取っておこう。仕事で挽回してもらうからな?」
と言った。心の中で何かが氷解していくような気持ちだった。
◆◇◆◇
クリュウとカエデがいなくなったあとにツァイの口を封いだままビョークとアキエは論じはじめた。
「やっぱここは殺して皮を剥ぐだろ?」
「皮剥いで殺すのほうがよくね?」
「皮剥いで生かすとか」
「ばーか、死ぬよ。普通死ぬって」
「あのう……」
なんだか生きたまま皮を剥がすとか言っている二人にエンジュがおずおずと進言した。
「せっかくだからカエデさんが言ってたあれを実行するとかどうでしょう?」
ビョークが振り返る。
「何? あれって」
「画鋲……」
ぼそっと呟いたエンジュの恐ろしい発言に二人の顔がいっしょににやつく。
「錆びた画鋲さがせ、画鋲」
「釘でもいいんじゃね? 螺子でもいいよ」
「うちこむってか?」
「ねじこむでも可」
そうして茶番劇は長々と延長戦にもつれこむのであった。
クリュウのアパートはそれなりの広さがあったはずだ。しかしそこは今は未曽有の巣窟と化していた。
クリュウとエンジュは最初から住んでいたとして、まずビョークとアキエ、それに新しく加わった臭いのとハゲたのと老けたの……トキとスオウとヒビキが加わったわけだ。
唯一の紅一点カエデが不在のため男所帯と化している。
「なぁ……ここ酒しかねぇんだけど、珈琲ないわけ?」
「おい、臭いやつが一人いるぞ」
「臭くねぇよ! 匂いたつようなフローラルのかおりだよ」
「臭いたつってのはあっているんじゃないか?」
「臭っているよな」
「珈琲……」
もう好き好きに話している男どもの横で、クリュウとエンジュが真剣に不動産物件を見ている。
「やっぱりそれなりの広さが必要ですよね、この人数だと……」
「最低八人収納できて、あと集まる部屋が必要だな」
「このまま七人が同じ部屋で暮らすのには耐えられませんからね」
カエデのために一部屋使うと、あとに残る男七人はひとつの部屋に雑魚寝である。みんな自宅に戻って寝てくれればいいのにとエンジュはため息をついた。
「そういえばカエデさんはどこに行ったんですか?」
「俺たちのアフターケアーをとりに行ってるんじゃね?」
ビョークがそう言った。エンジュが首をひねる。
「……アフターケアーですか?」
「そ。アフターケアー。この一ヶ月お前を監禁したまま俺たち遊んでいたわけじゃねぇのよ」
「監禁されていた部屋なんですけど、大きなベッドと買ってきたばかりのなめこの缶詰の箱以外何もなかったんですが。それにしてもどうしてなめこなんですか? 僕はこの一ヶ月間ずっとぬるっとしたキノコの食感しか口にないんですけど」
「あーあそこ、アキエの別宅。家に女連れ込まれたら邪魔だから別んところ借りてんの。お前ごときにカニの缶詰なんて用意するか、ばーか」
「はぁ……それで、なんですか? そのアフターケアーって」
もうカニとかキノコとかそういうのはどうでもよくなったエンジュがそう聞くと、ビョークはにやっと笑った。
「遺言書の発見」
「遺言は見つからなかったんじゃないんですか?」
「コズエのババアを脅したらあっさり出しやがったよ。あの女にとっちゃ誰が勝ったところで自分の保障さえしてもらえればいいわけ。それがロウコでも、クリュウでも。そんでクレイは結局俺の母親もコズエのことも愛していたわけじゃあなくて、死んだクリュウの母親が好きだった。クリュウはその息子。ちょっと嫉妬したんじゃねー? だって遺書の内容には全財産をクリュウに相続って書いてあってコズエの分書いてねぇんだもん」
アキエが乗り出して続きを話した。
「そらーロウコと取り引きしてちったぁ甘い汁も吸いてぇよな。金もった旦那と結婚して旦那がさっさと死んでくれるなんて女の至福じゃねえの? まぁとりあえずロウコはコズエの生活を保障し、コズエは遺書を隠蔽するっていう取り引きが成立して……ああなったわけ。ご苦労なこったな、クリュウ」
「……訴訟よりも今のこの環境のほうが煩わしい」
ぼそっとクリュウが本音を吐いた。
ふと実家という言葉で思い出した。幼い頃だったことを差し引いてもあの屋敷は広かった。
しかもあの地下には父親が忙しい合間をぬって仕事先から自宅に帰ってくる道があり、仕事先は……
クリュウは言った。
「ビョーク、好きなだけ珈琲が飲めるかもしれないぞ」
「マジ?」
「大マジ」
マジなんて言葉使ったことなかったがなんとなくノリで使ってみた。
遺言の隠蔽をした人間があの家に残ることはできない。まずあそこは近いうちに売りに出されるだろう。
「エンジュ、キャッシュで幾ら用意できるか銀行に相談して、即金で大邸宅を買うぞ」
「あああああ! またそうやってあなたは衝動買いするんだから」
「金は稼げばいい。幸い今までなかった人手はある上に遺産が転がり込んでくるんだ。相続税を差し引いても運営すればおつりはくるさ。ビョーク、投資はやったことあるか?」
「ねぇな」
「じゃあお前に任せる」
すごく無茶苦茶だとエンジュは思った。自分に任せられたりしなければいいのだが。
「エンジュは雑務担当だ。アキエは料理担当。回収は残り三人」
自分にまわってきた仕事がいつもどおりでほっとしていいんだか、むなしくなればいいんだかわからないエンジュだった。
ふとクリュウが思い出したようにエンジュに聞いてきた。
「ツァイはどうなった?」
「死にましたよ」
「どんなふうに?」
「うきうきるんるん気分の二人が大工店で五寸釘とトンカチを買ったところまではよかったんですが……」
「もう既にそこからしてどうしてそうなったのかわからんが」
「まぁそれでいざ、ツァイのアレに刺してやろうって時に……」
「アレってなんだ?」
「ツァイが大声で叫んで助けを呼ぼうとしたので、ビョークが先に喉を潰そうとしてうっかり喉に釘を打ちこんじゃいました。もう鮮やかなまでに一発でしたね」
その言葉を聞いて、クリュウが頷く。
「ツァイが騒いだのか?」
「ええ」
「それは災難だったな」
「はぁ……」
災難というべきなのかどうかはわからなかった。
ただしこの時ばかりは見逃したが、次第とクリュウはカエデが絡むと相手に容赦ないということがエンジュにはわかってくる。
ほしいものはすべての財産をなげうってでも手に入れる。それが彼式哲学であり、ここは彼にとっての箱庭のようなものだ。その後も彼にとって弟という存在以外は箱庭の中の存在だったのではないかとエンジュは思った。
自分を人質にとって「生かしたまま返してほしけりゃ負けろ」と言った理由……それが自分たちが面白いかどうかっていうところだけに帰一したものであって、今回は自分と違って愛されつづけた兄をなんとかしてがっかりさせたいという、なんとも十七歳とは思えない子供っぽい発想、そのくせ自分たち以外に兄をコケにされると全力で阻止しようとするあたりが、もうなんだか子供っぽすぎてエンジュには理解できなかった。
こうして天災のように襲ってくる弟の問題の数々は、神がクリュウに与えた試練のようでもあった。
忍耐、という名の。