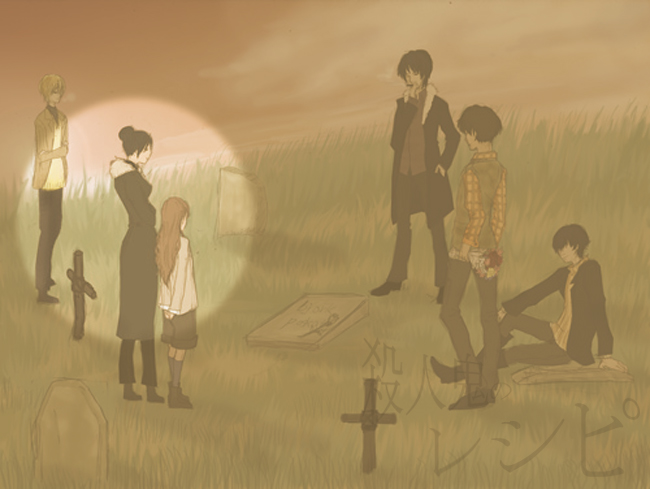
10 「かけがえのないもの」
グレープフルーツジュースを飲みながら書類に筆を通しているカエデの後ろを通りかかった時、ふと思ったこと。そんなことが始まりだった。
「カエデの奴太ったんじゃねぇの?」
無論本人に言うと鉄拳が飛んでくるのは火を見るより明らかなので、これはこっそりヒビキに聞いたことである。
トキとヒビキとスオウの会話。ヒビキは少しだけ頭を捻った。
「まぁ確かに少し丸みを帯びたかもしれないな」
「胸が大きくなっただけじゃないかね?」
「そのせいかな、最近フルーツ系ばっか食べているよな。魚は白身だけだし、野菜中心だし」
「あいつは前からベジタリアンだったよ」
「何の話をしているんですか?」
アリーを部屋に寝かせつけて戻ってきたエンジュが三人に声をかける。
「おう、エンジュ。最近カエデさんふくよかになったねって話だ」
「ダイエットしているんだろうな。フルーツばっかりとっているし」
「ああ、なるほど。たしかにそう言われるとちょっとばかし太りましたね。でもそんなこと本人に言うと――」
「――本人に言うとなんなの?」
後ろからカエデの声がしてエンジュがこの世のものとは思えないような悲鳴をあげる。
カエデは耳を塞いでから頭をおさえた。
「徹夜続きなんだから、もうちょっと声落としてちょうだい」
「あ、すみませんでした。珈琲でも持っていきましょうか?」
「いや、珈琲はちょっと吐臭がして……グレープフルーツジュースにしてちょうだい。うっぷ」
気持ち悪そうに口元を押さえるとカエデは地下へと下りていく。
豆を準備しかかったマスターが、木箱からグレープフルーツを取り出すと絞り始めた。
氷を浮かべたグラスに硝子のストローを差しながらエンジュが呟く。
「でもカエデさん、今までどれだけ馬鹿食いしたって徹夜したって、絶対に美貌と体型だけは崩さなかったじゃないですか。変ですよね、フルーツばっかりとってて。妊娠でもしたんでしょうかね」
「あはは、確かに妊娠するとすっぱいものほしくなるらしいしな!」
「まさかー、クリュウが死んでからどれだけ経つんだよ? ありえねぇだろ」
「まだ四ケ月ですから、ちょうどそろそろ腹ぼてになりはじめる頃かもしれませんね」
あははははは、とひとしきり笑ったあとに場の空気が凍りついた。
意味もなく声をひそめて会話する。
「……ってことはクリュウの子供か?」
「他の奴の子供ってことはないのか?」
「まだ子供と決まったわけではないんですが……」
◆◇◆◇
「――という話が昨晩でたんですよ」
「ふーん……」
珈琲を飲みながらビョークが眠そうに頷く。こちらも徹夜続きである。年末ここに休息はない。
「気にならないんですか?」
「だってクリュウの子供だろ? 俺の子供じゃあないし」
「はぁ。あのですね……」
あまりにも無関心なビョークに、ため息をついてエンジュは説明をはじめた。
「忘れているかもしれませんが、ビョークは書類上は死んでいて、今はあなた、クリュウってことになっているんですよ」
「……そうだった」
そこまで言ったところでビョークは思い出したように頭を抱えた。エンジュがとどめを刺す。
「つまり戸籍上父親になるのはあなたなんです」
「二児の父親か。あーどうしよう、碌に恋さえしていないのに」
「恋もしてないのに既成事実だけ重ねていくからこんな結果になるんですよ」
まるで自分があちこちの女に手を出してまわっているような言い草に、ビョークは何か言い返してやろうかと考えたが、それよりもやらなくてはいけないことがある。
「エンジュ、皆に検尿するように言っといて」
「検尿ですか?」
「表向きは健康チェック、カエデが妊娠しているかどうか調べさせてこい」
数日後、検尿の結果発表が配られると共に、スオウがビョークの部屋に来た。袋に入っている妙な棒をビョークとエンジュの前に並べる。
「いいか、ビョーク。これが陰性の色だ。そんでこっちが陽性。それで、これがカエデのだ」
最後に並べられた結果を見ながらビョークは唸った。エンジュも唸る。
「めちゃくちゃ陽性じゃないですか」
この結果は想像していたにはしていたわけだが、しかしどこかでそうならないでいてくれればいいのにといった願望はあったわけである。
部屋の中心にあるソファには、人払いをすればいいのにアリーがいた。
ビョークはおもむろに聞いてみた。
「アリー、おかあさんほしいか?」
「別に」
チョコレートを口に放り込みながらすごく投げやりな返事が返ってきた。
「お父さん結婚するかもよ?」
「すれば?」
今度はホットチョコレートを飲みながらアリーは言った。
甘ったるいかおりと共に妙に世知辛い空気が流れる。
なんだかこの親に対して興味のひとかけらも示そうとしない娘になんとなく腹立たしいものを感じる。
「……んじゃ、勝手に結婚するから」
「ビョーク、子供の言葉真に受けてムキにならないでくださいよ。だいたいあなた、クリュウが縁談持ちかけた時はことごとく蹴っていたじゃあないですか。しまいにはウエスト五十センチ代の握力五十の人とか無理難題突きつけて……」
「あれなー、あれたしかすごい美人が来たっぺよ。どうして断ったんだ?」
「……戸籍上の性別に問題があったから」
最後の最後に婚姻届にサインする際にわかった事実を少しだけ口篭もりながら言った。
法律が変わった時、もう一度彼女(彼?)が自分の目の前に現れた時のことも考えて今のうちに結婚しておくべきなのかもしれない。
「俺のお見合いの時異様に人来たけど、どうして?」
「あれはですね、そのままだと誰も来なくてビョークの自尊心が傷つくといけないので『お見合いに来た人にはもれなく宿泊費と温泉代もちます』って書いて配ったからです」
「……それ聞いた時の俺の自尊心はどうなるのよ?」
どうりでお見合いの最中、温泉について詳しく聞かれると思ったらそんな裏事情があったとはまったくもって知らなかった。
「逆にビョークが開催したクリュウの花嫁探しはなんだか皆怖かったべよ」
「なんだか皆積極的というか、目がギラギラしていましたよね」
「あれなぁ……あいつの最大の長所をアピールするために下のほうに年収を書いておいてやったんだ」
「だから皆怖かったんだ」
「なんというか即物的な女性が多くなりましたね」
三十路の男が顔を並べてため息をついた。スオウがアリーに聞いてみる。
「アリーはどんな男がいいんだべよ?」
「お金持ち」
「時代は着々と女の時代になってきているようですよ、ビョーク。いつまでもあなたの女性蔑視は通じません」
「やー別に女を差別しているわけじゃねーのよ。俺がここだとするっしょ? あんたらはー、まとめてここらへん」
目線の高さをつつ、と指を動かしたあと、今度はわざわざしゃがみこんで地面をなぞるようにして指を動かすのを見て二人は同時にうなだれた。ビョークの時代はまだまだ続きそうである。
ここのトイレはユニセックス制になっていたりする。
男の数が圧倒的に多い組合の中で、女性用のトイレを別に用意するのはコストがかかる。 しかし用意しないわけにはいかない。では全部個室にしてしまえばいいではないか。こんな考えからこうなった。
そこの奥の一室はいつもビョークが何か考え事をしていて、邪魔されたくないときに篭ると決まっている。これはクリュウの時からの伝統である。
十八の頃にクリュウの姿がまったくどこにもないとき、必ずここの扉がしまっていた。
ノックすると低い声で「考え事中だ。邪魔するな」と言われるのである。
いつしかクリュウがここに篭ると、プレートを「考え事中」にかえる人まで現れた。
そんなわけでいつしかここは、誰かが考え事をするとき、プレートを「考え事中」にかえて入る場所……そんなところなのだ。
二児の父親になる。
一人は自分とまったく面識のないまま十代突入、もう一人はまったく身に覚えもない戸籍上の子供。自分の年齢はもう三十代に突入していて、この年齢で二人の子供を持っている親というのは少なくはない。
自分の父親がどんなのだったかを考えれば、ともかく自分のことを憎んでいたような気がする。
表だってそういう否定的なことを何か言われたわけではない。母親が何か言ったわけでも、周囲の人間が何か言ったわけでもないのだが……あの父親の目が、自分と母親を向いている時だけ妙に冷たい白けたものになっているのにある日気づいて、それは薄々気づいていたことではあるのだが、ともかくそうして日に日に父親を観察するようになると、色々なことが見えてくるようになった。
組合の人間は何も教えてくれなくたって、近所の情報屋にいってちょっと金を握らせれば噂話くらいあっさり手に入る。そうやって少しずつ、自分の生い立ちを調べていった。
今考えれば確認する必要なんてなかったのかもしれない。
あのまま何も知らないでいけば自分が愛されているかもしれないという希望くらいはもてたのじゃあなかろうかと。
そうしたら今こんなに自分の子供を愛してやれるかどうかに疑問をもたなかったかもしれない。
「愛されてない子供だって世の中で生きていく価値がないわけじゃあないんだよな」
もしそれが権利でないとするのならば、自分はここには存在してはいけない。そうして存在してはいけない子供があふれて、その子供から生まれた子供がまた存在していいかという馬鹿馬鹿しいロジックにはまりこんでしまう。
ザーっと水が出る音がした。
蛇口をめいいっぱい開けた音である。
そしてドン、と一度扉を蹴る音がすると扉の上の部分に白い手が見えた。体をぐっと持ち上げるとそのまま個室の中に入ってきた青年をビョークは座ったまま見上げた。
「アカツキ。お前、ここはどこよ?」
「知っているよ、トイレだよ」
「トイレって完璧プライベートな場所じゃねぇの?」
「そうかも」
薄茶色の目が見下ろしてきている。仄暗い白熱灯が点滅している下でビョークの目を覗き込んでいた。
コンタクトの向こうの、ちらちらと不思議な光が目の中で動くのを見ているといつも不思議な気分になる。この目には不思議な力が本当に宿っていた。
アカツキの目は通称“フロンティアの眼”と言われる古代技術を受け継いだものだ。その眼を媒介に人体の中を流れるあらゆる情報を汲み取ることができる。今、アカツキは自分の中のどんな情報を見ているのだろうか。
「誰か入ってきたら蛇口を止めるだろうし、あれだけひねっておけばちょっとの声じゃあかき消されるよ」
たしかにこれだけ大きな音を出していれば消えるかもしれない。
「色々考え事していた」
「表に『考え事中』の札がぶら下がっていたからわかったよ。あのね……」
アカツキは一呼吸間を置いてから話し始めた。
「最初から完璧な親なんてどこにもいないと思うんだ」
「じゃあ何時頃を目安に完璧になればいいわけ?」
「何時頃完璧になりたいの?」
ビョークはアカツキの言葉に少し考え込んだ。死ぬまででは少し長い、しかし今すぐは少し難しい。
「アリーが大人になった頃に俺を憎んでいなければいいと、うっすら考えた」
「じゃあその頃を目安にしとけばいいんじゃない?」
「えらくいい加減じぇねーの?」
「普段のビョークから比べれば子供が関わっている時のビョークが真剣すぎるんだよ。答えが出ないものに真剣になって悩んでいるんだ」
たしかにそうかもしれない。
答えが出ないという結論がありながら、悩む。この繰り返しである。
答えの出ないものは普段は保留にしておく。 しかしこの子供というものが関わっている時だけはそれができなかった。
「問題はアリーなの?」
「いや……」
嘘をついても仕方がないので正直に否定した。
「子供がもう一人できるかも……」
「おめでたい話じゃない。相手は僕の知っている人?」
「知っているな」
「認知はするの?」
「しなくても一人で産むだろうさ。そういう女だから」
「結婚はするの?」
「するかも……」
ビョークはアカツキの質問の中で確かめなければいけないことに幾つか気づいた。
そうか、自分は認知もするし結婚もするつもりでいるわけだ……と。
「……なんか色々悩んでいたことが馬鹿らしくなった」
「そうでしょう?」
「なるようになるわな。とりあえずアカツキ、ここから出ろ。トイレで子供の育てかたを相談している男二人ってのはなんだか間抜けだ」
「ぶっちゃけ傍目から見たら気持ち悪いよ」
そのとおりである。
ざーざーという水道蛇口の音が聞こえっぱなしで本当によかった。
翌日は実に晴れ渡っていた。
雲がひとつでもあれば誰かを気まぐれに殴ったかもしれないが、自分の心に迷いがないことを証明するように真っ青な空だった。
「ビョーク、言わなきゃいけないことがあるっぺ」
あらたまってスオウがビョークの部屋に入ってきた。昨日と同じように透明な袋に入った棒を取り出す。
「これ……アリーの検査結果を試しに出してみたんだけど……」
「ふーん……」
珈琲をずずっと啜りかけてからその結果を見てビョークは噴き出しかけた。
「……陽性反応なんだけど」
「んで、エンジュの結果がこれなんだ」
こっちの反応も陽性である。
「……男が子供産めるようになっちゃ女の立場ないんじゃね?」
「だから、これ結果が逆なんだよ。こっちの色が陰性でこっちが陽性……つまりカエデは妊娠してないと」
「……そもそもカエデが妊娠したってなんで思ったわけ?」
「太ったってことと、フルーツばっかりとるようになったってことと、あと珈琲見ると吐きそうになっていたべ」
「……どうせ二日酔いだ」
カエデが太ったのも吐きそうになっていたのも全部酒のせいということにした。
ああ、昨日一日を無駄に使ったとビョークは頭が痛くなった。
年末から年始にかけては忙しい本部で、カリカリと万年筆を動かす音がずっと聞こえる。
執務室で無言で作業をしていたカエデとビョークのところに新人がいつものように珈琲を持ってくる。
それに口をつけながらビョークは考えた。
自分は子供ができたから世間体を気にして結婚をするような人間でも、責任を感じるような人間でもないはずだ、と。
だとするならばどうして結婚しようなんて思ったのだろうか。
幸せな家族なんていうものは自分の幼い時に打ち砕かれた。それにまだ未練があるとするならば、この人とならばもしかしたら……ちゃんとした家族を築けるかもしれないと、どこかで希望のようなものを持っていたのかもしれない。クリュウもその昔同じことを考えたのだとしたら……どうなのだろう。
「……カエデ」
「何?」
グレープフルーツジュースを啜りながら寝不足のカエデが不機嫌そうに応えた。
「結婚しないか?」
「あんた以外とならね」
にべもなく断られた。
もうこれはクリュウへの敗北以外のなにものでもないと思った。
昔からわかっていたことだ。彼女はクリュウが好きだということや、死んだ人間に敵うはずがないということくらいは。
カエデから回される書類にサインだけしていく流れ作業なのでカエデは忙しいがビョークはそれほど忙しいわけではない。続けて言った。
「でもお前そろそろ結婚しねーと色々とやべぇっしょ? 結婚適齢期はぶっちぎったからもう気にしないとして、ウェディングドレスの九号が入らなかったり、鯨骨のコルセットでもバルコニー型にならない胸とか……」
「殴られたい?」
どうやら体型が崩れはじめていることはカエデ自身も気づいているらしい。
「ここの組合、むさ苦しい集団だから女っ気すくねーのよ。お前けっこうモテるの。知ってる?」
「へー、誰がよさそう? 選んであげる」
時代は女が選ぶ時代になったようだ。
エンジュのもう自分の女性蔑視の時代は終わったという言葉がよぎる。
「えーとね……クリュウ」
「死んだ」
「スオウ」
「ハゲ」
「トキ」
「くさい」
「ヒビキ」
「妻子持ち」
「アカツキ」
「ガキ」
「エンジュ」
「却下」
一言でことごとく却下されていくのに最後だけ決定的な理由がなかった。
「なんでエンジュが駄目なわけ?」
「はあ? あいつ却下なのに理由っているの?」
「やーいるでしょう。万年雑用とか万年平とか小間使いだからとか下僕だからとかなんでもいいからとりあえず探せば理由のひとつくらい」
「とりあえずあんたとエンジュだけは却下なのよ」
「だから、なんで俺とエンジュだけ却下なんだよ!」
ビョークが意味なくムキになったのでクマのある据わった目で睨みつけながらカエデがずずっとジュースを飲んでしぶしぶ話しはじめた。
「あんた、妻と夫どっちが立場的に強いと思っている?」
「夫」
即答した。想像していたかのようにカエデが頷く。
「それが理由よ」
「俺はともかくとしてエンジュは違うでしょ」
「違わないわよ。あいつはね、すっごく女の人を大切にするの。守らなきゃいけない存在だと思っているのよ」
何かそれがいけないことなのだろうかとビョークが聞こうとしたところで、ガシガシとカエデが頭を掻きながら書類に目を通しつつ唸るように言った。
「あんたたちだけとは生涯対等であり続けたいのよ」
「……なんで?」
「ともかくよ」
ともかくを強調されて、なるほどそれが理由なのかとビョークは納得することにした。
長い黒髪はひっつめたまま、まったく乱れがない。爬虫類のような鈍色の光を放つ視線の、かつてクリュウが愛した女の横顔をじっと見つめた。
気持ち悪そうにカエデがこちらをきっと睨んで言った。
「何じろじろ見てる? 見世物じゃないんだよ」
「いや、いい女だなって」
「あんたは紙魚みたいな男だけどね」
紙魚というのは、和紙を食う触覚をつけた害虫である。和紙が何を指しているのかはわからなかったが、なるほど自分はたしかに紙魚のような男であるとなんとなく納得してしまうのだから自分はマゾなのかもしれないと思った。
「カエデー」
「いい加減に仕事に集中させてくんないかな?」
「愛してる」
「キショッ!」
容赦ない一言で叩き落されて背中がぞくっとした。自分はいよいよ未知の分野に踏み込みかけているのかもしれない。
そのサティスファイな笑みを見てからカエデが心底気持ち悪いとジュースを飲みきってがん、とデスクに置いた。
「今日のあんた気色悪い。私にやさしくしてやるという心構えができたならちょっくらグレープフルーツジュースもってこいよ」
「新人ー、カエデがおかわりだってよ。ダイエット用のグレープフルーツバケツごともってこーい!」
「一言多いのよあんた!」
「ビョーク、カエデさんのダイエット用グレープフルーツもうありません」
「あんたも!」
入ってきたエンジュにまで牙を剥いた。
何もわかっていない、目をぱちくりとさせているエンジュとにやついているビョークにカエデは言い切った。
「絶対あんたらと結婚なんかしないからね」
「……なんのことですか?」
「なんのことだろうな?」
ふたりが一緒に肩を竦める。三人はいつでも対等なのだ。これまでも、これからも。