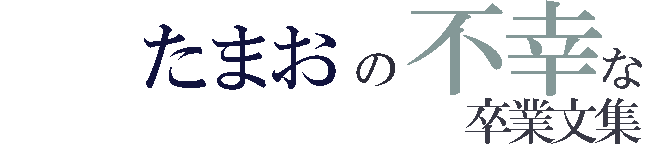
12/13
そもそも、感情障害ってどんな病気なのだろう。
精神病の一種ということしか知らなかった僕は近くの本屋でそれを調べてみることにした。
もし篠宮さんと関わらなかったら、一生手にしなかったであろう本に手を伸ばす。中学生である僕が「学習・参考書」のとなりにある「家庭・医学」の棚と真剣に向き合っている姿は、参考書選びのときより真剣そのものだった。
そうしたら意外なことがわかった。感情障害はてっきり精神病だと思っていたら、それには含まれないらしい。鬱病や躁鬱病のことを総称してそう呼ぶらしい。
ハイになったり、鬱になったり、ころころ気分の変わる病気のことで、感情が欠けていることについて言うわけではないようだ。
僕はまったく言葉の意味を理解していなかったのだなあと思ったが、篠宮さんが滅多に「悲しい」とか「つらい」とか言わないのは、きっと陰性反応のほうに入るのだと思う。他の要項もチェックしてみたけれども、篠宮さんは鬱病でも、躁鬱病でも、躁病でもなさそうに思えた。もちろん、他の不安障害やパニック障害でもない。
でも実際彼女は苦しんでいるし、それは憂鬱なんて言葉で片付けていいものではない。
素人判断で「彼女は○○病だ」と決め付けることはできないし、病院の先生が「感情障害」とくくったのは、おおよそのくくりでしか判断できないと見たからだろう。
「あれ? 三芳じゃないのさ」
後ろから篠宮さんの声がして、ばっと振り向いた。そこにはいつものぼさぼさ頭ではなく、綺麗なボブカットの篠宮さんがいた。
「髪……」
「ああ、山田のかあちゃんが切ってくれたんだ。美容師だったんだって、どう、似合う?」
篠宮さんがにかっと笑う。眉まできっちりと整えてあった。
「今ちょうど、あんたの持っている薬の本を探しにきたところだよ」
「どの薬飲んでるの?」
「睡眠薬となにか」
「ちゃんと調べなよ」
「それを調べるために買いに来たんだろ。三芳ー」
薬の名前も覚えていられないのか。受験大丈夫なんだろうな? と少し心配になる。
ふと、篠宮さんのこの記憶力の悪さもこの障害に関わってるのかな? なんて思った。
「感情障害について調べたんだけど、篠宮さんがどのケースなんだかよくわからなかった」
「そんなの、医者でないあんたにわかるわけないじゃない」
「普段どんなこと感じたりしているの?」
「言葉にしがたいね。外の音がやけに気になったり、戸締りを何度もチェックしちゃったり、別に視覚が狂ってるわけでもないのに世界がモノクロに見えたかと思ったらサイケデリックに見えたり、ともかく色々だよ。これって説明できない」
本に書いてあった妄想や幻覚とは違う説明をされた。やっぱりこれから勉強するしかないのか。
「受験終わったら、本格的に勉強するよ」
「なんで? これは私の障害なのに」
篠宮さんはとても鈍い。僕がこれだけ力になりたいとがんばってきたのに、まだそんなことを言っている。
「僕は君の力になりたい。助けたいんだ」
そう言った瞬間、篠宮さんは半眼になり低い声で「ぶぁーか」と言った。
「誰かに助けてもらって幸せになりました、なんて結末、幼稚園児しか納得しないよ。そりゃひとりで生きていけないのはわかっている、私は無力な子供なのもわかっている。だけど……自分でできることまで、人にやってもらうつもりはない」
びしゃっとそう言うと、僕の手から薬の本を取り上げて、何事もなかったかのように笑う。
「あんたの思いやりに何度も救われてきたよ。とっくの昔に、三芳は私を救ってるんだ。私がひとりじゃあないって教えてくれたのは、鮭弁当であり、執務室のクーラーであり、野菜ジュースであり、ラーメンであり、使い古したセーターであり……ともかく色々だったよ」
篠宮さんは「ありがとう」とぼそっと呟いた。
僕が篠宮さんにしたことは、彼女の境遇から見たら本当に僅かなことだった。僕はもっともっと、篠宮さんが成り立つようになるまで援助しなくちゃいけないと思っていた。まだ足りない、まだ足りないと思っていた。
だからお礼を言われたのが信じられなかった。
その日から、僕は彼女に「尽くす」のをやめた。「充分だ」と言われたからやめたわけではない。犠牲になったり、尽くしたりするのが「彼女のためになる」という考え方をやめただけだった。