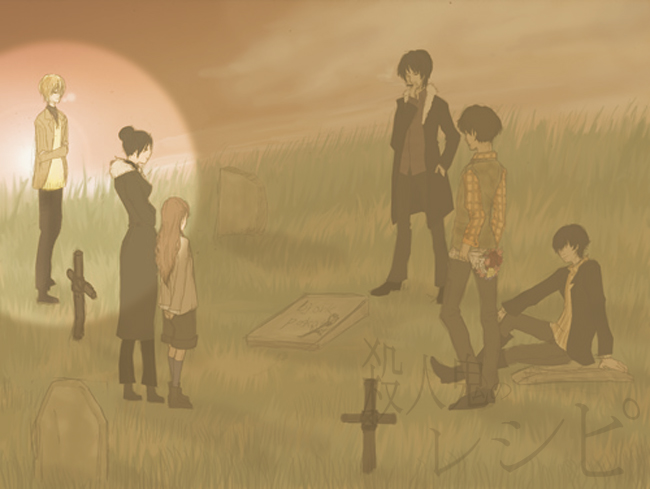
03 「暁」
03暁
フロンティアの眼。それは人体に流れる情報をすべて、手に取るように感じ取られる能力。
スノースタリン大陸の少し東にある島にその眼を持つ一族たちは住んでいた。朱い柱と赤土の建物、黒い瓦で作られた都ファンダリアは、テールの歴史上、何度も侵略された。
最初はその赤い眼が美しいと眼を取られる、
次はその能力が面白いと見世物小屋に連れて行かれる。能力が危険視されて殲滅させられれそうになったこともあり、今はその能力は稀少価値があると世界中から注目されている。
長い間侵略され続けたファンダリアに今、フロンティアの一族はいない。最後まで住んでいた人々も世界中に連れて行かれて、今では世界中に散り散りだ。
その人間がフロンティアの一族かどうか手っ取り早く知る手段は眼を見ることだ。彼らの眼はとても赤い。アルビノというわけではないのに赤いのだ。
その眼ゆえに殺され、その眼ゆえに道具扱いされ、その眼ゆえに化け物と恐れられるその一族の、一番の苦しみは心の声が聞こえてしまうことだった。
ファンダリアが平和だった頃、彼らは嘘という概念がなかった。そして思いやりのある人たちだった。
世界中に散らばったフロンティアの一族たちは“悪意”というものを知ることになる。人一倍、悪意というものを感じ取ることになる。人の何倍も、悪意の渦中に身を置かねばならなくなる。
◆◇◆◇
父は僕に、僅かばかりのお金とチケットをくれた。
「これでアルカロイドに逃げなさい」と言われた。お父さんがもうすぐ死ぬことは体の情報を読めばわかった。父も僕の悲しみがわかったようで、僕たちは言葉の代わりにそっと抱擁し合い、僕はひとりで飛行竜乗り場まで向かった。
声をあげなかったのは恐ろしかったからではない。声をあげたら最後、屈服したようで、それが嫌で闇の中で声を噛み殺した。
耳元に熱い息が吹きかかる。相手の攻撃的な感情がダイレクトに伝わってくる。
ひとりで生きていかなきゃいけないんだ。こんなことくらいへっちゃらなんだ。そう言い聞かせて奥歯を強く噛み締めた。
見上げた夜空に月が上っていた。水晶体を包むようなうっすらとした泪で、月が濡れていた。
夜陰の頃には宴も終わり、ずたぼろの自分だけが残された。
金の猫毛を秋の宵風が撫ぜていく。やわらかい風だった。心を少し落ち着かせるように、少年は深呼吸をする。
じっとりとした土の匂いと虫の鳴き声が少年に晩夏を知らせてくれた。
ざりっ、と地面を踏む音が聞こえて、緋色の視線だけを動かした。
暗い中にエナメルの靴だけが艶をはなち、こちらに近づいてくる。
自分の倒れているあたりまでやってくると立ち止まって、男はしゃがみこむと少年を覗き込んできた。
ギラギラとした凄艶な目をした、その男に首筋に触れられた時はそのまま殺されるのかと思った。
ひんやりとした指先がぺたりと首の動脈に添って動かされ、ごろんと仰向けに転がされた。そのままにしていると、今度は乱れたシャツの間から脇腹あたりを触られた。
「生きているー?」
声はけっこう若かった。
うっすらと開いた目を瞬きさせると男は頷いた。
「痛いところはあるか?」
ある。こくりと頷く。
「怪我はしてないように見えんだけどどっかしら内臓にダメージがあるかもしんねぇな。犯人の顔は見たか?」
もう一度、頷く。
「最後にひとつ、俺と来るか? このまま放っておいてほしいならそうするけど」
少しだけ考えてもう一度頷くと、男は形のよい唇を歪めて自分の髪を撫でるとそのまま軽い体を抱き上げた。
裏路地からはいったアパートの中は、外壁とは裏腹にきれいにされていた。
薄暗いランプの灯りがゆらめく小さなダイニングを横切ると、そのままシャワールームへと連れて行かれた。
この頃になると少しだけ体に力が戻ってきたが、部屋まで連れてこられてまともに立っていられない体では抵抗はできないと少年は思った。
無造作に服を引き剥がされる。男は服を着たまま、少年を抱きかかえて浴室に入った。
栓を開けると鉄くさい水が天井から降り注いでくる。
冷たい水が火照った体の熱をじょじょに奪い去っていく。男は自分の体を壁に斜めにかけると背後からやる気なさげに言った。
「ちっとの間立ってられるか? 別に悪さしようってんじゃねぇよ、さっきの奴があんたの体ん中に出しやがったもんを外に掻きだすのさ。そっちには詳しいわけじゃあないから乱暴だけどまぁ許せ」
言い終わるか言い終わらないかのうちにまた体に電撃のような痛みが伝わる。じくじくと中身を掻き回されて抉られて、先程堪えていた呻き声が少しだけ零れた。
「泣きたければ泣けば?」
その言葉そのものが、台詞とは裏腹にいやに冷ややかだった。
別に泣いたって泣かなくたって、この男にとってはどうでもいい問題なわけで、この言葉にも深い意味はない。
体を十分に洗われたあとには白いシルクのシャツが放られた。
手短に「着ろ」と言われて、言われたとおりに袖を通す。自分は着たこともないようなおそろしく肌ざわりのいい生地に、なんとなく居心地悪い思いだ。
男のほうは男のほうで、濡れた衣服と破れた服をてきとうに洗濯カゴに突っ込むと、洗ったばかりの服に着替えていた。
そのままキッチンのほうに入るとなにやらマグカップに注いできて、それを渡された。
珈琲の上に八分立ての生クリームとアラザンが乗っかっている。表面を啜ると、仄かな甘さと苦味が広がった。
男はずずっと一口珈琲を飲むと、切り出してきた。
「……名前は?」
「セス」
「歳は?」
「……十三歳」
この男の正体がわからず、質問されるがままにか細い消え入るかのような声で答えた。
先程陵辱していった男の舐めまわすような視線とはまったく違う、観察する者の視線である。
この男はきっと、何か目的があって自分に近づいたのだ。そういう電気信号を奏でている。
男の濡れた髪は鴉のように黒い。インディゴの目の、二十代半ばの男だ。
セスはありったけの勇気を絞って質問してみた。
「……おにいさんの名前は?」
「ビョークって呼ばれてる」
「自分の名前嫌いなの?」
「別に嫌いじゃあないけど?」
嘘だ。ネガティブな信号を出している。
セスはソファに座ったまま、見下ろされてびくっとした。怯えるように紅い目で見上げる。
「怒った?」
「なんで?」
「不機嫌そうだから」
「そうだな」
否定してくれれば少しは居心地がよかったかもしれない。
居た堪れなくなって視線を珈琲へ落とす。
ビョークは近くのベッドに腰かけるとこちらを向かずに聞いてくる。
「他に聞きたいことは?」
「どんな仕事しているの?」
「内緒」
「家族はいる?」
「いるよ」
「どうして一人で住んでいるの?」
「アルカロイドに留学しているからだよ。ポスカトに家族はいる」
「それも嘘なんだね」
「嘘だよ」
「本当のことは何も言わないの?」
「言う時もあるよ」
「じゃあビョークはどうして僕をここに連れてきたの?」
そこまで言うと彼は顔を上げた。
形のよい柳眉をぴくりとあげると、すっと指をセスの鼻のところまでもってきた。
「お前を探してたんだよ。失われた技術の継承者、フロンティアの末裔」
フロンティアという言葉にセスはびくと目を見開いた。
その紅い揺らめきの中にちらちらと細かな黄金の文字が浮かぶ。
ビョークはずずっと珈琲を飲みながら、セスに言ってきた。
「体温の変化があるか? 脈拍は、波動は……別に何ら嘘なんてついていないことぐらいわかるっしょ? お前なら」
びくびくしながら頷いた。
セスは小さい頃から不思議な力があった。それは相手の心の変化が読めるのだ。
具体的に心が読めるわけではなかったが、体温の上昇や心拍数、脳内のちょっとした分泌物質の違いなんかもわかった。
それが自分だけの特異体質であることがわかったのは、親が死ぬ間際に教えてくれた、自分の血筋だった。
「息子のお前が軍部に利用されることを恐れて親は死の間際にお前をヘサから逃がした……それでアルカロイドまで来たわけだが、来たと同時にまぁ、災難だったな。俺が早く見つけていりゃあなぁ〜」
悪びれずに呟くビョークにセスは聞いた。
「ビョークは軍の人なの?」
「逆。ヘサのマフィアからお前を探せって指令がおりているわけ。お前の能力をほしがっているのは何も軍部だけじゃあないってこと」
「……僕、これからどうなるの?」
「聞きたいか?」
空になったコップをチェストの上におきながら、ビョークはこめかみを指差す。
「軍部に行くと、ここにチップみたいなのを埋め込まれる。逆らえないようにだ。万が一の時のことを考えて、能力が他者にわたらないように爆発する仕組みになっている。逆に俺たちについてきた場合はきっとクスリを使われるな。長く飼いたいだろうからそんなヤバイもんじゃあねぇと思うけど、依存性が強くて常習性があって、逆らう気が失せるようなやつだよ。だいたいこの先の運命がわかったか?」
「……うん」
なんだか暗雲立ち込める思いでセスは頷いた。それを見てビョークはやや呆れたような顔をした。
「子供なんだからさ、『そんなのイヤだ』くらい言えねぇの?」
「言って運命が変わるの?」
「言わないで運命が変わってくれると思うなよ?」
ビョークはセスのコップを取り上げてチェストに置くと、そのままセスを抱き上げた。
軽い体は一瞬にして重力から解き放たれる、が、次の瞬間にはベッドに投げ出されていた。
上から圧し掛かるようにしてかかる重圧と香水の匂い。セスを組み敷いたまま彼は囁いた。
「またさっきと同じように我慢していれば終わると思っているから抵抗しないんだろうがな、俺たちがこれから行こうとしている世界は、抵抗しなきゃどこまでも食い物にされる世界なんだ。生かされ続けて食われ続けるんだよ、わかっているか? わかっているなら死ぬ気で抵抗しろよ。死ねるかもしれねぇぞ?」
無茶苦茶な理屈だとセスは思った。
真っ直ぐに真紅の眼で、濃紺色の目を見つめる。
ビョークはまた聞いてきた。
「なんで抵抗しないんだ?」
「抵抗しているよ。ビョークの言うとおりにしないっていう意味で」
「ああそう」
ビョークが低く呻いた。セスは続ける。
「あと、心拍数が落ち着いているんだ。まったく昂揚感がない。きっとビョークはなにもするつもりがないんだと思う」
「それ言ったらムキになった俺に何かされるんじゃないかって懸念はないのか? クソガキ」
「それは念頭に入れてなかった」
ため息をつくと、ビョークはそのままごろんと横に転がった。
「とりあえず寝ておけよ。ベッドは一つしかないから共用だけど、何もされないってわかっているなら大丈夫だよな?」
本当は本当に大丈夫という確信などなかったのだが、とりあえず大丈夫だろうと自分に言い聞かせた。隣に転がっているビョークに聞いた。
「ねえ、僕が逃げたらどうするの?」
「ほうっておく。どうせお前みたいな世間知らず、アルカロイドの路地で野垂れ死ぬだけだ。じゃあなかったらその可愛いベビーフェイスを売り物に男娼ぐらいしか仕事なんてない。そういう街だよ、ここは」
ビョークは眠そうに欠伸をすると、そのまま眠り始めてしまった。
世間知らず。囚人たちがうろうろしているヘサ育ちなのだ、そう世間知らずなほうではないと自分では思っていた。
テールで一番大きなアルカロイドという都市は貧富の差が一番激しいと聞く。きっとヘサのように下々の者にもそれに相応しい仕事があるんじゃあないかと勝手に思っていた。
――男娼ぐらいしか仕事なんてない。
セスは先ほどの台詞を思い出してぶるっと背中が震えた。仮に客がひどいことをしたとて、医者にかかる金もないのだろう。
飛行竜から見たアルカロイドの街は、赤や黄色の綺麗なライトで色彩られた華やかな街だった。
月――メカポリスへの銀河鉄道はここからしか出ていない。一番メカポリスに近く、最新の技術が入ってくるのがアルカロイドなのだ。
自分がのびのびと生きて行ける場所なんて存在しない。生きるのに精一杯の人々は、夢など持ってはいけないのだ。
◆◇◆◇
夜中にふと珈琲が飲みたくなって、ビョークは起き上がった。
普段から生活が逆転しているせいか、なかなか眠れなかったのである。
ドリップで抽出した珈琲を口に運び一服して、先程拾ってきた少年を見た。
身長はこんなものだろう。体型もまぁこの年齢相応のものだと思う。金色の猫毛がやわらかく、紅い目がすごく澄んでいた。
それは別にこの子供が何も困ることがなく生活してきたからそうなわけではない。
人の心が読める人間は、普通ならば人間不信になるだろう。それなのにこのセスはそれでも人を信じようとしているのだ。
愚かと言えば愚かなのだが、愚直とも言える、どこか美徳めいたものを感じた。
ビョークは綺麗なもの、美しいものをこよなく愛する。
そういうものは汚れないように大切に宝石箱か何かにしまっておきたいと思ってしまうのだ。誰にも見せず、自分だけが見ておきたいと。
しかしそう思う一方、だからこそ自分の手で汚してしまいたいと思ってしまう人間がいることもわかっている。
真っ白な新雪に足跡をつけるような感覚で、美しいものを軽々しく踏みつけるそんな人種がビョークは嫌いだ。
こんなにきれいな少年をどうして皆して踏みにじろうとしているのか、ビョークにはいまだに理解できないでいた。
◆◇◆◇
安物の薄いカーテンが風でめくれあがる。
その隙間から差し込む朝の光にセスはうっすらと目をあけた。
「っ!?」
自分の体の上に乗っかっている右腕に思わず身が引き攣る。おそるおそるその腕をどかして起き上がろうとした。
昨日はシャツを着ていたのでまったくわからなかったが、半裸で寝ている隣の男は、かなりしっかりと無駄のない筋肉がついている。そのくせに指は女のように細く、水仕事なんてしたことがないようにやわらかい。
どんな仕事をしていたらこんな体になるのかセスにはまったくわからなかった。
と、今まで妙に重たかった腕が自分の意志をもって動き持ち上がった。それと同時にビョークが体を起こす。
「起こした?」
「いや、今起きた。顔洗え、すぐ出かける」
どこに出かけるかは教えてくれなかったが、その言葉からセスはそのままヘサを想像して、疑うこともなかった。
案の定ついたのは飛行竜の屯所だった。
つい一昨日ここについたばかりで、もうこれから先はアルカロイドで生きていくと決めていたのに、そう決めた翌々日にはヘサに帰るのか。しかもこれから先はよりいっそう、碌でもない人生になりそうだ。
「浮かない顔じゃねぇの。おおかたヘサにでも連れて行かれると思っているんだろう?」
「違うの?」
「人を待っているんだよ」
「誰?」
「俺の相棒」
相棒と言ったときのビョークは少し嬉しそうだった。きっと彼はその相棒のことが大切なのだろう。
そんなことを考えた矢先、向こうのほうから手を振って近づいてくるチャコールスーツの男がいた。
セスの超人的な視力は遠くのほうにいるその男の顔が、あまりにも隣にいるビョークにそっくりなのがわかった。
「よぉ、アキエ。どうだ、いい休暇はとれたか?」
隣のビョークが手をあげるとアキエが大声で名前を呼ぶ。
「ビョーク、いつ行ってもポスカトはいいところだな! 酒は美味いし、温泉は気持ちいいし、また影武者になってほしい時は言ってくれよ」
「そっちが遊んでいる間に俺はお前の仕事をちゃんとこなしていたぞ。これが、“眼”の持ち主だ」
ビョークがどん、と背中を叩く。セスは前につんのめた。
アキエは山高帽をはずしてセスにかぶせると、にっこり笑った。顔はそっくりだが目が明らかに違うとセスは感じた。
「可愛い子だな。ビョーク、名前はなんてぇ言うんだ?」
「セス=フロンティアだ」
「セスっていうのかー、可愛いなぁ。よろしく、セス」
そう言ってセスの唇に軽く唇を重ねると、そのままアキエは何事もなかったかのように歩き出した。眼が点のまま固まったセスにビョークが声をかける。
「びっくりしたか? あれはキス魔なの。俺も最初はびっくりした」
「お……」
セスは唇が触れ合った瞬間のアキエの脳内物質の氾濫を見た感想をどう伝えようか迷って、そのまま端的に表現した。
「……犯されるかと思った」
「じゃあ気をつけろ。あいつは俺よか腕っ節が強い」
ビョークはきっと守ってくれないだろうとセスは思った。
最初にビョークに連れてこられたあの古びたアパートはアキエのものだった。
簡単に話を聞いたところ、アキエは各地を転々としている賞金稼ぎで、ビョークはポスカトの大地主。
地位のまったく違う二人が知り合ったのはポスカトの珈琲店で、そのままビョークが自分がどこかに旅行に行く間だけ仕事を代わってもらうために雇ったそうだ。
本来ならば、アキエの仕事だったことをどうしてビョークがやっているかといえば、暇つぶしのようなものらしい。
そしてこう付け加えておこう、その話の半分以上は嘘で構成されているのがセスにはわかっていたと。
帰り道にブティックに寄ってビョークが服を買ってくれた。セスの服は破損が激しかったので、仕立て屋に出しているそうだ。
ビョークのぶかぶかのコートだけを着ていたセスにはありがたかった。
ビョークはアルカロイドの一等地にある大きなホテルのメゾネットルームをとった。
「あの家には戻らないの?」
「あの家にはベッドがひとつしかないっしょ? 俺と寝るのは安全でもこっちのアキエは危ないからだめ」
「ビョーク、お前俺の家でセスと何やってたんだ?」
「何もしてねぇっての。お前が邪推しているような類のことは何も。ほら、興奮しすぎるとセスが怯えるでしょー? とりあえず落ち着け。俺の指は何本だ?」
「五本」
「足と手いれると二十本でした」
ルームサービスの珈琲を飲んだビョークの脳が少しだけ活性化したようだった。
遅めのブランチを食べながら、セスはこんなに美味しいものがテールにあるのだと味わった。
卵とほうれん草のココットをよく味わって食べていると、アキエが笑う。
「おかわりはどれだけでもしていいぞ。このビョークって奴は、性格は冷たいが懐はあったかいんだ」
「そうそうおにいさんは懐だけはいつもあったかいの」
「これ、なんて言うの?」
「フロマージュ・ルーのアボカドとのサラッド」
「よくわかんない」
ビョークの言ったそのフロマージュという言葉がチーズだということさえわからなかった。隣からアキエが説明を端折って言った。
「サラダだ」
「よくわかった」
よくわからないけれどサラダということだけはわかった。
ビョークはその受け答えにやや呆れたようだったが、セスがそれで納得するようだったのでそれ以上は何も言わなかった。
ひととおり食事を終えると広いリビングのソファにどっかりと座ってアキエは口を開いた。
「そんで、セスをすぐに連れて行かないのには理由があるんだろう?」
「まぁ理由ってほどのもんでもねぇんだけど」
筋張った手を膝の上で組みながらビョークは前に体を乗り出した。少しだけ口の端を歪めて
「帰る前にセスに悪さした奴らに落とし前つけていこうかなーって」
「悪さ?」
曖昧にぼかしたところを突っ込まれて、ビョークは一瞬だけセスを見て、もう一度ぼかすことにしたらしい。
「ボコられた」
「こんなかわいい子供を誰が?」
「いやかわいいとかはどうでもいいんだ。とりあえずどんな奴だったかここの殺気丸出しのお兄ちゃんに話してごらん。きっと殺しに行くから」
殺すとか殺さないとか言っている人間に本当のことを言っていいものかセスは迷ったが、隠す義理もないので正直に話すことにした。
「親に渡されたチケットだけでアルカロイドに来たけれど、仕事もなかったし、住むところも知り合いも食べ物もなかったからあてもなく歩いていたんだ」
「そうしたら後ろから通行人に殴られたと?」
「違うよ。そうしたら巡回していた軍人がやってきたんだ」
「その軍人が殴ったのか?」
「アキエ、少し黙ってろ」
先を急ぐアキエにビョークが釘を刺した。セスはしどろもどろに説明を続ける。
「親に『軍部にだけは捕まるな』って言われていたから、咄嗟に脇道に入ったんだけど裏路地に出たと同時に数人に囲まれてそこの一番偉そうな男の人に――」
「――犯されたんだ」
「……ビョーク、お前は俺にさっき殴られたって言ったよな?」
「先にこれを教えたらきっとアルカロイド中の男をとりあえず刺してまわるだろう。お前は俺より見境のない男だ。とりあえず刺したら殺すところまでやっとけ、そうすれば刑は軽くなる」
ヘサ育ちのセスの感覚でもビョークとアキエの会話はトンでいると思った。
「そんでーどんな奴だったわけ? 暗いつってもお前なら見えるんだろ?」
セスの目は夜でもあるだけ採光して、それができなければ赤外線だけでものを捉えることができる。
「二十代半ばの、黒髪で、目がぎらぎらしてて……」
「ビョークか!」
「アキエだな」
同じ顔をした二人が同時に相手を名指しして沈黙した。言いがかりであたりの雰囲気が険悪になった。
セスは二人の誤解を解くために説明を追加した。
「飛行竜に似ているんだけどちょっと違う、鱗のある生き物の刺青が腕から手の甲にかけてあって、手の皮はビョークなんかよりもっと硬かった。口を塞いだ右手の中指にマメがあって、口からお酒の臭いがした。脳内のドーパミンとセロトニンの分泌量が通常よりも多く、アルコールを摂取した時間から二十分以内だと思う。ミクロゾーム・エタノール酸化系の量の関係から見てもたぶん普段から大量の酒を摂取している……」
「ほら、俺だったら口から珈琲臭がするはずだろうが」
「それだったら俺ならばまずムードを大切にしてだな、路上と言わず自宅まで引きずり込んでそれからじっくりと楽しむさ。むしろランプをつけて苦痛に歪む顔を見なきゃ燃えるもんも燃えないしタ――」
アキエが何か言いかけた瞬間、ビョークが近くにあったゴツゴツしたガラスの灰皿で彼の顎を強打した。ビョークは冷ややかな軽蔑しきった目で一言。
「変態」
「なんだよ、お前にダメ出しされる覚えはねぇっての! ほっとけよ。どうでもよくないことに顎って急所なんだぞ。下手すると脳震盪起こして死ぬんだぞ! 俺が死ぬと悲しいだろ? 影武者いなくなると色々と困るだろ?」
「悲しくないし、寧ろ影武者が悪評立てるのを考えれば喜ばしい」
「影武者よか本物の悪評のほうがひどいんじゃあねぇの? クリュウもエンジュも俺が来ると歓迎してくれるぞ」
「それはお前を歓迎しているんじゃなく、俺がいなくなることによってもたらされる心の平和を歓迎しているわけ。幸せな勘違いするなひとりメリーゴーランド野郎」
セスは誰もいないメリーゴーランドで一人だけ幸せそうにくるくる回っているアキエを想像した。たしかにおめでたいイメージではある。
ビョークが灰皿をテーブルに置きなおしてからまとめに入った。
「竜の刺青したアル中の男で中指にマメがあったってことはきっと頭や外見はいらない力仕事系だろうな。セス、月はどの高さにあった?」
「四十五度以下だった」
「今の時期、南中が何時だかわかんねぇけど単純に考えて二十一時以前に酒を飲み始めた奴を片っ端から探せばそのうち見つかるな」
「そのうちっていつだよ? 今日明日くらいに見つけねぇと酒場の奴だって忘れるだろうがよ」
「じゃあ今日明日のうちに見つけるしかないな」
「アルカロイドの広さ知っているか? 自宅で飲んでいた場合は目撃者はなしだ」
「見つかんなかった時は片っ端から刺していきゃいいじゃねぇか。そのうち当たるだろうよ」
「結局俺とお前の差ってどこだ!?」
アキエに聞かれて迷うことなくビョークはこめかみを指差した。
「本人達にしか認識できない微妙なイカレ具合の差異、それだけだ。他人から見たら俺たちなんてほぼ同類だろ? 酩酊状態で長時間歩いていれば誰かの目にとまるし、あまり目にとまらなかったならば近場からってことだ。あとはお前のほうが詳しいんじゃねぇの?」
「対象物が固定されている場合は外側から螺旋を徐々に小さくしていくけどこの場合はどこにいるのかわからないから現場から螺旋状に大きくしていくべきだろうな」
「じゃあ俺は内側から調べるからお前は外側からってことで。セスはアキエについていけ」
「僕……ビョークとがいい」
なんとなくアキエという存在が怖くてセスはそう言ったが、ビョークに却下された。
「アキエは少年と地球に優しい殺人鬼だから安心しろ。七時の夕食まで各自持ち場へ」
◆◇◆◇
「まんまと嵌められた」
赤い×印のついた地図を持ったままアキエは固まった。
セスが不思議そうに鸚鵡返しに聞く。
「はめられたって?」
「ビョークに。だって外から歩くのと中から歩くのじゃ絶対中から歩くほうが楽に決まっているじゃないか! どさくさに紛れて楽しやがってあいつ!」
ふと横を見ると、目立たないようにニット帽子とカラーコンタクトをつけた、セスの茶色い目がこちらを見ている。
サボらないようにこんなものまでつけてきて……とアキエは舌打ちした。
「でもどうやって探すつもりなの?」
「ホームレス・ネットワークを使うんだよ。ビョークの奴はどうせ軍部を動かすんだろう」
「ビョークは軍に知り合いでもいるの?」
「知り合いなんてのはね、お金をちょっと渡せばこの街ではすぐできるんだよ。あいつは犬をからかうのが好きだから、幾ら金を渡すと軍服脱いでパンツ一丁で帰ってくれるかとかそんなことばっかりやっている」
「幾らでやってくれるの?」
「子供はすぐに実験したがるから教えない。大人のおちょくりかたは大人になってから覚えなさい」
ふとアキエは足元を見た。上機嫌に通り過ぎていく犬を横目にセスに聞く。
「今あの犬、俺にひっかけていったか?」
「片足あげかけたけど途中で気がかわったみたい」
「よかった。これ俺の一張羅スーツなんだよ」
ほっと胸を撫で下ろしたところに頭に何か降ってきた。
「なんか雨降ってきたな」
「鳩が糞していったよ。今度は本当」
「畜生! 料理してやる、勝負しやがれ!」
怒り狂うアキエの靴に何かべたっと付着したものがあった。今度は唾である。
陽気な声がした。
「にいちゃんにいちゃーん、靴が汚れているよ?」
「いい男が台無しだね。靴磨いてやるから金くれよ」
数人の若者に囲まれた。アキエが不機嫌そうになにかを言おうとした瞬間、セスに服の裾を引っ張られて彼を振り返った。その怯えた視線をたどれば、竜の刺青をした男がいた。
◆◇◆◇
「なんつーか竜の刺青しているんだって。そんでもって酒くせぇの。黒髪で、典型的なプロレタリアート」
「典型的な労働階級者って言われましても、たくさんいますからねぇ」
「そこんところ思い出してちょうだいよ。糖分とか摂るといいらしいからこれでケーキでも買ってくれば?」
銀粒を渡されて少しだけ思い出しかける警備兵。ケーキなんて、月に一番近いと言われているアルカロイドでさえ、一般人は特別な日にしか食べられない。
「ケーキってうちの子供が好きなんですよね。うちの子供にも買っていってあげたいんですが……」
「なるほどたしかに。もう一粒やるよ」
「実はカミさんも好きでして……」
「カミさんと言わず死んだおばあさんの仏前にも供えてやれよ」
「死んでいませんがもらっておきます」
てきとうに銀粒をばらばらと男の手に握らせた。その感触を確かめさせたまま手渡さないでおく。しっとりとした絹のような掌を重ねたまま、にっこりと頬笑み、ビョークは訊ねた。
「……思い出しそうか?」
「ええと……」
思い出せない、しかし金はほしい。そんな揺れに揺れ動く警備兵の胸は男だから当然Aカップ以下、あまり揺れ動かないけれど欲は激しく揺れ動く。
遠くのほうで警笛がピーピー鳴るのが聞こえた。
そちらのほうを気にする警備兵。
「なんだ?」
「軍人さん、あっちのほうで殺生沙汰が起きているらしいよ」
ビョークはその言葉になんとなく嫌なものを感じる。そうしてそういう時は往々にして的中するのである。
◆◇◆◇
「セスよぉ、この刺青野郎が犯人か?」
「……よく覚えてないや」
「お前は優しい子だなあ。庇うこたぁねえんだよ、こいつはお前のことなんてなんも考えちゃいないんだ」
刺青を確認した直後のアキエはかなり速かった。
まず挨拶がわりに手前の男の鼻をへし折ると、そのまま反撃する隙を与えずあっと言う間にそこにいた人間を沈めた。
速すぎてよくわからなかったが、その順番のどこかで刺青の男も巻き込まれていた。
蹲った男に近づいて髪を引っ張り持ち上げるとビョークそっくりのギラギラした暗い目でその男を覗き込んだ。
セスにはこの男の恐怖もびりびりと伝わってきたが、それよりもこの深閑とした中に潜む、不穏な何かが自分の全神経を粟立たせた。
この刺青を入れた男が犯人だと言えばきっとこの男を殺すのだろうということは疑う余地もなかった。
ビョークが「きっと殺しに行くから」という言葉が本当だったということが、今自分の言葉ひとつで証明されようとしている。
死刑宣告を出すのは自分なのだ。十三歳の少年は命の重みがわかっているつもりだった。
黙ったままのセスを見てこれ以上何か聞き出すのは無理と判断したアキエは煙草に火を点けながら
「じゃあこいつが嘘を言った時だけ俺に教えろ。あとはだんまりでもいいさ」
逆らうことができない威圧感があった。
アキエは半開きにした口から煙を吐き出してから尋問をはじめた。
「あんた、名前は?」
「……ハーヴェイ=ノルキア」
最初の問題はクリアである。続けて
「セスを知っているな?」
「し、知らないよ!」
アキエはセスを振り返った。セスは黙ったままだったがそれを見てふっと笑う。
「目は口ほどモノを言うってのは本当だな。子供って正直でいいねー、とりあえずペナルティ」
ジュッ……とたんぱく質が焦げる音がして男の瞼が焼ける。反射的に瞑ったからこそ直接目のダメージは庇えたものの、瞼を通して熱の伝わった目はそれでもダメージを受けているはずだ。
セスは思わず目をそらした。
「じゃーさくさく答えてちょうだい。昨晩セスを襲ったか?」
「……ああ」
「そーかそーか。どうして襲ったのか言ってみな?」
「何も知らなさそうなガキが裏路地に入ってきたからちょっとからかおうと思って、調子乗りすぎたんだ。あからさまにこの土地の人間じゃなかったから……こいつならばれないだろうと思って」
「誰でもよかったってぇことじゃなくて?」
恐る恐る頷く男の怯える目を冷ややかに蔑視しているアキエは、口調も表情も視線も何もかもがビョークと同じだった。
「んじゃー最期に質問するけどさ……」
“最後”ではなく“最期”とアキエは発音した。
「再来年にはアルカロイドの法律が改定されて、強姦が殺人罪と同じ重さになるって知っているか? 知らなかったら知っている前提で考えてみてちょうだいよ。俺はこの法律に関しては反対なんだ。理由はわかるよな? 二年後の昨日だったらお前はセスを口封じのために殺していたよな?」
この質問には男は答えなかったが、セスはどうしてこんなにアキエが怒っているのか初めてわかった。もしこれが二年後だったら、自分はもうここには存在しないのだ。
それが真実なのは男の鼓動が一段と高くなって、また静かにもどっていく図星を突かれた時の心拍数が証明していた。
そんなセスの表情をまた、アキエも見ていた。
「訊きたかったことはこれで全てだ。もういいや」
ぐっと首を握った右腕に力を篭める。苦しさのあまりに必死にもがく男の右手にはマメがあった。
警笛が鳴り響いて警備兵が駆けつけてくる。
「そこのお前、殺人未遂で逮捕する!」
「その男から手を離したまえ」
「あー、うるせぇのが来た……」
うるさいのというのは、警備兵ではない。騒ぎを聞きつけて一緒にやってきたビョークのほうである。
◆◇◆◇
ビョークは銃を構えた包囲網を縫って中に押し入ってくるとやおらいきなりアキエの頭をはたいた。続けてよく透る声で周囲に呼びかける。
「いやーすみませんでしたね。うちのひとりメリーゴーランド野郎がとんだ粗相を。なんでしょうねぇ、根はいい奴なんですがちょっぴり怒りっぽいだけでして」
ビョークはあまり金を持ってきていないことを後悔した。
「この中の責任者、一番偉い奴と話がしたいんだけど」
「私です」
先程の警備兵が名乗り出た。
なるほどこいつは先程も金に弱そうだったからなんとかなるかもしれないと思いながら、ビョークはとりあえず財布に手を突っ込んで、金粒を鷲掴みするとこんもりと男の手に乗っけた。
今度は先程と違って周りの人間にもよく見えるように手を離す。
「事故だ」
だがさすがにこれだけの大通りで起こった殺人未遂事件を見逃すということは、法のある社会として由々しきことだ。男も首を振った。
「これは無視できません」
ザザ……
財布をひっくり返して中身を全部出した。
男の手から金と白金の粒が地面に零れ落ち、それを男は慌てて両手で落ちないようにした。ビョークは先程と同じ言葉を繰り返す。
「事故だ」
「お気持ちはわかりますが、ご親族の方でもそれは困ります」
どうやら顔がそっくりなために血縁があると思っているらしい。
考えてみれば血縁であるクリュウならば、ビョークが同じことをしでかした時、どれだけだって身代金を積むのだろう。彼はアキエためならばどこまで身代金を出すだろうか。
あれは自分の身内にはとことん甘いタイプなので部下の尻拭いのためにも金を惜しまないタイプだろう。そんな似たくないところだけ似てしまったと思いながら、ビョークは仕方なく財布から紙と胸元から万年筆を取り出した。
小切手からはみ出すくらい0をいっぱい並べて、左端に一とふってからもう一度言った。
「事故だ」
さすがにこの金額には周りの人間も、何より目の前の男が驚いている。0の数は数えていなかったが、もしかしたら月の首都、エルシュタットに豪邸が建てられるくらいの金額を書いたのかもしれない。そんな金がポスカト本部にあるかどうかはわからなかったが、とりあえずこの場だけでもしのげれば、小切手は現金化に二日以上かかるため、その間に手はどれだけでも打てると踏んだ。
どよめきが起こる中で動揺しながら警備兵は唸る。
「ですが……」
パンッ
乾いた拍手のような音がして、空にセスの目と同じ緋色が散った。
どさりと崩れ落ちる音と共に男の腹から血を吸ってどす黒くなったチャコールの袖口と、普段からアキエが愛用していた銃のぬらりと光る銃身が見えた。
「あーあ、結局スーツ汚れちまった」
男の体を突き放すとアキエは立ち上がった。
自分の今やっていることそのものが無駄だったのかと、ビョークは疲れきったようにアキエを見た。
アキエは罰が悪そうにしていたが、最後に開き直ったように言った。
「やるんだったらしっかり殺せって言ったの、お前じゃなかったか?」
そういえばそんなことを言ったような気もする。
警備兵長はビョークの手に自分の受け取った金を全部乗せて言った。
「せいぜい彼にいい弁護士をつけてやってください」
ビョークはもうただ呆然として指の間から金粒が落ちても拾う気にさえならなかった。
◆◇◆◇
留置所の面会室というのはなんともこざっぱりと殺風景なものだとセスは思った。
面会できるのは短い時間だけである。ビョークが部屋から出てきたあとはセスの番だった。血糊のついたスーツ姿ではなく、汚い色をした作業着のようなつなぎを着たアキエが、硝子を挟んだ向こう側に座っている。
アキエのは落ち着き払ったものだった。
「不自由していない?」
「さっきビョークも言ったよ。あいつはしくじったことが一度もないからな。実は不便って言うほど不便でもないんだ」
「ヘサの刑務所に入るのは恐くないの?」
「前にも入ったことがある。そん時は潜入調査だったんだが、まあヘサの監獄ってところは不思議なところでさ、貧乏人は残飯を漁らなきゃなんないってのに金さえあれば貴族様顔負けの生活も不可能じゃないわけ。金ならばビョークが送ってくれるだろうさ」
「……アキエは嘘ついている」
「そのとおり。実はヘサの将軍の愛人に手を出して、監獄行きになった。もうちょっと実のある話しよう。時間は限られているんだし」
アキエは笑った。
「あいつに隠れ家の管理は任せてある。もしあんな汚いアパートでよけりゃあ、セスが自由に使っていいよ。もうちょっと治安のいい地区に住んでもらいたいってのが本音だが……住む場所もなくうろうろされるよりは俺も安心だ」
そうしていくつか無駄話をしている間にあっさりと面会時間は終わった。
古びたアパートに戻る頃には夜が更けていた。
ほとんど何もない棚からマグカップをふたつとりだして、ひとつしかない鍋でお湯を沸かすとビョークは自慢の珈琲を淹れてくれた。
アキエもビョークもブラック派のため砂糖がなく、香り高いが苦い珈琲を口に運んだ。
「俺がお前と話す時心がけてきたことは何かわかるか?」
ふと出されたなぞなぞにセスは首を横に振った。
「肝心なところで嘘を見抜かれないことだ。馬鹿馬鹿しい意味のない嘘をいっぱいつくことで真実は隠しておき、だが本当のことを言う……これがポイントだ」
それが前置きだった。
「ヘサのマフィアからお前を探す指令がでている、これは本当だ。だが俺が依頼されたのはヘサじゃなくてアキエ。あいつはお前と同じ歳くらいの時にヘサのマフィアから逃れて山越えて、ポスカトまでやってきた。メレッサ産の一番いい薬とポスカトの温泉を使っても体から完全に麻薬を抜くのには数年かかったよ。あの顔は俺の親父が、たまたま年齢の近かった俺の顔をモデルに整形させただけで、髪の毛は染め粉だし、目もカラーコンタクト嵌めていただけ。明慧(アキエ)って名前もうちの組織に入る時のコードネームみたいなもんだ。あいつの本当の名前は……」
すべてが虚偽で塗り固められていたアキエの真実をどんどんとビョークは暴露していった。
「ソレイユ=フロンティア。お前と同じ、フロンティアの末裔だ。軍部も馬鹿じゃあないだろうから、そのうち気づくだろうさ。あいつは待っていても帰ってこない。マフィアから逃げたと思ったら、今度は軍部の道具にされるってわけだ。次に逃げたとしても脳内に埋めたチップが反応して……」
やりきれないと言った具合にビョークは呟いた。
「アキエの財産は全てお前に相続すればいいとさ。財産って言っても、ちょっとずつ貯めた金と、このボロアパートくらいのものだけど、今のセスには十分だろう。アキエも言ったと思うけど、ここは捨て値で売り払ってどこか遠くに住んだほうがいい。ゼブラ平原に俺の別荘があるからそこの掃除してくれるとそりゃあそれで助かるんだけどな。あそこは白い砂浜とペンギンが共存する謎のリゾートだ。色々な動物がいるがコモドドラゴンっていうのはドラゴンとか言いつつ、肉食だから絶対に近づくな。あとワニとかいうのもだめだ。とりあえず鱗のびっしり生えているものを見かけたら逃げろ。奴らは胴体が長いからジグザグに逃げるのが生き延びる秘訣だ」
「……ビョークについていったらだめかな?」
思い切って聞いてみたが、反応はいつもどおり乏しかった。
「うちは俺が最年少みたいなものだから、誰も遊んでくれるやつはいねぇよ?」
「ゼブラ平原で僕と遊んでくれるのってコモドドラゴンとかワニのこと?」
「…………」
「やっぱり迷惑かな……」
がっかりしたように呟くセスを見てビョークは呟いた。
「子供らしく『絶対ついていくんだ』とか言わないあたりが同じフロンティア一族でも違うもんなのね」
「絶っ対、ついていく!」
「それじゃあしかたがない。明日の便で帰るぞ。わかったら寝ろ」
「やった!」
セスのここ数日暗かった顔がぱっと明るく晴れわたった。
素直にベッドへと走っていくセスを見ながら、ビョークは名前を呼ぶ。
「セス……」
「何?」
「アキエは俺なんかよりよっぽど優しい男だったろ?」
緋色の目の中では金色に輝く文字が躍った。様々なビョークの中に流れる情報を汲み取りながらセスは答える。
「どっちも照れ屋で、少しネジがとんでて、よく似ている」
問いの答えとしてはトンチンカンではあったが、それはたぶん正解だった。
◆◇◆◇
数日後
「クリュウ、いい加減に決めてちょうだい。仕事は他にもあるんだから」
明けても暮れても辞書のページをめくる音だけが淡々と聞こえるクリュウの部屋で、苛々したようにカエデが言った。
てきとうに抜き出した文字が乱雑に並ぶ紙を眺めながらクリュウがカエデに答える。
「だってアキエの忘れ形見みたいなものなんだろう? 変な名前つけたらきっとあいつ怒るから、ここは慎重に……」
「ヘサのどこにいるかわからない人間にどうやって伝えるってぇの? てきとうでいいんだよてきとうでさー」
「お前は何事もてきとうにやりすぎなんだ、ビョーク」
辞書のページをめくりながら弟を注意するクリュウと、そんなことにはまったく頓着しない愚弟のいつもどおりの会話だ。
「あんたは何に対しても几帳面すぎ。連想ゲーム、アキエといったら〜……カエデ」
「アキエといったらキモい。キモいといったら〜……エンジュ」
「……キモいといったらアキエ」
「エンジュ、戻してどうするの?」
「そうだいくらキモいからって一度出た単語は使うの禁止だ、エンジュ」
エンジュははあ、とため息をついた。
「カエデさんもビョークも人の名前を連想ゲームで決めるなんてアバウトなことはやめましょうよ。絶対あなたたちまともな連想しないんだから、セスが可哀想です。既にキモいとか言ってアキエも可哀想です」
「几帳面がもう一人いやがった」
カエデが「いやだいやだ」と声が聞こえてきそうな視線でこちらを見る。
「カエデー、あいつ絶対親父につけられたエンジュって名前に恨みもってるよ」
猿と鷲(わし)と書いてエンジュ。槐(エンジュ)という字もあるというのに、何故こんな画数の多い名前をつけられたのかよくわからない。
好き好きに言うカエデとビョークにエンジュは疲れたようにため息をついた。振り返れば半地下の天窓からもう朝日が差しかけている。
「ビョーク、アキエの本名のソレイユって、たしか太陽って意味でしたよね?」
「そうだったっけ?」
「しっかりしてくださいよ。僕は言語系弱いの知っているでしょう」
エンジュが半眼で低くうめく。面倒くさそうにビョークが「そうだ」と頷いた。
「フロンティアのほうはどんな意味なんですか?」
「未開の地と開拓地の境界線って意味」
「じゃあ……」
日の出じゃあ語呂が悪い。貧困なボキャブラリを捻出しているうちにクリュウがピンと閃いたようにぼそっと言った。
「暁(アカツキ)なんかいいと思わないか?」
カエデとビョークが顔を見合わせて、エンジュを見て、クリュウを見た。
「日の出よか幾分かマシなんじゃない?」
「日の出よりかはなぁ〜」
「なんであなたたちは僕の心を読んでいるんですか!? “フロンティアの眼”でも持っているんですか!」
「なくたってエンジュの馬鹿みたいにストレートな連想なんて当てられるよねー? ビョーク」
「当てられるよなー? カエデ」
「なんなんですか、いつからあなたたちそんなに仲良くなったんですか。もういいよ、上司は初めてパパになる人みたいにネーミング辞典睨んでて、同僚は意地悪なこんな職場辞めてやるんだ!」
辞めてやるとエンジュが言い出す時には決まって切り返さなければいけない形式があった。迷うことなく三人が同じタイミングでカップを掲げる。
「エンジュ、珈琲持って来いや」
「私にも」
「すまないがエンジュ、深煎り珈琲を持ってきてくれないか」
「知らないよ、あんたら勝手に注いでくればいいじゃないか!」
万年雑用係が三人のカップを毟り取ると上のカフェまで階段を一段飛ばしで駆け上がっていった。
辞めてやるなんて言葉は珈琲を淹れている間にどうでもよくなってきて、惰性でまた雑用を押し付けられるのがエンジュである。なんだかもう雑用を言い渡されると反射的に動くように脳内プログラムされているとしか思えない。
◆◇◆◇
オレンジ色のやわらかな光が寝不足の人間も眠っている人間も等しく照らしていた。
その美しい光をあらわす言葉がたくさんあった。何の思い付きだかビョークが提案する。
「語彙が一番貧困だった奴が今日の三人分の仕事やるってことで。暁って文字を使った言葉をどんどんあげていくゲームな。暁。はい、カエデ」
「暁更(ぎょうこう)はい、クリュウ」
「暁鶏(ぎょうけい)。……ビョーク」
「暁降(あかときくた)ち。どういう意味か知ってるか? カエデ」
およそ普段は使わない単語から潰していく三人だったが、辞書の“暁”のページを開いたままのクリュウが最強だったのは言うまでもないことだった。