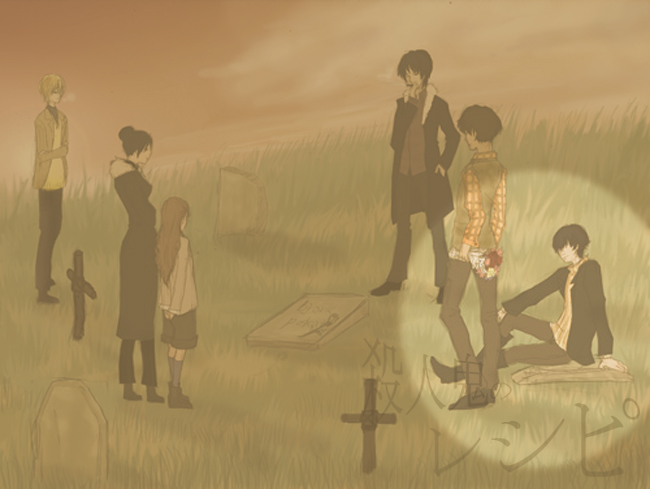
05 「いるべき場所へ」
ゴンザレス准将は現在ヘサに来ていた。
「なんでヘサの将軍が私たちを呼ぶんですか?」
そう言ったのはフレデリカ=エーディンリッヒ、ジオ軍部の諜報員のひとりだ。
「あいつら金のためならなんでもしちゃう品のない連中だから好きじゃあないんですけどー!」
ヘサの市場はともかく人が多い。少し前を歩いているゴンザレスの背中を追いかけながら、大声で文句を言っている。そりゃあそうだ、ゴンザレスだってできることならばヘサの軍部に関わりたくない。
「フレッド、上層部には底辺の部下にとってよくわからない、色々な事情があるのだよ」
主に保守的な。と胸中付け足す。
フレデリカは人の波の中をやっとゴンザレスに追いつき、ゴンザレスを見上げた。
「私ぃ、あいつら〜、嫌いっていうか〜なんていうか〜」
「手短に言え」
「つまり〜あいつらのために〜、命張った仕事とか〜したくないっていうか〜なんていうか〜」
「ああ、わかったわかった」
無視して間延びした口調を続けるフレデリカにゴンザレスは黙れと言った。
フレデリカが苛々しているのも当然だ。この依頼でフレデリカを連れて行けという指示は、つまり彼女が中心に動くことになるという意味だ。
「他人の〜組織の〜ために〜、張る〜、命も〜、義理も〜、ないっていうか〜」
「言いたいことはわかる」
フレデリカの苛々作戦。これで動揺して相手の将軍に失礼なことでも言おうものなら、商談は不成立。彼女の思いのままだ。
「ひとつ何か、上層部に進言してやる。だから今回は黙って仕事してくれ」
「わあ、本当? じゃあ今すぐヘサとの協定を切ってもらってください」
「本当にお前という奴は……」
上司が困るのを喜んでいるフレデリカを黙らせるのはもうよすことにした。
***
ゴンザレスは一昨日、今回の指令が書かれた書面を受け取った。
今ではシステム化されすぎて、議員たちが直接軍部に出向くこともない。紙切れ一枚で命を捨ててこいという、無慈悲で能率重視のシステムだ。
直接の内容はヘサへ行ってから聞くようにということと、連れて行く部下はフレデリカひとりという指示。
「よかったな。死ぬ部下は多くてもひとりだ」
アシッド大佐が皮肉を言った。ゴンザレスは眉をひそめて、アシッドを睨み返す。
「アシッド、お前はフレッドが嫌いなのか?」
「あの女見ていると苛々するけど、嫌いじゃあないよ」
アシッドは間を置いて、低い声で言う。
「大嫌いだ」
そして去っていった。ゴンザレスはため息をつく。アシッドはいい奴なのだが、フレデリカを敵視しすぎなのだ。
「准将〜。さっき酸性チンカス野郎に『そろそろ死ね』って言われました」
へらへら笑いながらフレデリカが近づいてくる。ゴンザレスはため息をついて、言った。
「アシッドがお前を嫌っている理由わかるか?」
「いえ、全然」
「お前があいつのことをチンカス野郎とか言うのがいけないんだ」
ジオの人間は下品な言葉を使う人間をともかく嫌う。そういうのは文化的ではないと言われるのだ。
「あいつが先にこっちに嫌味言ってくるからですよ。あっちの味方なんですか?」
「わかってないのはお前だと思うが? あいつが部下のほとんどを失ったときに、『わあ、司令官誰だったんですか?』とか言ったりして。無神経にもほどがある」
当然、アシッドが司令官だ。フレデリカはつまらなさそうに口を尖らせる。
「私は、司令官とか、上層部とか、大嫌い。末端の命のことなんて全然考えてないんだもの」
「それも勘違いだ。アシッドはいつでも最前線の人間のことを考えている。あいつのことはもういい、お前はもう少し、敵を作らないようにする練習をしろ」
フレデリカは人を怒らせることにだけは長けている。
「さて、今回の仕事の件だが。ヘサの将軍直々のお願いらしい。詳しい情報はあっちで聞いてこいと書いてある、が……」
「が?」
最後の言葉を鸚鵡返しに彼女が呟く。
「ただ協力してこいとは、書いてない」
「つまりは?」
「ヘサとの協定は崩したくないが、あっちが力をつけるのはよしとしていないということだ」
「協定なんて破棄すりゃいいじゃあないですか。議員たちが一番ああいう下卑た奴ら嫌いなんでしょ?」
たしかに議員たちはヘサの上層部が大嫌いだ。ゴンザレスはその質問には答えず、こう言った。
「ヘサに囚人を引き取ってもらう必要がある。ジオの国民はともかく神経質だ。脱獄した犯罪者のひとりさえ、議員の責任だと言ってくる。外国に追放してそっちで管理してもらったほうがいいだろう?」
「わあ。名づけて汚いものは外国に捨てる作戦ですね。メカポリスがテールにした仕打ちみたいです」
その昔、メカポリスは不要なゴミをテールに捨てたことがある。不要なゴミとは、危険な物質のことだ。
テールの海は酸と化し、異形の生物が増えたのもこれのせいだと言われている。
つい最近までメカポリスには鬼のような人種が住んでいると言われていた。彼らは高度な文明の廃棄物を、こちらに押し付けてくる。
しかしそんなメカポリスから、二十余年前に使者がやってきた。
彼が言うにはメカポリスは人口が増加しすぎて、もう住むところがないそうだ。そして食糧危機が酷く、困っているという。
テールの代表者たちはメカポリスの使者を追い返そうとした。
今まで散々こちらを苦しめておいて、助けてほしいとは調子に乗るのも大概にしろと。
話し合いは何日も続き、最終的に使者たちとテールの代表者の間でこういう取り決めがされた。
テールの海を浄化し、環境破壊を食い止める。それを交換条件に、テールの各都市はメカポリス人の移住を受け入れるというわけだ。
メカポリス人に人気があるのはアルカロイドとジオだ。
銀河鉄道が下りてくるアルカロイドは一番メカポリスに近い都市。当然文化のギャップも少ないため、人気がある。
一方ジオはアルカロイドのあるフールレラ大陸とは別の、砂漠しかないエレセレナ大陸ど真ん中にある魔法都市だ。
魔法というものに興味があるメカポリス人はこちらにやってくる。
事実、ジオの組織ではメカポリス人が働いている。積極的に人種の垣根を取り払うつもりで政府は働きかけた。
魔法とは、元々は魔族と呼ばれる種族のものだったが、今は混血児がほとんどだ。
純粋な魔族は反則的な能力を持っている。たとえば指を動かすだけで人間を消滅させることさえできるのだ。
ただし魔族は寿命が極端に短い。三十そこそこまで生きれば長生きしたほうだろう。彼らは自らの子供を延命させるために、積極的に人間と結婚したと言われている。
「魔族の魔は、魔界や魔物の魔じゃあないよ。魔法の魔だよ」
そうゴンザレスに説明をした、旧い友人を思い出した。彼は純粋な魔族で、そして彼のひとり娘であるフレデリカも、他の者に比べれば純魔族に近かった。
「フレッド、メカポリス人もたくさんいる職場でそういう悪口はよくない」
もう一度注意をする。幼いうちに親を亡くしたフレデリカにとって、自分は親代わりのようなものだった。躾は厳しくしなければいけない。
***
「アキエ=ポスカトの正体を探れ、と?」
「そのとおりだ」
ヘサの将軍の応接室はとても豪奢なところだった。
誰だ? そいつ。ポスカトという名前でなんとなくポスカトの人だろうと言うことはわかった。
しかし今のポスカトマフィアのリーダーはたしかクリュウ=ポスカトとかいう名前だったと思う。よくはわからないが、それの親戚だろうか。
自分の年齢で准将というのは普通のエリートの出世しかたであった。この手前に座っている男も自分と同い年くらいであろう、しかし彼は将軍である。明らかに地位が違った。
ヘサは金があればどれだけだって出世できる。囚人だって貴族のような贅沢な暮らしができるのだ。
ここの社会の腐敗した制度はジオで育った潔癖主義のゴンザレスにとっては不快だった。
「アキエ=ポスカトはもしかしたらヘサマフィアから逃げ出したソレイユ=フロンティアという少年かもしれないという情報が入った。それを確かめたいんだがね」
「はぁ……」
フロンティアという名前は聞いたことがある。ジオにもフロンティア一族の末裔が軍部に貢献しているからだ。
ゴンザレスの中では、もとはファンダリア遺跡で生活していた一族だが、あちこちからその能力を利用せんと無理矢理連れて行かれて世界中ばらばらになった可哀想な一族、という認識だ。
ゴンザレスはヘサの軍部で調べてくれりゃあいいのにと思った。
資料を渡されてそこの少年の顔写真を見て、次にアキエの顔写真を見る。
「明らかに別人物に見えるのですが……」
「整形しているのかもしれない。そこらへんは君たちのところのあの、なんて言ったかね……スレンダーな女スパイがいただろう? 彼女あたりがよくわかっているんじゃあないかね?」
「女スパイではありません。諜報員です」
女スパイに限らず、女弁護士、女教師、女裁判官……ただの単語に女とつけるだけで卑しい妄想を働かせる男の多そうなヘサではこの単語は別になんの抵抗もないのだろう。ジオではもう既に使われていない単語である。
「まぁあの諜報員に調べさせてくれないかね。なにしろ、アキエ=ポスカトは無類の女好きみたいだからね」
その淫靡めいた言葉にゴンザレスはうんざりしたように聞き返した。
「つまり彼女なら誰とでも寝られるだろうからという理由で私のほうにこの仕事を依頼されたというわけですね? わかりました、引き受けましょう」
ゴンザレスはそのまま将軍を睨みつけて言った。
「そのかわりあなたの娘をヘサの花街に売り飛ばしてもいいですか? くそったれ」
自分の部下を馬鹿にするのも大概にしろと言いたかったが、ここで喧嘩をはじめるわけにもいかず、呆気にとられている将軍の前で資料を束ねると封筒にしまいなおして立ち上がった。
「依頼はお引き受けいたします」
◆◇◆◇
ヘサの軍部に女の姿はほとんどない。ジオの男女平等の社会からかけ離れて男社会だからである。
待合室で軍服を着たまま本を読んでいたフレデリカは周囲からの視線を感じた。
この体に纏わりつくような視線にもかなり慣れたものだが、最初ジオから来た時は周りの男が気持ち悪く思えた。
しかし慣れとは不思議なもので、今は読書に支障がなければそれほど気にならないし、時折脚なんぞを組みかえて男の視線を独占するのもままおつなものと思うようになった。
「フレッド、終わったぞ」
向こうから中年に入ったばかりくらいの男が歩いてくる。自分との年齢は父と子ほども離れている、自分の上司にあたるゴンザレスだ。
「ここの空気はもう吸いたくない、外に出るぞ」
軍の本部を出ると、ゴンザレスとフレデリカはまず一番最初に煙草を咥えて火をつけた。
なぜ軍の中は禁煙なんだろうといつも思う。さんざん澱んだ空気の中から出てきてすぐに煙を吸っている自分達は肺が既に真っ黒だろう。
「それでどんな用件だったんですか? 准将」
「至極馬鹿馬鹿しい内容だったが、受けないわけにはいくまい」
「ええー」
面倒そうに眉をしかめたフレデリカに無言で資料を渡した。フレデリカは資料の入った袋の中身をチェックしはじめる。
えらく可愛らしい少年の顔やら、色っぽい男やら、ともかくそんな写真ばかりである。
「なんですか? このおびただしい数の美形どもは。ホストですか? AV男優ですか? 選んでいいんですか?」
「フレッド、それはポスカトマフィアの上層部とフロンティア一族の写真だ。そこのアキエという男について調べてほしい。あとの説明は中の資料を見て考えてくれ。それで任務だが……お前の大好きな仕事だ」
「はぁ」
「ヘサの馬鹿な男どもをちょっくらからかってこい。どれだけからかってもいいが、絶対にジオの本部が責任に問われてはいけない。あとは……」
すぱーっと煙を吐き出すとフレデリカのほうを見てゴンザレスは言った。
「決して捕まるな。生きて帰って来い。以上だ」
◆◇◆◇
毎月送られてくる金で普通の囚人よりはいい暮らしができるものの、さすがに労働を休むわけにはいかない。
配布されている作業着はアキエでさえぶかぶかで、腰のところをベルトでとめている。
大きめの服を用意して自分達で勝手に切ったりして調整すればいいという大雑把なあたりもヘサらしい。
重たい荷物を運ぶという作業を何度かくリ返して、休憩時間に入った。
他の囚人に見つからないところで一服しようと建物の裏にまわった時だった。またいつぞやのように何人かの男に囲まれた。
この前殺した竜の刺青をいれた男なんかよりもよっぽど屈強そうな男達である。
その男達が自分に対してどういう意識を向けているか、それは脳内物質を読めばわかった。
相手が喋る暇を与えることなく、体を沈めて腹に一発いれてなぎ倒す。の繰り返しであっという間にその場には沈黙が訪れた。
なんだって自分はこんな顔をしているんだろう。
もうちょっと造作の悪いつくりだったならばいちいちこんなのを殴り倒す手間もいらないのに。
そんなことを考えたが、別に今の顔が嫌いなわけではなかった。
カチッ、
ライターをつける音がした。
何時頃からそこで見ていたのだろう。ジオの軍服を着た女が階段に座って咥え煙草でこちらを見ている。
ゆるやかな茶色い巻き毛をそのままおろした、少し痩せた女だ。ノーメイクとは思えないほど目に力があり、一目で美人とわかる。
だが、彼女自身が放っている空気は軍人特有の威圧感があり、女性的というイメージはなかった。
「俺を厳罰処分にするってか?」
「いいえ。そいつら私が差し向けたの。あんたが私よりお金持ちでムカツクからちょっくらオカマ掘ってきてよって。刑期減らしてやるって言ったら喜んでいったわよ。別にあんたの面がいいからじゃあないのよ、残念だったわね」
声は幼い。やや早口でまくしたてるようにしゃべるその女にアキエは肩を竦めてみせた。
「俺は掘られる側じゃなくて掘る側なんだよ。残念だったな。俺はお前になんか悪いことしたっけ? 誰だよあんた」
「誰だっていいじゃない。でもそんなに教えてほしいなら教えてあげる、フレデリカって言うのよ。それよりあんたは何者なのよ? ソレイユ=フロンティア」
誰だ、それ。そんな表情をアキエは作る。ビョークほどではないが、とぼけるのは上手だと思っている。
フレデリカは煙草をくゆらせながら、続ける。
「別にあんたがソレイユじゃあないってんだったらそれでもいいのよ。あんたが大事にしていたあのセスって男の子は間違いなくフロンティアの血筋だし、あっちを連れてくるから」
セスという名前にアキエは少しだけ眉をひそめた。
「やってみろよ。あっちには俺が手塩にかけて育てた殺しのプロがいる。返り討ちにあってくるんだな」
「あんたが可愛がっていたビョーク=ポスカトのことだったらついでにいっしょに殺してきてあげましょうか? お土産は何がいい? オーソドックスに指? それともあの黄色人種には珍しい紫の瞳? 生首にリボンつけてあんたに送りつけたら、あんた私への復讐心とかそんなのも萎えるくらいきっと打ちのめされてそのまま軍の言いなりになったりね」
女の体の中を流れる情報が、一寸の乱れもなかったために、はったりで「やってみろよ」と言うことができなかった。
もし言ったらその場で実行しかねない、そんな空気だったからである。フレデリカは続けた。
「私、今のあんたの面嫌いじゃないけど、昔のきれいな金髪に赤い目も嫌いじゃあないのよ。愛くるしい容姿のおかげであだ名はシュガーちゃんだったらしいじゃない。あんたが誰彼構わず抱いたり殺したりするのはその時の復讐なのかしら? ヘサはマフィアも腐っているけど軍部だって十分に腐敗しているわよ。誰もあんたの可愛いセスを守ってくれる奴なんていないわ」
「……女を解体(バラ)したいと思ったのは久しぶりだな」
挑発だとわかっていても、乗るしかない。フレデリカは「ふふっ」と笑った。
「やれるもんなら殺ってごらんなさいよ。私はこの場から動くことなくあんたの指をはねることだってできるけど、あんたは私に近づかないと攻撃できないじゃあない」
ジオの軍人のほとんどは、魔法が使える。フレデリカの能力が何なのかはわからなかったが、魔法が発動する前に勝負をつける必要がありそうだ。
アキエは地面を蹴ると一気に距離を縮めた。フレデリカはまだ印を結んでいない。あともう少しで首に手をかけられる。かけたら力を篭めるだけで折れるはずだ。
目前まで迫って、ぴたりとそこから進めなくなった。どういうことだ? と思っているアキエの口に自分が吸っていた煙草を押し込んでフレデリカは言う。
「空間をずらしておいて正解だった。遺失技術の継承者はあなただけじゃあないってことよ。さっきも言ったけど、あんたじゃあなくたっていいの。セスのほうが可愛いし抵抗もしないだろうし。でもそこをあんたで我慢してやるって私が進言してやるんだからありがたく思いなさいよ。ソレイユ……それであなたは引き受けてくれるの? どうなのよ?」
フレデリカはにっこりと笑う。答えはどっちでもいいのよ? と。
引き受けないわけにはいかないじゃあないか。大事な弟分二人の人生を人質にとられているのだから。
◆◇◆◇
数日後、頭部の皮を剥がして中に起爆チップを植え込むという手術が行われた。
アキエがここから脱出したときに他の組織にその能力がわたらないように、そうするのだ。
これでアキエはここのヘサから出ることができなくなった。一生ここの軍部の道具として使われるのである。通常ならば。
手術が終わるのも待たずその場を去ろうとしたとき、後ろから声をかけられた。ゴンザレスの嫌っている将軍である。
「いつもながら鮮やかな手捌きだったな。どんなわざを使ってあの男を陥落させたのだね?」
ぽっちゃりとした頬で笑う男の顔が嫌でフレデリカは微笑むだけにした。
今時、フロンティア一族に協力を仰ぐのに、麻薬やら機械やらを使わなきゃいけないこの原始的な、しかしもっとも人間に近い形とも言える己の利益に忠実なヘサの軍部。
「あーあ、やんなっちゃうなあ」
フレデリカは宿舎に戻ると、布団の上に倒れこんだ。
ふう、とため息をついて枕を抱える。体を丸めると少しだけ気分が落ち着いた。
指令の内容は頭の中に記憶してある。ソレイユの正体を暴き、ヘサの軍部への協力を要請するところまでが自分の仕事だ。そこから先は自由におちょくっていいとは言われているが、証拠を残さずにやるというのはけっこう難しい。それとあとひとつ、機密事項があるがこれはもうちょっと時間を置く必要があった。
「暇だし、ソレイユのことでもおちょくりに行こうかな……」
ソレイユは可哀想な男だ。フロンティアの眼の所持者というだけで軍に利用されるのだから。
「別に私にとっちゃどうでもいいけど」
口に出してそう呟いてみる。本当は嘘だった。どうでもいいことではない。だけど口に出して自分に言い聞かせないと、誰かの人生を台無しにした重みに勝てそうもない。
「弱いな、私……」
諜報員を始めてかれこれ何年になるだろうか。いまだに人の心が忘れられない。フレデリカは十分人間らしかった。
◆◇◆◇
ヘサの軍服を着たアキエはすごく不機嫌だった。
鏡で後頭部を見ると黒い髪の影からちらちらと赤いチップの光が見える。先程とまったく変わり映えはしないが、埋め込まれているのはたしかのようだ。
新しい部屋として割り当てられたところは、自分が今まで使っていた囚人の部屋よりも簡素なもので、なんとなく普段使っていた自分の部屋を思わせるインテリアだった。
そのパイプベッドで煙草を吸いながら待っていた女にアキエは舌打ちをする。
「まだいやがったのか?」
「ジオからまだ新しい命令がでてないもの。もうちょっとここであんたをおちょくっていこうかと思って」
最初に受けた印象よりも幾分か歳相応の雰囲気のフレデリカにアキエは顔を歪める。
どうやら彼女はジオの軍部に所属しているらしい。首元のタイを緩めつつ女を見ていると、フレデリカは暇そうに言った。
「あなた欲求不満そうね。特別に進言して花町に連れて行ってあげましょうか?」
「てめぇとヤらせろよ、売女(ばいた)が」
女の中を流れる情報にはいつでも乱れがない。規則正しい脈と呼吸と、あと時折煙草のニコチンによって肺の酸素が脳に運ばれない時のみ、少し働きが鈍っているようだ。
ふと周囲を見渡す。
おそらくこの部屋にはきっとプライバシーの概念などないのだろう。ざっと見渡しただけでもカメラやら盗聴器やらが幾つかセットしてあるのがわかった。アキエは聞いた。
「その花町に行くってやつ……許可とれそうか?」
「とれるんじゃあない? 事務所に外出届『歓楽街まで女を買いに』って書いとけば。行ってみましょうか?」
灰皿に煙草を擦り付けて消したあとに立ち上がるフレデリカの後ろについて歩き始めた。
まだ活動時間のために宿舎のほうは、この時間には人があまりいない。
スノースタリン大陸は北にあるため、朝が早く、夜も早い。
外は既に暗く、今日は月もあがっていない。先を歩く女の吐息も僅かに白い。
柱の翳が濃厚に落ちているところに差し掛かったあたりで、アキエは前を歩くフレデリカの口を手で塞いだ。そのまま近くにあった部屋へと引きずり込む。
手錠があればそれが一番手っ取り早かったが、生憎とまだ支給されていなかったので首に巻いていたタイを使って手首を縛り上げた。背中から体をぴったりと添わせた状態で囁く。
「ジオの軍人が自分の特殊能力に頼りすぎるってのは本当らしいな。お前は空間をいじれるもんだから普段の警戒を怠りすぎだ。いざとなったらいつでも逃げられると思っているようだが……残念だったな。お前は印が結べなければ逃げることはできない、つまりこうしておけばただの人間ってわけだ」
ぐっ、と手首の腱を無理矢理引き伸ばすと、フレデリカの顔が苦痛に歪む。初めて見る女の視床下部への指令を感じ取りながら赤い目が暗い色を湛えた。
左側から這わせた手が太腿を撫で上げてから臀部で止まる。
「俺の薬当番が休んだ日に来た男は最悪な奴で、ここに突っ込んでこう言ったんだ。『キスして赦しを請え』ってな。それが毎日のように続いて普段の奴が復帰した日も、俺は部屋に来る足音に怯えていた……お前にはわかるか? 俺がたった一人の肉親のセスを守りたかった気持ちと守りきれなかったときの気持ちと、お前がセスを人質にとったときの気持ちが」
アキエは続ける。
「十四のときにもう一度その最悪の男が俺の薬当番になった。その日、俺は初めて殺しをしてから逃げ出したんだ。死んだってあそこには二度と戻らないと決めて。……ポスカトはいい場所だ。セスだってしばらく暮らしていれば俺のこともヘサのこともみんな忘れられる。忘れられなくても忘れるふりはできる。……そのためだったら俺は何でもするさ。お前はジオの出身だって言ったな?」
フレデリカが嫌な予感を察知したようだった。少なくとも、彼女の脳内は何か不穏さを察知していた。
「お前を素っ裸にして指を全部切り落とした状態で吊るし上げとくってのどうだ? その死体から精液でも見つかれば完璧だ。ジオのお偉方の中じゃ女も何人かいる、奴らが怒ればジオとヘサの戦争のはじまりだな。お前一人を殺すだけで今まで人を殺したこともない奴らが皆武器を取って殺しあうんだぜ?」
特殊な眼なんてもっていなくても、アキエが本気だったことはわかっただろう。しかし最初に腕を捻り上げた時から、アキエが喋りつづけるにつれてフレデリカの心拍数は落ち着いていった。面白くない、表面上は体よく繕っている人間の内面が見えるからこの眼は面白いのだ。
「ソレイユ、あんたの言っていること、半分も実現しないわよ?」
鼻で笑い飛ばしたフレデリカのそれがはったりではないことは、見ればわかった。
「私がなんで諜報員なんてやっていると思うわけ? 死体が見つからないからよ。時空間を司る魔族が死ねばその死体は残らない。やってみる? 嘘だと思うならとっとと犯って殺してみなさいよ、ちんたらしてるとあんたのは小さくてやったかどうかもわかんなかったってあの世で言いふらすわよ!」
そこまで言ったあと、アキエが何もしていないのにドクンとひときわ大きく脈打つ、心臓。
フレデリカの体が崩れた。その体を支えた状態で腕の中の女を見ていると苦しそうに呼吸が荒い。先程までの落ち着き払った様子が微塵も見られない。
「……お前、病気なんだな」
死体も残らないと言った女の言葉を思い出す。
胸が絞めつけられ、今すぐ胸を押さえたいのに腕が動かないフレデリカが、肩ごと喘いでいる。
きっとあと数年もしないうちに死ぬだろう。
「……なんだっていいじゃない。病人は殺さないっての?」
殺す様子が見られないアキエに、ぜえ、と呼吸をしながらフレデリカが言う。
「お前が死んで悲しむ奴はいねぇの?」
「そんな奴……とっくにみんな死んだわよ」
みんなというのは、家族や友達以外にも仲間もみんな死んだという意味だろう。諜報員なんて仕事を続けていて長く生きられる人間はごく僅かしかいない。
アキエはシガレットケースの中から昔使っていた麻薬を取り出した。薬が必要なくなった頃に、ビョークが「もう必要ないだろうが…」と返してくれたものだ。
フレデリカの口の中に押し込んで、彼女の苦痛が和らぐのを待つ。
「こんな仕事、なんで続けているんだよ?」
仲間が死ぬのを見たり、自分が誰かを殺したり……こんな難儀な仕事をどうして続けているのだろう。
これが遺失技術を受け継いだ者の宿命だというのだろうか。
「怖いからよ。痛かったり辛かったりしないと絶望は忘れられないじゃない」
フレデリカが静かに呟いた。
「たとえ傷つけあうだけだとしても私はそれだけで救われているの」
翌日、フレデリカはアキエの部屋にはこなかった。数日してもまったく姿をあらわさなかった。
「あの女はどうした?」
近くにいた自白担当の軍人に訊ねてみた。
体は大丈夫なのか、という意味で「どうした」と聞いたのだが、白衣を着た軍人は違う意味で捉えたらしい。
「ジオへ帰りましたよ」
「……そうか」
帰る前に薬を渡しておけばよかったかもしれない。
部屋に戻ればそこに彼女が吸っていた煙草が置いてあった。忘れていったものだ。
それに火を点けて肺に満たす。吸っている煙草も、同じメーカーだった。
どう転んでも幸せに生きられないあたりも、今まで器用に生きてきたつもりでいるあたりも自分とどこか似ていると思った。
そんな暮らしを一ヶ月も続けた。
いい加減ヘサの軍部での生活にも慣れた。
毎日淡々と尋問を繰り返す軍人に合わせてホログラフのように「嘘・本当」と繰り返すだけの単調な毎日だ。
いかに“アキエ”と呼ばれて過ごしていた時間が自分にとって貴重なものだったのかがわかった。あの時間を忘れていたならば、自分は今ここで過ごすことができただろうか。誰も守るべき人も大切な人もいない状態で、自分はここにいただろうか。
スノースタリン大陸は夏がなければ冬を越せない。自分にとっての夏はアキエと呼ばれていた頃だ。
その日、部屋に帰る時……やけに静かだと思った。
あまりにも静謐とした空気にまるで時が止まったのかと思った。足音さえ響かない。
自室の電気をつけようとしてスイッチを入れても火花どころか、まったく音さえしなかった。自分の眼が通常の人間の眼だったならば、ここで何が起きているかさえわからなかっただろう。
「おまえ……」
細く昇る煙草の紫煙を見ながらアキエは言った。
「ジオへ帰ったんじゃあなかったのか?」
ベッドの上のフレデリカが顔をあげる。隣で椅子に座って待っていた中年の男も同じジオの軍服を着ていた。
フレデリカが待ちくたびれた様子で肩をこきこきと鳴らした。
「あんたを逃がしにきたのよ」
「俺を……?」
アキエは首を捻る。この会話はどこかに洩れたりしないのだろうか。
「心配せずとも時間軸をいじってある。この会話は外部には洩れない」
「そういうこと。あ、こっちの人はね、気になっていると思うけどゴンザ……」
「私のことはどうでもいい。話の続きだが……」
ゴンザ……なんだろう。気になるところで途切れてしまった。
どこかぷっつんしたような目の男は、もしかしたら自分やビョークなんかよりも性質が悪いかもしれない。何しろ、このフレデリカを部下に持っているくらいなのだから。
「ジオの軍部が関わったことは今後も伏せておいてくれたまえ。たとえそれがフロンティアの血族でも、ポスカトの仲間でもだ」
アキエは頷いた。自分をここから逃してくれる条件がこんなにあっさりしたものでいいのだろうか。
「でも俺は逃げるとこの頭皮のチップが爆発するんだけど」
「それは私とこいつで今摘出する。ちょっとこちらに来てくれるかね?」
男に手招きされてアキエがそちらに向かうとフレデリカが印を結んだ。ちかちかと光っていた点滅が止まったのを確認して男がアキエの頭に指をくっつけると、思い切りチップを皮ごと引っ張った。
「っ痛って!?」
僅かな肉片といっしょに赤いチップが、またちかちかと点滅しているものが男の手中にある。
「こいつにジオの軍部は魔法に頼りすぎると言ったらしいので、今回は魔法を使わないことにした」
しれっと言ってのける。指でチップを潰すあたり、握力はどれだけあるのだろう。アキエは大人しく口答えせずにいた。
「あとはお前をポスカトへ逃がすだけだな」
「ここからポスカトに逃げたらすぐに捕まっちまうぜ?」
「心配ない。時間をゆがめて五年後にお前を逃がす。五年間は少なくとも捕まらないさ。なんせ存在情報そのものが時間を超えるんだ」
なるほど、何もかもジオの魔法でしかできないことである。
「ジオのフロンティア一族からお前に『よろしく』だそうだ。彼女のことなら心配せずとも普通の暮らしをしている。落ち着いたらジオのアンジェリーナを訪ねてみたまえ」
「これ、あんた必要でしょう?」
渡された紫色のコンタクトレンズを受け取り、それを眼にはめ込んだ。金色のちらちらとした光が紫の中に吸収されていく。
「それじゃあそろそろお別れの時間ね。じゃあね、ソレイユ」
印を組む瞬間をぐっと押さえて、フレデリカを引き寄せた。後ろの男が少しばかり眉をしかめたが、気にはしない。
「俺の名前はアキエだ」
「そうだったわね」
「お前の名前はなんていうんだ?」
「あんたみたいに名前が二つしかないわけじゃあないのよ。どのパスポートに使われている名前がいいの?」
自分みたいに名前が二つあることだってめずらしいのに、彼女はたくさん名前があるらしい。
「お前が一番信頼している男に呼ばれている名前は?」
「フレッド」
「じゃあフレッド、プレゼントだ」
男のような名前だと思いつつも、その手にシガレットケースを握らせた。
「最高級だ」
「あらありがとう。あとで吸うわね?」
煙草だと思ったらしい。フレデリカはにっこり笑った。
最後にその唇に口づけしたものだから、いよいよ男の眉はしかめられた。アキエはフレデリカを抱きしめて男に聞いてみる。
「……妬いた?」
「娘を不誠実そうな男にとられた気分だ」
「ああ、なんだ。恋人じゃあねぇの?」
がっかりしたかのようにアキエが呟く。その言葉に男とフレデリカが一緒に噴出した。どうやら本当に親子のようなものらしい。抱き合ったまま、フレデリカがぽんぽんと背中を叩く。
「セスには私が五年間あんたの代わりに手紙送っておくから」
「せいぜい俺ののたくった筆跡練習するんだな。落ち着いたらお前のところに遊びにいくよ。アンジェリーナって人にも会いたいし……」
五年後にはもう彼女は死んでいる。そんなことはわかっていたのに、それでも遊びにいくと約束した。フレデリカは何も答えずに笑ったが、その瞬間少しだけ寂しさを司る情報が体の中を流れた。
フレデリカの指が空を切る。五年間という時間を歪めるのだ、普段のちょっとした動きではなく大きなものだった。
体の情報がばらばらになっていって再構成されていくような感じだった。
黄金の粒子は螺旋を描いて空へと舞い散った。
◆◇◆◇
金色の粒子になったアキエを見送りながらゴンザレスは彼女に近づいた。
「お前をフレッドと呼ぶ男だが……私は少なくとも五人知っているぞ」
「准将のことを准将と呼ぶ男を私は百人挙げられますよ?」
たしかにそのとおりだ。フレデリカの切り返しにゴンザレスは苦笑いをした。
「さて……」
帰る前にもう一仕事ある。
ゴンザレスは窓を開けた。時間が止まっているので風は吹いていないが、それでも少し肌寒い。
銃を構えるような格好をすると人差し指の先にオレンジ色の光が宿った。
心の中で引き金を引けば、光は一直線に流星の如く飛んでいく。それがいくつもの光に分岐してから雨のように武器庫に降り注ぎ、中の火薬が誘爆しあって、あっという間に一帯が燃え尽くされた。
「きれいな火柱……」
呑気にフレデリカが呟く。本当ならば大きな隕石くらい降らしてやりたかったのだが、そこまでするとさすがにジオの軍部が関わっていることに気づくかもしれない。
これだけやっておけば、しばらくヘサの軍部は後始末に追われて動きが取れまい。その間にアキエが逃げたということになるだろう。
ジオの協力まで仰いで手に入れたかった男が、忽然と消える。その上ジオからは約束どおりの謝礼を要求されるではヘサの将軍はきっと悔しがるだろう。
「フレッド、煙草は持ち帰れ。ここに証拠品は残すな。アキエは口紅をつけたりしないからな」
「ああ、そうだった」
うっかり棄てて帰りそうになったフレデリカにゴンザレスが釘を刺す。
フレデリカは自分専用の時計を見た。あともうちょっとで時空間が元に戻る時間である。
「帰りましょうか。それぞれのいるべき場所へ」
「そうだな」
歩きながら二人の姿が霞み、黄金色の足跡になる。やがてはその足跡さえ蒸発するように消えて……あとには何も残らなかった。